|
第二章「上空視点による三人称」 18.指導者 prev * index * next 窓の下の外壁には50cm程度の張り出しがあった。ぴうと吹きつける風に震えながら真沙美は壁に張り付いた。 外側からそっと窓を閉めた。そのままやりすごしてくれないかと期待したが、足音は部屋の前で止まり、窓に近づいてきた。真沙美はそろりそろりと壁を伝った。 「おい、ちょっと君、そりゃ無茶だよ。落ちたら痛いよー」 窓から男が身を乗り出して叫んだ。腕を伸ばして真沙美の服を掴もうとするがもう届かない。 男は整った顔立ちだったが、笑顔は似合わなかった。なにか卑屈に見えるのだ。自分にも他人にも嘘をつき続けていた顔だ。真沙美は顔を反対に向けた。 「ほらー、行き止まりだよー」 真沙美は透明なガラスに阻まれた。 エレベーターだ。半円形に外壁に張り出している。真沙美は目を瞑った。 「ほら、ほら、あきらめろー」 深く息を吸う。不安定な姿勢のままで瞑想する。なにかがお腹の底から湧き上がってくる感じがした。ゆっくりと拳を握り締める。雑音が耳の底のほうに沈んでいくのが分かる。「おい、早く網を用意しろ」男がなにか部下に指示している声も、もう聞こえない。真沙美は目を開いた。 「は!」 素手でガラスを叩いた。ごくんと鈍い音が響く。 「おい、おい、馬鹿な真似はやめ……」 「は!」 真沙美はもう一度叩いた。ガラスにびしりとヒビが入る。 男は息を呑んだ。 「は!!」 3度目にガラスは砕けた。 厚手の硬質ガラスが粉々になって宙に舞った。真沙美は肘で割れたガラスの破片を掻き落とし、空洞の中へすばやく身を躍らせた。エレベーターの箱は下にあるらしく昇降ワイヤーが長く伸びていた。ワイヤーに手を掛けて空洞を下へ降りる。エレベーターの箱に辿り着いたらどうするのか、という疑問はとりあえず打ち消した。映画なんかにあるように管理用の出入り口が付いているかもしれない。真沙美はいまだかつてそんなエレバーターは見たことがなかったが。 「まいったなー」 男は頭を掻いた。まさか、あんな真似が出来るとは思わなかったのだ。 「おい誰か、至急エレベーターを停めろ。このまんまじゃ潰しちまう。あと、各階のエレベーターホールに人をやってくれ」 すぐに追っ手がやってくるのは想像できた。急いでも無駄かもしれない。ワーヤーケーブルは油で滑りやすく、ロープのようなわけにはいかなかった。何度か足を壁面に引っ掛けながら降りていく。暗い縦長の空洞は不安を掻き立てた。じっとりと汗が滲む。 このエレベーターはこのまま地下まで伸びているようだった。底のほうは真っ暗でなにも見えない。今、箱は地下のほうにあるのだろうか。ワイヤーが昇降する気配はなく、どうやらエレベーターを停止させたらしかった。 ずずっ、ずずっと何度か手を滑らせた。そのまま、落下しそうになる。そのたびに壁面に足を突っぱねて制した。曲芸のようだ。 真沙美はだんだんと現実感が希薄になっていくのを感じていた。 だいたい、さっきのはなんだったのだろう。あんなことが自分に出来るとは思わなかった。気がついたらやっていたのだ。『カワスミ マイ』を殺すために格闘技の訓練も積んだが、あんな真似は出来なかった。拳がじんと痛んでいる。 いくつかのエレベーターの扉を通り過ぎた。 追っ手はまったく来る気配も見せなかった。何を考えているんだろう。 ワイヤーを握る手がじんじんと痛む。 何度か、意識が跳びそうになった。 暗く狭い穴のなかで、長時間精神を保てるほど真沙美は強くはなかった。それでも、かろうじて意識を繋いだ。 (私は『カワスミ マイ』を殺さなければならない……) その言葉だけが、深く胸に刻まれていた。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ かなりな時間が経った。 ふと、壁面に小さな四角い穴があるのに気付いた。人ひとりかろうじて通れるくらいの穴。一見、換気孔のように見えた。今までも見過ごしていただけであったのかもしれない。だが、エレベーターの内壁に換気孔など必要なのだろうか? 不自然な気がした。この孔がどこに繋がっているのか、見当も付かなかった。 そして思い出した。 ブルーイーターは宗教色の強い組織だ。それ故に指導者『カワスミ マイ』のカリスマには絶対的なものがある。施設内部には、『カワスミ マイ』だけが使用できる、いざという場合の脱出孔があるという噂だ。実際、そういった仕掛けをしている宗教施設は多い。教祖だけが生き残れば再建は可能だからだ。 この孔がそれの可能性はあるだろうか。 真沙美は少し躊躇したが、結局孔にもぐりこんだ。もう手がいかれかけていた。実際のところ選択肢はなかったのだ。 もし、この孔が『カワスミ マイ』のところまで繋がっていたら…… 都合が良すぎる。 しかし、真沙美は歩調を緩めることなく孔を這って行った。 カワスミ マイ…… ブルーイーターの指導者である彼女はめったにその姿を見せることは無い。真沙美も直接顔を拝んだことはなかった。ビデオ映像で見る彼女は凛として気高く、無表情だった。歳も若く、まだ二十歳にもならないと聞く。だが、その彼女の命令は絶対だった。多くの者が命を賭してテロリズムに手を染める。家族を捨て、友人を捨て、笑って手榴弾のピンを抜ける者が五万といるのだ。 彼女は現代の生き神であった。真の理想を具現化できる、そう信じさせるだけのものが備わっていた。 こんな話がある。 まだ、ブルーイーターが宗教法人であったころ、統制社会の脅威として、政府の特別機動隊の襲撃を受けたことがあった。追い詰められた指導者マイは、数人の側近に付き添われながら銃器に身を包んだ男たちの前に出た。 そして、おもむろに、すらりと腰に設えていた剣を抜いた。 機動隊の間に緊張が走った。最後の抵抗に出ると思ったのだろう。しかし、マイはそれを高く掲げると、すっと自分の腹に突き刺した。 男たちは目を見開いた。敵わないと悟り自害の道を選んだか、と目を伏せたものもいた。多くの者は声を発することも出来ず、そのままマイを凝視した。 マイは剣を抜いた。 血が溢れ出ると誰もが思った。剣は幅広で、腹には大きな孔が穿たれたのだ。無事で済むはずがなかった。 だが、マイは無表情のまま立っていた。 多くの者が注視するなか、マイの傷はみるみる塞がっていった。そして、こう言った。 『去れ』 この話の真偽は定かではない。 だが、こういった噂がいくつも重なり、現在のブルーイーターを支えている。真沙美はトリックに違いないと思っている。それくらいいっぱしの手品師ならいくらでも演出できるだろう。要するにブルーイーターは詐欺組織なのだ。真沙美はそう信じている。 孔は終点に近づいた。 薄明かりが壁面を照らし出した。淀んだ空気が入れ替わっていった。真沙美は外に出た。 そこは、使われていない暖炉だった。数本の炭が積まれて入口を隠していた。真沙美は煤を払って立ち上がった。 部屋は薄暗かった。片隅にベッドが置かれている。ベッドには天蓋がついていて内部の様子は伺いようがない。他には家具はなく、どうやらここは寝室のようだった。 真沙美はごくりと喉を鳴らした。 カワスミ マイがいるのか? ここが、指導者の寝所であるのは間違いがないように思えた。すると、あのベッドには……。真沙美はゆっくりと近づいた。 (……いない) ベッドには誰もいなかった。 「――!!」 ぱっと部屋の明かりが燈った。 豪奢な扉が重々しく開いて、男がひとり入ってきた。 「お疲れ様でした」 男が丁寧に頭を下げて言った。真沙美は身構えた。 ずきりと頭が痛んだ。 極度の緊張のためか、また意識が途切れそうになる。 男は、真沙美が敵意を剥き出しにしているのを見て、面倒くさそうに首を振った。 「こういうのは、あんまり良くないんですよ。ホントはな……」 ふところから、小さな筒状のものを取り出した。そこからしゅっと霧が噴出する。 ガスだった。 ぐらりと頭が揺れた。辛うじて保っていた意識が根こそぎ奪われる感覚があった。 真沙美は倒れた。そして、倒れる瞬間、男が言った言葉も聞き取れなかった。 「まだ寝るには早いんです。指導者マイ様……」 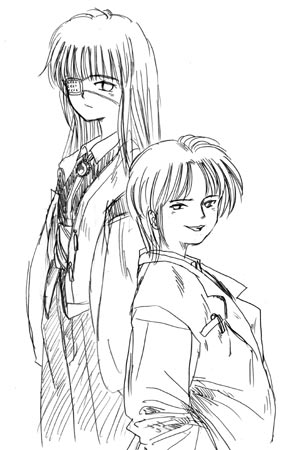 桑木真沙美はそのまま、天蓋つきのベッドに寝かされた。 「もう、大丈夫だ。次に目覚めるときは、我らがマイ様であるはずだ」 男――国立宇都(クニタチ ウト)は、駆けつけた女に言った。 「今回は長かったわね。自覚がないってやっかいだわ」 女――井能江可雁(イノウエ カカリ)は、うんざりするように言った。 「仕方ないだろう。これはKanonの特性だ。人格の解離――いわゆる多重人格であるのは確認されている全てのKanonに共通する。マイ様の場合、たまたま元人格が物騒な人間だっただけだ」 「それでも、圭洋の真琴のように、元人格とうまく折り合いをつけている例もあるわ」 「あの姉妹は、そのほかの部分が特殊だ。うちのマイ様は能力もずば抜けている。そのへんでは優位にあるよ」 宇都は満足そうに首を振った。彼はしばしば『川澄舞は自分が創った』というような発言をして周囲の反感を買っている。 「そうそう、その真琴だけど、ついに圭洋が4人目捕獲に、真琴を投入したようよ」 「なんだって?」 「ついさっき工作員から連絡が入ったわ。ナンバーズが真琴を連れて、尾瀬に入った。間違いないわ」 「まずいな……Kanon同士が接触した場合の影響は未知数だ。何が起こるか分からん」 「マイ様にも行ってもらうべきかしら」 「それはいけない。それこそどうなるか……君のところで動ける者は何人いる? ONEの工作員も動いているということだし……もう傍観は出来ない」 「わかってる。亜夷夜(アイヤ)と霞(カスミ)が動かせるわ」 「武器を揃えよう。明け方には手配できるだろう」 可雁はベッドに横たわる邪気のない顔を眺めた。この娘から全てが始まったのだ。全てを手にするのは自分たちでなければならなかった。 「どうやら私たちは出遅れている。でも、まだ間に合うはずよ」 |