|
第一章「三津木弥生による一人称」 3.鍵 prev * index * next 真臣の住むマンションは、私鉄沿線の駅からそう遠くない所にある。当然、電車を使ったほうが通勤も楽だし、なにより酒を饗する職種なのだからそうするのが当然だ。だが、真臣は車を使っていた。 飲酒運転になるから不味いだろうという忠告を受けたことは少なからずあったが、そのたびに同じ言葉を返した。 「私は職場ではお酒を飲みませんから」 そう、真臣は店で一切酒を飲まない。客からいくら勧められても決して飲まないのだ。『エラトステネス』には一見の客は来ないし、客達も酔ってバーテンダーに絡むなどといった輩は皆無なので問題になったことはないが、まったく飲酒を嗜まないバーテンダーというのも少ないのではないか。下戸というわけではない。カクテルアーティストや愛飲家たちの協会にも籍があり、コンテストで入賞したりしている。カクテルの研究をするときなど、実際に自分で酔いつぶれるまで試したりもする。しかし、職場では飲まない。酔うと感覚がおかしくなるから客に充分なサービスが出来なくなる、といつも言う。彼女なりの職業意識だった。客に愛想を振り撒いたり、楽しい話題を振ったり、一緒に酒を飲んで笑ったりするのは、俺たちウェイター兼ホストの役目というわけだ。彼女はそれを管理する立場なのである。管理者が一緒に酔ってしまうわけにはいかない。 しかし、実は他の理由があることを俺は知っている。 真臣は酒癖がわるいのだ。猛烈に。 笑う、泣く、怒るの三種の神器に、絡む、脱ぐまで付いて来る。彼女自身、これで失敗したと思うことが多多あったのだろう。そのいくつかは俺も知っている。 ともあれ、そのお陰でこうして車で移動できた。 真臣の酒癖の悪さに感謝したのはこれが初めてかもしれない。 駐車場にも不審人物は見当たらなかった。いくらなんでも車に発信機でも付けられていない限り、追ってくるのは無理だ。ひとまず安心していい。 なるべく音をたてないように階段を上がると、首藤のプレートの掛かった扉を押した。 「見て、これ」 中に入るなり、真臣は奥の部屋から手招きをして俺を呼んだ。もう、部屋着に着替えている。恐るべき素早さだ。 「彼女は?」 「汗臭かったから、先にお風呂に入らせた。んで、これが収穫」 脱衣所からくすねてきたらしい。彼女のウエストポーチだ。白い翼を広げたようなマークは見たことがないが、まずはありふれた代物だ。 事情は聞かないと言ったが、調べないとは言っていない。真臣もそのつもりだったようだ。実に頼りになる。しかも行動が早い。 「見事になんもなし。財布も、定期入れも、ケータイも」 逆さにぱらぱらと振った。中からは葉っぱが一枚出てきただけだった。 「その葉は?」 「さぁ、どっかで紛れ込んだんじゃない?」 よく見るとプラスチックの作り物だ。おかしな趣味もあるものだ。とりあえずポーチとともに手早くデジカメに収める。 「あとは、これくらいかな」 内ポケットに小さな金属片が入っている。 鍵だ。 「でも、これだけじゃねぇ」 キーホルダーの輪ッかに指を通してくるくると弄ぶ。 どこか、遠くを見ているような表情になる。真臣はどちらかというと童顔のほうだ。俺よりひとつ歳上だとは思えない。もっとも、髪を頭の両側で結んでいる、いわゆるツインテールのために幼く見えるのかもしれない。普通、二十歳を過ぎた女性がする髪型ではない。(と思う) ちらちらと物問いたげな視線が送られる。直感だけで身元不明の少女を連れてきた。迷惑なのは判っている。しかし、それを口に出さないだけでなく、最大限の協力をしてくれる。いい奴、の一言では片付かない。 「真臣、少し時間稼げないか」 俺は鍵をじっと見つめた。 「んー……判った」 眠そうな目を少し逸らせて、頷いた。 真臣は、思案するポーズすら見せずに、浴室のドアをそっと開けた。 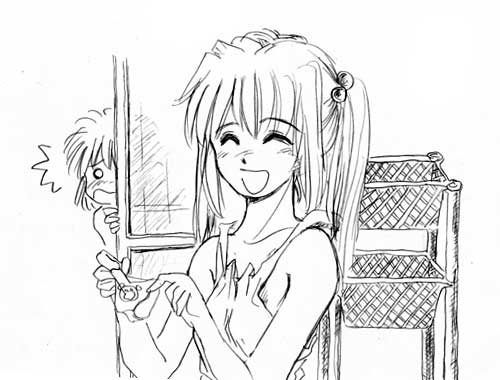 「どぉーもぉ」 息を呑む気配が感じられる。俺は少女に同情した。 真臣は遠慮なく脱衣篭の中を弄った。ガラス越しに浴室の中からその動作が見えているはずだ。 「あ、あの」 シャワーの音が止まった。 「わぁ、可愛いぃぱんつ。でも汗だくだし、洗っちゃうわねー」 「あ、あの、別に……あの、うぐぅ……」 洗濯機をごんごん回し始める。 「大丈夫、着替えならカレに買ってこさせるから」 「あ、あのッ……」 「ねぇ、わたしも一緒に入っていいかな?」 「え……えええ!」 「普通のワンルームより浴槽広いでしょ。新婚さん向けなのよ、それ」 衣擦れの音が聞こえる。真臣は容赦ない。本気で一緒に入るらしい。ほとんどエロばばぁだ。しかし、適切である。これで、かなり時間が稼げるし、俺がいなくなっていても不審に思われることもない。浴室の様子は窺い知る術もないが、彼女の緊張感を和らげる効果があることを期待しよう。 俺は急いで部屋を出ると、商店街に向かった。 * その時、マンションの前を一台の清掃会社のバンが通り過ぎた。車の横に大きく会社の名前が書かれている。車内では、作業着とセットになった帽子を目深に被っている男がひとりで運転をしていた。宣伝カーを兼ねているらしく、助手席にはメガホンも用意されていて、車は住宅街をゆっくりと循環するように流している。 そして、運転席の男は携帯に口を寄せ、聞き取れないくらい小さな声で呟いた。 「……こちら008、雪うさぎは中庭に入った。繰り返す、雪うさぎは中庭に入った……」 |