|
第2話「海鳴へ」 (作:A−140) 2 海鳴へ 床に大の字に寝そべって、ぼんやりと天井を眺めながら、何となく考え事をする。 それは、貞俊が時折見せる癖だった。いつ頃からこのようなことをするようになったかは、当人もよくわからない。ただ、彼がこんな姿を見せるようになったと同時に、 「お前は、何でそういうところまで爺さんに似たのかね」 と、伯父や伯母たちから笑われるようになってしまったのは確かなことであった。 この日、貞俊は比較的心地よく目覚めていた。昨日あれこれ思い悩んでいたのも事実だが、既に事は始まっているのだから、じたばたしたところで仕方がない。そこは軍人だの警防隊員だのを職業として選ぶだけあって、それなりに腹は据わっているようだった。 「貞俊」 さて海鳴へ行ったらどうするか、などと考えようとしたところで、扉の向こうから声が聞こえてきた。もっとも幸恵は朝食を済ませた後、友人と出かけるとかで既に留守だったから、この声の主は父親以外にあり得ない。 「どうぞ」 扉が開くと、正俊が部屋に入ってきた。 「どうした、考え事でもしてたか?」 「……うん。何とはなしに、いろいろとね」 半分は嘘である。正確には『何か考えようとしていた』というところであり、それをまとめるには少々時間が不足していたのだった。 「ところで、そろそろ出かけなくていいのか?」 「ちょうどいいと思っていたところだよ、用意は出来ているから」 「そうか、わかった」 正俊は部屋を出て行き、それを見届けると、貞俊もゆっくりと立ち上がった。 「よし、と」 着替えを終え、玄関に出て靴を履いて荷物を持つ。準備万端であった。 「車は問題ないか?」 トランクを開け、荷物を積み込む貞俊の背中へ、外に出てきた正俊が声をかけた。 「昨日確認しておいたけど、問題ないね。いつも大事に乗ってくれているようで、ありがとう」 香港警防隊に入隊して以来、これまで貞俊は日本に帰る機会がなかった。そのため二年ほど前に自分で購入したこの車も、自分で運転する機会に恵まれていなかったのだ。 現状、この車は塚原家の予備車という扱いになっている。故に使われる機会は決して多くなかったのだが、それでも父母や従姉たちがこの車を使用し、たまにではあるが、正俊が自ら整備してほぼ万全の状態にしてあった。 「お前、車の運転は久しぶりじゃないのか?」 「そうだね……」 作業をしながら、少し記憶を辿ってみる。 「言われてみると、本当に久しぶりだね。向こうではあまり自分で運転はしないから」 「なら、勘も鈍っているだろうから十分気をつけろよ。途中で事故なんかしたら大変だからな」 「……」 荷物を積み終えて、トランクを閉めると同時に軽くため息をつく。貞俊は少し暗い表情をして、首を振りながら言うのだった。 「友達が交通事故に遭ったばかりだからね、気をつけないと」 「そうだったな、すまない」 それを聞いて、僅かに表情を緩める。それから運転席に座ってエンジンを始動し、窓を開けて父親の顔を見た。 「じゃ、行ってくるよ。母さんによろしく」 「ああ、気をつけてな。愛ちゃんや耕介君にもよろしく言っておいてくれ」 「わかったよ、それじゃ」 サイドブレーキを解除して、車を発進させる。久しぶりに本来の主人を得たシルバーのギャランは、滑らかに走り出していった。 貞俊の実家がある横須賀市から海鳴市までは、だいたい三、四時間ほどかかる計算になる。少し余裕を持って家を出たから、耕介の見舞いをするにしても、さざなみ寮に行く約束の時間には間に合うはずだった。 そうして車を走らせたのだが、時間の見積もりに余裕を持たせすぎたらしく、海鳴市を目の前にして、耕介を見舞うにしてもまだ時間が余るという状況になった。 「どこかで時間をつぶすか」 高速道路を降りるインターをひとつ手前に変更して下道を走り出したが、それでもまだ暇つぶしの必要な状況に変化はない。 だが海鳴に近づくにつれ、貞俊の表情は厳しいものへと変わっていた。緊張し始めていたのである。 (もう長く来ていないが、今の海鳴はどうなっているのかな) 街も大きく変わっただろうし、そこに住む人々もまた変わらずにはいられないだろう。新たな知己を得る事にもなるはずである。そして、今度のことが貞俊自身に何かをもたらす可能性もあった。今はまだ見当もつかないことだが。 それに何より、彼にとって海鳴とは、どうしても忘れることの出来ない経験をした土地であったのだ。 運転を続けながら、ふと右側のほうを見る。すると視線の先に、見慣れない洒落た雰囲気の公園が認められた。 (あそこは、確か臨海公園じゃなかったかな?) 自分の記憶に留めてある臨海公園の光景との違いに、戸惑いを覚える。しかし考えてみると、貞俊が最後に海鳴を訪問したのは十年近くも前のことである。今に到る間に、町の様子はもちろん、公園そのものの風景が大幅に変わっていたとしても何ら不思議はない。 そんなことを思いつつ、時計へと目をやる。すると、耕介を見舞う時間までまだ一時間ほど余裕があった。 (……寄っておこう) 少し迷ったものの、そう決断する。そして、道端の『海鳴臨海公園南駐車場 ↑200m右折』という看板に従って車を進めるのだった。 今の貞俊はもちろん知る由もないのだが、ここ海鳴臨海公園はデートスポットとして相応に有名な場所で、特に学生や旅行者の間で人気が高かった。もっとも、仮にそれを知ったところでほぼ間違いなく、自分には縁のない話だと軽く流してしまっただろう。 それに彼にとって、実はここは忌まわしい記憶が残る場所なのである。そうした軽めの話題の種にするには、その出来事は少々重すぎた。 「随分と変わったんだな、この公園も」 駐車場に車を止めて、かつての記憶を頼りながら公園の中を歩いてみる。この公園については『自然物と人工物のバランスがよい』という評価があり、それが人気の高さの理由となっていた。貞俊もそういう観点では、これまで自分の知っていた臨海公園よりも好印象を抱いたのだった。 「ここだ、間違いない」 しばらく歩き、海に面した道の途中で立ち止まる。そして近くにベンチがあるのを見つけて、そこへと座った。 (少し、疲れた) さすがに三時間も休憩なしで車を運転すると、若くもあり、体も鍛えてあるとはいえ多少は疲れも感じるようで、ここでようやく一息つくことが出来た。そして、目前のある一点に目を注いでから、今度はまぶたを伏せて過去の記憶をたどり、そのまま考え事を始めた。 (もう十六年、か) 十六年前、目の前のこの場所で起こった事を思いだすと、未だに背筋が凍るような思いに駆られることがある。それは、きっと今後生きている限りずっとそうだろうと、貞俊はそんな気がしてならない。 それだけ、その出来事は彼の心に深く刻み込まれている。そして、そのことが今の自分自身を形作る契機になったというのは、恐らく間違いない事だろう。 (私は……今の自分は、あのときの過ちを償えるようになっているんだろうか) 空には雲ひとつない、よい日和である。その下で元気よく遊ぶ子供たちの声も聞こえてくるし、海のほうに目をやれば、日差しに波頭が白く輝いているのが美しい。だが、今の貞俊はそのいずれもが、意識の内に入り込んでこなかった。 静かに息を吸って、大きく吐く。そうしてから、ゆっくりと目を開けた。 「まあ、過ぎたことばかり考えているわけにもいかないな」 呟きながら、自分の頭を数回、軽く叩く。確かに、今度この海鳴に来たのは仕事のためであって、このような場所で郷愁に浸るためではない。まして、その職場は自分にとって困難なことが待ち受けているはずなのだ。 今は、その仕事にこそ集中するべきだろう。そう思い直したのだった。 それから、少し勢いよくベンチから立ち上がる。そして、駐車場の近くの屋台でホットドッグを購入して軽く腹ごしらえをしてから時計を見ると、十三時近かった。 「さあ、行こう」 自身を元気付けるように張りのある声で言ってから、貞俊は駐車場の車へと歩き始めた。 今回の最初の目的地である海鳴大学病院は、臨海公園から少し西へと向かったところに建つ、この周辺では最も大規模な病院である。神奈から聞いたところによると、さざなみ寮の住人もよく世話になり、また信頼できる先生もいるので安心なのだそうな。 病院の駐車場に車を停めると、貞俊はまず受付で耕介の病室の場所を確認した。そして、そこへと歩いていく。 (そういえば、耕介と直接会うのは海軍を辞めたとき以来になるんだな) 歩きながら、ふと考える。この記憶が正しければ、耕介の顔を見るのはおよそ三年ぶりということになる。 (あいつが今の自分の仕事を知ったら、どう思うだろう。いつまでも隠しておけることではないのかもしれないが……) そこまで考えた次の瞬間、後悔して大きく首を横に振った。 (いや、自分のことは話すまい。むしろ絶対に話してはいけないことだ。あいつには平和な日常で心置きなく管理人の仕事を続けてもらいたい。自らの手を血で染めるような世界なんて、教える必要もないことだ) そんな結論が出たところで、耕介の病室の前へと着く。さっきの思考が念頭にあったためであろうか、少し緊張があった。 「ふう」 軽く深呼吸して、背筋を伸ばしなおす。その動作を経て、とりあえず表面上の平静さは取り戻したようだった。 そうしてから、とんとん、と扉を二度叩いた。 「どうぞー」 記憶にあるそれより少し弱々しい、久しぶりに聞く声。それでいて、貞俊の耳によく馴染んだ声であった。 懐かしさと、いくらかの安堵感を感じながらゆっくりと扉を開ける。そしてその目の前に、ベッドに身を横たえる懐かしい男の姿が認められた。 少し歩みを速めてその相手に近づくと、貞俊は笑顔で右手を差し出した。 「久しぶりだな、耕介」 「……はい、先輩。お久しぶりです」 答えて、耕介もまたゆっくりと右手を差し出し、二人は握手を交わす。互いにとってそれは、ひどく懐かしく思える行為であった。 「今度のことは、災難だったな。だけど、思ったより元気そうだから少し安心したよ」 耕介に勧められて席に着いた貞俊は、開口一番、そう言った。 「ところで、怪我の具合はどうなんだい?」 「全身打撲と、あと両足骨折ですね。といっても、思ったほどひどくなかったので、足が治ればすぐ退院できると思います」 「そうか。しかし、車に轢かれてよくその程度ですんだな」 「無駄にでかい体も、たまには役に立つみたいっすね」 その答えに、貞俊は笑った。普段、声を出して笑うことが多いとは言えないのだが、それでも昔馴染みの耕介が相手のときは、こういう表情を見せることも少なくなかった。 「そういう口がきけるなら大丈夫だ。ともあれ、早くよくなるといいな」 「ええ、寮のみんなが待っていますしね」 「そうだな」 「ところで……」 ここで、耕介は口調を改めた。 「愛さんから聞きましたが、俺の留守中、先輩がさざなみの管理人をしてくださるんですね。ありがとうございます」 「……ああ、神奈さんに泣きつかれたから。流石に断りきれなかった」 「はは」 「どうも、昔からあの人は苦手だよ。まして今でもいろいろと世話になっているから、どうしても頭が上がらないんだ」 少し困ったように、貞俊は首を振る。 「それは俺も同じですよ……俺がさざなみに就職したのだって、神奈さんに騙されて送り込まれたからですし」 「そうだったな。となるとお互い、神奈さんの被害者ってことになるか」 「そうっすね」 言い合って、二人は大笑いした。 「まあ、こういうことになった経緯はともかく……」 しばらくして笑いを治めると、今度は貞俊が口調を改め、にわかに起立して深く一礼した。 「管理人の仕事、至らぬ点も多いかと思いますが、精一杯努めさせて頂きます」 「せ、先輩。そんな改まらないでくださいよ」 耕介はさすがに呆気にとられたが、その内心は同時に、妙に納得できるものもあった。彼の知る貞俊は自分に優しくしてくれると同時に、少し固くて必要以上とも思えるほど気を使う男だったのだ。 それは、耕介が貞俊を尊敬できる先輩と仰ぐようになってから、いや、最初に出会ったそのときからまるで変わらないことだった。 「そんなに難しく考えなくても、大丈夫ですよ。まあ座ってください」 再び貞俊が席に着くのを見てから、耕介は少ししんみりした表情で口を開いた。 「管理人の俺が不注意でこんなことになって……本当に、寮のみんなに迷惑をかけて申し訳ないって思っているんです」 「……」 昔から、黙って耕介の話を聞くということは少なくない。そして穏やかな口調とは裏腹に、耕介の気持ちが非常に重いものになっていることを理解した。 「先輩にはほんと、感謝してます。俺が抜けるのは申し訳ないけど、先輩が代わってくれるなら、今日からはみんなにあまり迷惑をかけなくてすみますから」 「……そう言ってもらえるのはありがたいが」 今の貞俊は、恐縮したとも、困ったようなとも取れる表情だった。 「少し、買い被りじゃないか。私に管理人が勤まるかどうか、まだわからないんだぞ」 「ははは、俺が勤まっているんですから、先輩に勤まらないわけがありませんよ」 そういう問題なのかと思わなくもないが、口には出さなかった。 「確かに、俺も最初はいろいろ大変でした。でも、あの寮の人たちはみんないい人ばっかりですから。先輩なら、きっとうまくいくはずです」 「そうか、ありがとう」 それから、二人は管理人の仕事についていくつかの事項を確認した。おおよそのことは貞俊も神奈から聞いていたし、現場で愛や住人たちから聞くこともあるだろう。だが本職である耕介から、仕事の『コツ』というものを聞けるのは、非常にありがたいことだった。 「……とりあえず、このあたりですね」 「わかった、十分注意しておくよ」 この話の中で、耕介は寮生の性格に関しては特に語らなかったし、貞俊も聞こうとはしなかった。 貞俊にとって、さざなみ寮の住人は大半が初見の相手となる。だから、もしここで耕介から何か聞いてそれを仕事に反映させたりすると、かえってわざとらしくなってしまい、彼女らから不信を買う可能性も十分に考えられたのである。 (まずは会ってからだ。それから、自分なりに誠意を尽くすことから始めないと) そうして話が一段落したちょうどそのとき、病室に看護士が入ってきた。 「槙原さーん、そろそろ検温の時間ですよ」 「はい、わかりました」 それを聞いてから時計を見て、貞俊は席を立つ。 「じゃあ、そろそろ失礼するよ。くれぐれも大事にな」 「ありがとうございます。先輩も管理人の仕事、よろしくお願いします」 「……ああ、頑張るよ」 内心、不安を抱えていることなど、特に耕介には絶対に見せられないことである。笑顔でそう答えてから、すっと右手を差し出した。 「折を見て、また見舞いに来るよ。それまで元気で」 「先輩も」 再び耕介と握手を交わして、病室を出て行く貞俊だった。 駐車場の車まで戻ってきてから、再度時計を確認する。寮へ顔を出す約束の時間まで、あと三十分ほどというところになっていた。 「よし、行くか」 また、少し気合を入れなおすように声を出してから、貞俊は車を発進させた。 さて、目的地であるさざなみ寮は、海鳴市の桜台というところにあった。地名のとおり、あたりは春になると満開の桜に覆われるのである。 この周辺はほとんどが私有地であり、また自然保護区として立ち入り禁止になっている区域も多かったため、見ず知らずの人間が簡単に立ち入ることの出来ない場所でもあった。 「この辺りは、何も変わっていないな」 十数年ぶりの、それでいて変わらない風景を見ながらしばらく走ると、目指すさざなみ寮が視界へと入ってきた。 (とうとう来たか……) 彼自身、この寮には父母や親戚と共に何度か訪れている。外見はその頃と同じように、寮というより小奇麗なペンションという感じを保っていて、そういう意味では非常に懐かしさを感じることが出来た。 だが今回、貞俊はここに仕事をするために来ているのだ。しかも、もう昔のような子供ではないのである。 (ここで、いろいろ考えても仕方ないんだが) とはいえ、さすがに緊張は禁じえない。この場所はいわゆる『男子禁制』の女子寮であり、これからその場所における唯一の男となるのだ。意識するなというほうが無理な話だろう。 いったん車を玄関先に駐車し、いくつかを除いてトランクから荷物を出すと、貞俊は寮の門前へと立った。 「ごめんください」 「はーい」 インターホンを押して声をかけると、可愛らしい返事と共に扉が開く。そこから出てきたのは、小柄で髪の長い女の子だった。 その子に一礼してから、貞俊は穏やかな口調で言った。 「こんにちは。今度、管理人代理としてこちらにお世話になります、塚原です」 「あ、うかがってます。どうぞー」 案内されて、寮の玄関をくぐる。すると、女の子は奥へと声をかけた。 「愛お姉ちゃん、塚原さんが着いたよー」 「あ、はーい」 もうだいぶ薄れてはいたが、それは貞俊にとって記憶に残る声である。そして、廊下の奥から歩いてくる女性の姿は、やはりどことなく記憶の片隅に残る面差しを持っていた。 「貞俊……さん?」 「はい、愛さん。久しぶり」 「お久しぶりです」 そう言いあって、互いに軽く頭を下げる二人だった。 挨拶を終えてから、貞俊は愛と最初に出迎えてくれた女の子と、彼の部屋として割り振られた103号室へと入った。 ここは本来、耕介の部屋である。だが現在のさざなみ寮には空き部屋がなく、また生活に必要な家財道具がとりあえず備わっていることもあって、一通り清掃したこの部屋を貞俊に利用してもらうことになったらしい。 「ごめんなさい、別のお部屋を用意できればよかったんですが……」 「いえ、寝る場所があれば十分です。ありがとうございます」 そう言いつつ、貞俊はベッドに荷物を置いた。 「そういえば、車はどこに止めればよかったでしょうか?」 「あ、途中にあった駐車スペースに空きがありますよね。そちらに止めていただけますか?」 「わかりました。では早速、車を動かしてきます」 「お願いします。知佳ちゃん、案内してきてくれる?」 「はーい」 部屋を出ようとすると、貞俊は知佳と呼ばれた女の子に声をかけられた。 「私、207号の仁村知佳っていいます。姉の真雪と一緒に、こちらでお世話になっています」 「よろしく、私は……」 「塚原貞俊さん、ですよね。愛お姉ちゃんの古いお知り合いで、耕介お兄ちゃんの先輩の」 「あ、はい」 お姉ちゃん、お兄ちゃんという言葉に少し戸惑ってしまったのだが、次の知佳の説明で納得することができた。 「ああ、この場合のお姉ちゃん、お兄ちゃんってのは、愛称なんです」 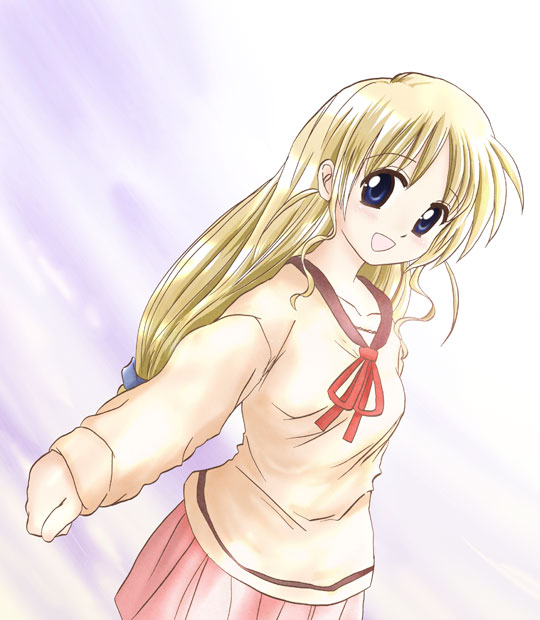 「そうなんだ、なるほど」 しかし、耕介が昔から妹を欲しがっていたことは知っているが、まさか自分から頼んで言わせたんじゃないだろうな……と、一瞬だけ考えてしまう貞俊であった。 「塚原さんのお話、お兄ちゃんから聞いてます。これからよろしくお願いしますー」 「いや、こちらこそ至らないところが多いと思うけれど、どうかよろしくね」 そう言って、貞俊は改めて知佳に一礼する。すると知佳のほうも、ちょこんとお辞儀を返したのだった。 再び車に乗って、貞俊は知佳の誘導で寮の駐車スペースへと移動させた。 「おや、これは」 駐車場で一台の車を目にして、ひどく驚いた。彼が最後に訪れたとき、そろそろ引退するのだろうとばかり思っていた赤いミニが、まだそこに姿を見せていたのである。 「このミニ、まだ動いていたんだ」 それを聞きつけたのか、知佳が声をかけてきた。 「あれ? 塚原さんもミニちゃん、ご存知だったんですか?」 「うん、愛さんのお爺さんが亡くなられてから、私の父親がたまに乗ったり、整備してたりしてたんだ。そうか、愛さんが乗るようになったのか」 「はい。愛お姉ちゃんにはこの車はお爺さんの形見だから、とっても大事に乗っているんですよ」 その説明を聞いて、貞俊も感慨深くなったものである。 二人がリビングに戻ると、愛が茶を淹れて待っていた。他の寮生たちは用事やら何やらで全員留守なのだという。 「そういえば、前に貞俊さんとお会いしたのはいつでしたっけ?」 「あれは……確か、こちらへ最後にお邪魔したときですね。もう十年くらい前になりますか」 出された緑茶を飲みながら、そう答えた。 「正俊おじさんと幸恵おばさん、お元気ですか? 最近お忙しいみたいなので、しばらくお会いしてませんけど」 「二人とも、元気ですよ。ご無沙汰しているのを気にしているようで、機会があればこちらにも伺いたいと言っていました」 そんな話をしていると、貞俊はリビングに別の気配を感じた。 「あ、美緒ちゃんおかえりー……って、どうしたの?」 知佳に呼ばれたその女の子は、黒い髪と服装をした小学生くらいの子であった。 (美緒ちゃん……ということは、この子が啓吾さんの) 時折、話に聞く愛娘なのかと思う貞俊だった。 「美緒ちゃん、こちら耕介さんの代わりに来てくれた塚原さん。ご挨拶は?」 「……」 愛に言われた美緒だったが、何か怒っているような、恨めしそうな、そんな表情で貞俊のほうをじっと睨んでいるだけである。だが、睨まれたほうはこのまま黙っていることもできない。 「こんにちは、よろしく……」 「!!」 まずは挨拶をしながら、貞俊はゆっくりと近づこうとした。すると、美緒はびっくりした様子で凄い勢いで走り去ってしまった。 「あ、あの」 あまりに急なことだったので、貞俊のほうもすっかり驚いて、何か悪いことでもしたのかと思わず愛と知佳の顔を交互に見てしまう。すると、愛が申し訳なさそうに言った。 「ご、ごめんなさい。美緒ちゃん、ちょっと男の方に人見知りする子なので」 「そうでしたか……」 「で、でも、お兄ちゃんが来たときもこうだったんだけど、今はとっても仲良しだから」 「そうね、だからそのうち貞俊さんにも慣れると思うんですけど」 「……」 そう簡単にはいかないかもしれない、と口にこそ出さないが、貞俊はそう考えていた。 美緒の態度から、貞俊は強い敵意を感じていた。あの視線と表情からは、自分に対する好意を全く感じることが出来なかったのだ。 もちろん、初めて会う相手からいきなり敵視される理由は無いはずである。それだけに、どうしてそう思われるようになってしまったかなど、今の彼にわかるはずもなかった。 (どうやら、そんなに簡単なことではすまないらしい) 今度のことは決して楽観できないであろうと、この時点で多少なりとも想像はしていたし、それなりに覚悟もしていたはずだった。だが、その想像や覚悟さえ、あるいは楽観的だったかもしれない。漠然とではあるが、貞俊はそう考えざるを得ない心境になっていた。 お茶が一段落してから、貞俊はいったん部屋に入った。とりあえず今夜の夕食を用意する前に、自分の荷物を整理しておきたかったのである。 (美緒ちゃんは極端なこと、と思いたいが) 整理を終えて一息つくと、ベッドに横たわって考え事を始める。 (しかし、愛さんは最近会っていなかったにせよ、古い知り合いだ。それに、あの知佳さんのように男に人見知りしない子は、むしろ珍しいだろうから) そう考えると美緒ほどではないとしても、ここの寮生から多少なりとも拒否反応を受ける可能性は高かった。女子寮に若い男がいるという時点で、相応の反感を買うのは当然だからだ。 また、本来の管理人であるの耕介が、不慮の事故で留守にせざるを得なくなっている状況である。そのため、当然寮生たちの精神状態も穏やかなものではないであろうと想像された。 (と、なると……予想以上に、自分に対する風当たりが強くなると覚悟しておいたほうがよさそうだ) 現実から目をそむけるわけにもいかないが、あまりこういうことは考えたくなかった。こんな有様では、ますます気が重くなるだけだ。 (だけど……自分はやることをやって、啓吾さんや神奈さん、そして愛さんと耕介の信頼に応えるしかないんだ) 内心の不安を意識しつつも、そう割り切ろうと努力する貞俊であった。 十六時ごろ、貞俊は夕食の用意をするためキッチンへと向かった。愛からはゆっくりするように言われていたのだが、仕事で来ているのだからこれくらいのことをするのは当然と考えたのだ。 「あれ、塚原さん」 キッチンには知佳が立っていた。 「ゆっくりしててよかったのに」 「仕事で来ているから、やることはきちんとやらないとね」 そう言いながら、貞俊は持ってきたエプロンをかける。これが結構似合っているものだから、あるいは耕介など彼の古い知り合いが見たら笑うかもしれなかった。 「とりあえず、何をすればいいかな?」 「えーと、じゃあ……」 少し考えてから、知佳は野菜が入っているボールを指して言った。 「この皮をむいた玉ねぎとニンジン、ピーマンをぶつ切りにしてもらえます?」 「うん、わかった。この材料からすると、これは酢豚用だね?」 「はい、そうですー」 聞き終わるや否や、貞俊は包丁を手に取り、一気に切り始めた。 「……!」 その動作を傍らで見ていた知佳が、驚いて言葉を失ってしまう。どうかしたのかと聞いてみると、知佳は少し口ごもりながらようやく返事をした。 「え、えーと……あ、あんまり切るのが早いから、ちょっと驚いちゃって」 「ああ、なるほど」 あまりそういうことを意識したことがなかったので、返答も少し素っ気無くなってしまった。 「そうだね、刃物なら……」 言いかけて、危険を感じていったん言葉を切った。 「あ、いや。一応、包丁の扱いには慣れているからね。でも、それは耕介も同じじゃない?」 「お、お兄ちゃんも切るの早いけど、塚原さんほどじゃ……」 「そうなんだ」 確かに自分の置かれた環境を考えれば、刃物の扱いについて耕介より熟練するのも当然だろうと思うしかなかった。 そうこうしているうちに夕食の準備は順調に進み、間もなく完成というところまでこぎつけていた。 「ただいま」 「ただいまです」 玄関から声が聞こえてきた。 「あ、ゆうひちゃんとみなみちゃんだ」 知佳が手を休めて、廊下へと歩いていく。 「ゆうひちゃん、みなみちゃん。新しい管理人さんが来てくれたよ」 「おお、そうか」 「もうすぐご飯できるから、しばらくしたら降りてきてね」 「うん」 そんな会話を聞きながら、調理しつつ時計を見る。 (そろそろ、夕食の時間かな) とりあえず、最初の仕事は問題なく処理することが出来そうで、貞俊はひとまず安心したのだった。 夕食どき。 リビングには愛と知佳、貞俊から一番離れたところに美緒が座っていた。美緒は相変わらず貞俊に対して、敵意に満ちた視線を送り続けていた。 また彼女たちの他に、先ほど帰ってきた人たちだろう。知佳より一回り背が低い、元気のよさそうなショートカットの女の子と、そうしたことへの関心が薄い貞俊の目から見ても『美人』と形容するしかない、背の高い、少しウェーブのかかったロングヘアーの女性が席についていた。 ショートカットの子は、恥ずかしがっているのか戸惑っているのか、今ひとつ判断のつかない表情で貞俊の顔を見ていたし、ロングヘアーの女性のほうは割と人懐っこい顔をしつつ、まれに貞俊を観察でもするかのような視線を投げてきていた。 「あれ、薫さんと楓ちゃんは?」 知佳が言うのを受けて、愛が答える。 「あ、そろそろ帰ってくるんじゃないかな?」 すると、 「ただいま」 まるで愛が言い終わるのを見計らったかのように、玄関から声が聞こえてくる。そしてさっきと同じように、知佳が廊下へと出て行った。 「薫さん、楓ちゃん。おかえりー」 「ただいま、知佳ちゃん」 「ご飯出来てるから、着替えてきちゃってね」 「うん、ありがとう」 そうした会話が終わり、二人分の足音がだんだん小さくなったところで、今度はリビングの入り口から別の声が聞こえてきた。 「おーい知佳、飯まだー」 「知佳、今日のメニューは何だい?」 その声のしたほうに顔を向ける。すると、そこには知佳や目の前に座っている少女よりさらに背の低い、恐らく外国人と思われる銀髪の女の子の姿が認められた。 そして、その子から更に目線を移動させてみると、 (っ!) ぎりぎりのところで声や表情に出さずにすんだが、目の前の光景に少し動揺を禁じ得なかった。視線の先に立っているのは眼鏡をかけた女性だったのだが、下着の上にシャツを羽織っただけというあられもない姿をしていたのである。 さすがにこれはまずいと、さりげなく視線をそらす貞俊だった。 「……あんた、誰?」 眼鏡の女性が、貞俊に声をかける。 「今度、管理人代理として来た塚原貞俊といいます」 「あー、耕介の代打の管理人? 聞いてるよ。206の仁村姉っす。よろしくー」 「よろしくお願いします」 この人が真雪さんかと思いつつ、妹の知佳に比べてあまりに雰囲気の違う姿にいささか戸惑いを感じる。だが、当の真雪は貞俊の挨拶を聞いていないのか聞き流したのか、気にも留めないように席に座り、胸ポケットから取り出した煙草をくわえて火をつけた。 「あの、そちらは?」 貞俊はあらためて、今度は銀髪の少女へと視線を移す。すると愛が口を開いた。 「あ、この子は私の……」 「204のリスティ槙原、ここのオーナーの娘だよ」 愛の言葉をさえぎるように、少女が言う。淡々とした口調であるが、少なくとも貞俊は嘘や冗談を言っているような印象を受けなかった。 (では、この子は愛さんの養女ということか) 意外な事実に少し驚いて、無言で愛とリスティの顔を交互に見てしまう。だが、仮にも養女にしたということは、そこに至るまでに何かしらの経緯や事情が存在していると考えてしかるべきである。そして、そのことについて今の時点で聞くのは失礼だし、無意味だろう。 「よろしく」 「ああ、よろしく」 そう挨拶こそ交わしたものの、リスティも貞俊にはさほど関心はないようで、そのまま黙って席へと座ってしまった。 (……どうしたものかな) そろそろ、貞俊も居心地の悪さを感じずにはいられない状況になりつつあった。 微妙に場の雰囲気がよろしくない方向へと向かい始めたように思われた頃、知佳が貞俊に声をかけた。 「あ、サラダ出すのを忘れちゃった。塚原さん、手伝ってもらえます?」 「はい」 答えて、席を立ってキッチンへと入る。知佳が冷蔵庫からサラダのボールを出すのを見て、貞俊はそれを取り分ける皿を用意しておいた。そして、それも一通り終わって二人が再び席に着いた瞬間だった。 「すみません、遅くなりました」 扉が開くと、長めの髪をポニーテールに纏めた女の子と、彼女に割と似た顔と雰囲気を持つ、もみ上げだけ長く伸ばしたショートカットの子が入ってきた。 「あ、薫さん、楓ちゃん」 愛が二人に声をかける。 「こちら、耕介さんの代わりに来てくれた塚原さん」 「よろしく」 そう貞俊が挨拶すると、二人はそろって「よろしくお願いします」とだけ言って頭を下げ、席に着いた。 だがこのとき、一瞬だけ彼女らと目が合った貞俊は、この日で一番の驚きを感じていた。 (何だ、これは?) 言うまでもなく、貞俊は香港警防隊の一員でもある。それだけに、敵味方を問わず修羅場を潜ってきたと思われる人間の鋭い視線や、身に纏う厳しい雰囲気というものには、それなりに慣れているつもりでいた。 だが、今の二人の女の子の視線、特にポニーテールの子から少しばかり、貞俊はそうした人たちと同じような印象を受けたのである。職場ならいざ知らず、ここはただの女子寮ではないか。 (それに) 少し、黙って観察してみる。すると視線や雰囲気もさることながら、彼女たちの動作には常人のような、いわゆる無駄というか隙というか、そのあたりがほとんど抜け落ちているように見受けられたのだ。 (この二人、ひょっとしたら相当な剣術使い? いや、まさかな……) ひどく気にはなったが、これもまた現状では詮索できるようなことでもなかった。 食事が終わり、簡単にした相手もいるにせよ、改めて互いに自己紹介をしなおすことになった。ところが、美緒だけは食事を終えると、貞俊に厳しい視線を向けながらリビングから出て行ってしまった。 「ごめんなさい、後で私からよく話しておきますから」 「いえ、あまり気にしないでください」 気にしている様子の愛を、貞俊はそうなだめた。無論、どうしたものかと彼自身思っていたのだが、今の段階ではどうしようもないのである。 そして、一人ずつ改めて寮生たちの自己紹介を受けた。 貞俊はこのとき、専ら寮生たちの名前と立場を覚えること。そして彼女たちの言葉の端々から、自分に対してどのような感情を抱いているかを推測することに終始した。それは恐らく、今後管理人の仕事をする時に非常に重要なこととなるはずだった。 一通り寮生たちの自己紹介が終わると、今度は貞俊の自己紹介となった。 まず、三年前までは海軍の主計少尉だったが、とある事情でこれを辞して調理師免許を取ったこと。そして、今回ここに来たのは昔から世話になっている啓吾と神奈に頼まれたからと告げる。 それから、耕介とは学生時代からの付き合いがあること。また、愛とは自分の父が彼女の後見人のような役割を担っていたことから面識があり、幼少の頃はこのさざなみ寮にも何度か顔を見せたことがあることを説明した。 (別に、これでどうなるということはないだろうな) このあたりのことは、既に事前に愛から説明があったはずだからそれも当然である。実際、彼の話を聞いて表情を変えたりするものは誰もなかった。 結局、芳しいとはいえない状況のまま、この日の夕食は散会する。そして、貞俊は食器の片づけを終えるや否や、すぐに自室へと足を向けた。 (情けない、と言われればそれまでだけどな……) さすがに、あれだけピリピリした雰囲気の中に居続けるのは耐え難いことなのである。しかし、これから先このような状況にならないと果たして言えるのだろうか。見通しは限りなく暗いように思えた。 「塚原さん」 部屋に入ろうとするところを、不意に後ろから呼び止められた。振り返ってみると、そこにはポニーテールの少女、神咲薫が立っていた。 「あ、神咲さん。何でしょう?」 「一つ、老婆心からご忠告申し上げたいのですが」 「……はい」 答えつつ、思わず身を固くしてしまう。薫の声は凛としていたが、それ以上に、自分へと向けられている彼女の目が恐ろしいほど真剣であることを見て取ったのだ。 (どうしたんだ、いったい?) 女子寮というこの場所で、こんな厳しい視線を向けられるなど全く想像していなかった。それだけに貞俊は戸惑っていたし、また驚いてもいた。 「どうか邪な感情でここの住人に接すること、ありませんように」 「……」 「愛さんや神奈さん、そして……」 薫の表情が、更に真剣さを増した。 「耕介さんの信頼を裏切るようなこと、どうかされませんよう。お願い致します」 軽く頭を下げて、そう締めくくるのだった。 (……そうか) 言われて、少し考えてみて貞俊はようやく気づいた。 (なるほど、女性ばかりの場所に男が居るわけだから、まず第一にそういう心配をされるのは当然のことだろうな) それに気づかなかったのは、貞俊が薫の言う『邪な感情』というものを、少なくとも意識していなかったことが原因だった。だが自分がどう考えていたにせよ、寮生たちの心情に対する配慮を欠いていたのは間違いない。留意すべきことを見落としていたのは、確かに彼の落ち度だったろう。 何より今の自分がそう思うだけに、この忠告には素直に感謝すべきであった。 「はい」 姿勢を正してから、貞俊は薫に対して一礼を返した。 「よくわかりました。十分、心しておきます」 「……」 「ご忠告、感謝します。ありがとうございました」 その答えを聞いた薫は、僅かに意外そうな表情を見せる。だが、すぐにそれを消して再度一礼した。 「お疲れ様でした、おやすみなさい」 「おやすみなさい」 挨拶を交わして、それぞれ部屋へと戻る二人であった。 「ふう」 自室のベッドに横になり、貞俊はようやく一息つくことが出来た。あまりの緊張に、悲しいかな軽い目まいすら覚えたくらいである。 だが、今日だけを乗り切ればよいという訳ではない。今後、貞俊はここの管理人として耕介が帰ってくるまで、寮生たちの生活を守らねばならないのだ。 しかも、彼女たちの多くは必ずしも好意的とはいえない。その信頼を得られない限り、今後の生活はそれこそ針の筵だろう。 いや、そればかりか寮生たちの不信が募れば、ここから追い出されることも考えられる事態だった。そして万が一にもそうなってしまったら、貞俊は幾人かの友人の信頼を致命的なまでに裏切ることになる。 (これから、正直どうなるか見当もつかない。だけど、今の自分はやることをやるしかないというのも、間違いのないことだ) それは、とりあえず判りきっていることであった。 (何だか疲れた。時間は早いが、もう寝よう) 明日からの仕事に不安と緊張を感じつつ、床につく貞俊だった。 「楓、楓ー」 「美緒ちゃん、どないした? こんな夜遅うに」 ここはさざなみ寮の102号室。薫の従姉妹にあたる、神咲楓の部屋であった。 「楓、どー思う? あいつのこと」 「あいつって?」 「だあーっ、耕介の代わりに来たあいつ!」 なぜ、そんな分かりきったことを説明しなければならないのかと、美緒の口調は苛立ちを隠さなかった。 「あんな奴、あたしは絶対管理人だなんて認めないのだ。楓はどう思ってるのだ?」 「どうって……うちはうちで、間違いがないように努めるだけやし」 あまり深く考えていなかったのか、楓はそう答える。だがこの返答は美緒にとって、歯痒いというか日和見のように聞こえた。 「ふんだ、いーもん」 「美緒ちゃん?」 「あいつなんか、ぜったい、ぜーったいあたしが追い出してやるのだ!」 ▼next ▲prev |