|
Chapter 3 (作:春日野 馨) ▼next ▲prev *第九七管理外世界 地球 海鳴市 桜台公園〜翠屋 私は桜台公園の近くのお花屋さんの前で降ろしてもらった。 お花屋さんでお花を買って公園に入る。晩秋というか初冬の今だから公園の中は人の数も少ない。 案内板を確認してあの場所へ向かう。海鳴の街を一望できる公園中央近くの広場。 忘れもしない。ここはリィンフォース・アインスが天に旅立った場所。 今日はあの日のように雪は降ってはいないけれど…… 広場の片隅にお花を供え、中央に向かって瞑目し手を合わせる。 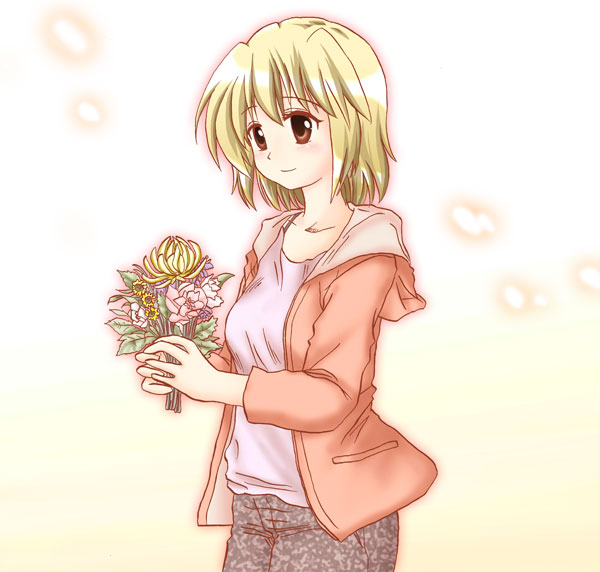 「アインス、こんにちは。シャマルです。随分ご無沙汰しちゃってごめんなさい。はやてちゃんと私たちにツヴァイ、なのはちゃんやフェイトちゃんもみんな元気です。いろいろあったけれどみんなこうやって無事でいられるのはきっとあなたのおかげ。あなたがくれたはやてちゃんとの限りある時間を私たちは大切にしています。そうそう、この前、ヴィータちゃんがこんなことを云っていたんですよ。『あたしらはアインスに永遠の転生をしなくても済むようにしてもらって、はやてとの限りある時間をもっと大事に思うようになったんだ。この気持ちはアインスからの贈り物だって思う』って。私も……シグナムもザフィーラも……みんなそう思っています。だから、これからもずっとはやてちゃんと私たちを見守っていてくださいね。いつの日か、またみんなで一緒に話せるようになる日まで……ありがとう」 私たち守護騎士・ヴォルケンリッターは、『夜天の魔導書』、別名を『闇の書』と呼ばれていたロストロギアの一部だった。 『夜天の魔導書』は古代ベルカ時代の書物型魔法記録装置で、始めは白紙だけれど全ての頁が埋まるとその管制人格が主との融合騎となり起動するというもの。そして私たちはその主や魔導書本体を護る守護騎士として働くプログラムだった。 過去、どの主も『自らの願いを叶える』という『夜天の魔導書』の強大な力を欲しがり、私たちに頁の蒐集を命じてきたのだった。そしてその方法たるやリンカーコアを有する生物の抵抗を抑圧し、強制的にリンカーコアを強奪して『夜天の魔導書』に吸収させるという、云わば強盗のようなものだったのだ。 私たちも後で知ったことだけれど、本来の『夜天の魔導書』の存在意義は様々な魔法を記録保存するためのもので、転生機能と自己修復機能、自己保存機能は蒐集した記録が散逸しないように付与されたものだったという。つまり、魔法を財産として半永久的に後世に伝承するという『本来の意味での魔導書』だった。もちろん、蒐集記録された内容を主が運用すれば強大な力を得ることになるのは云うまでもないことなのだけれど。 しかし、長き時間が流れて行く中で何をどう間違ったのか『夜天の魔導書』の根本は歪められてしまい、蒐集した頁の内容を基に『夜天の魔導書』の歪められた管制人格自らが強大な魔力を生み出すようにと改変されてしまっていた。そしていつしか完成した『夜天の魔導書』が主の望みを実現すると云われるようになってしまっていたのだった。更にその主となった人物の殆ど全てが頁の蒐集途中で絶命するか『夜天の魔導書』との融合の際にその最後の頁として取り込まれてしまい融合事故を起こして暴走し必ず絶命するに到っていた。そして主を失った『夜天の魔導書』自体は白紙に戻り新たな主の下に転生し頁の蒐集を再開していた。 つまり、『夜天の魔導書』の本来の役割はいつの間にか消滅し、単なるリンカーコアの無差別蒐集とその主への蒐集の強要がその存在意義となり、最後にはその主をすら取り込み暴走の果てに世界を破壊し主を死に至らしめるだけの存在となっていた。更に主が頁の蒐集を望まない場合には、主のリンカーコアを侵食し死に至らしめその後自らは転生する存在と成り果ててしまっていたのだった。それが故に『闇の書』と呼ばれるようになったのだけれど。 そんな結末を知っていたなら私たちの行動も少しは違っていたのかもしれない。 でも、私たちは管制人格の下位プログラムであって、上位である管制人格の覚醒のために主の命を受け頁を蒐集することしか出来なかった。更に、歪められた『夜天の魔導書』のプログラム群により、私たちの記憶も転生するごとにその一部を残し白紙化されていたのだった。 ある意味ではそれは幸せだったのかもしれない。主の悲劇的結末を知ることがなかったのだから。 しかし、それが私たちが頁の無差別蒐集を行い続けていた理由の一つであるであることは否定のしようがないのも事実であった。 その運命が変わったのは、はやてちゃんが『最後の夜天の主』となった時だった。 はやてちゃんは不思議な主だった。私たちを家族として受け入れ、共に生活し続ける事を望み『夜天の魔導書』の頁の蒐集を禁止した。つまり『夜天の魔導書』の強大な力を自己の物にすることを微塵も欲さなかったのだ。唯一はやてちゃんが願ったのは『夜天の魔導書』と私たちとで家族としての平和な生活を続けることだけだった。今までにこのような主はいなかった。そして、私たちもはやてちゃんとのそんな平穏な生活がいつまでも続くことを望んでいた。 でも、そんなはやてちゃんの願いは無残にも『闇の書』によって壊されてしまった。生まれた直後から傍にあり続けた『闇の書』によりはやてちゃんの身体は侵食の影響を受けていて下半身が麻痺し自らで歩くことが出来なくなっていたのだった。そしてはやてちゃんの九歳の誕生日に覚醒した『闇の書』は、はやてちゃんが頁の蒐集を望まないということが解ると、はやてちゃんのリンカーコアの浸食を公然と開始したのだ。 はやてちゃんの病状が進行していること、下半身の麻痺が徐々に上半身に及びつつあることを海鳴大学病院の石田先生に告げられた私たちははやてちゃんとの誓いを破り、隠密裏に頁の蒐集を開始したのだった。 『闇の書』が完成することがはやてちゃんの病気の回復に繋がると信じて。 しかし、それは私たちの短慮だった。『闇の書』は主喰らいでもあったことを私たちは知らなかったのだった。 完成の直前に『闇の書』の永久封印を意図していた時空管理局の一部により『闇の書』の頁の一部として取り込まれ私たちは消滅した。そして、はやてちゃんもまた、『闇の書』の最終頁として取り込まれ『闇の書』の暴走が始まったのだった。 けれども、なのはちゃんとフェイトちゃんの力、そしてはやてちゃんの想いによって『闇の書』の管制人格は『祝福の風・リィンフォース』という名を与えられ、はやてちゃんが『闇の書』の管理者権限を発動したことでその管制人格と守護騎士プログラムを自己防衛機能と切り離す事に成功し、私たちも復活することが出来た。 もちろん切り離しに成功したと云っても、自己防衛機能はそれだけで暴走を続け次元世界を崩壊させようとしていた。それは地球を含めた第九七管理外世界のみならず、他の世界をも巻き込む可能性のあるものだったのだ。 そんな危機もはやてちゃん、なのはちゃんとフェイトちゃん、クロノ執務官達が中心となり、私たちも幾許か協力することで阻止することが出来た。文字通り奇跡的に。 はやてちゃんも私たちもその時点ではリィンフォースと一緒にこのまま暮らし続けられると思っていた。 でも、リィンフォースには『闇の書』の長年に渡る度重なる改変により『夜天の書』本来の姿が上書きによってすでに破壊され基礎構造までもがすでに原型を取り戻せないこと、そして管制人格と自己修復機能を分離することが出来なくなっていて自らが再度『闇の書』が復活するということを知ってしまっていた。それゆえ、このようなことを繰り返さないためにリィンフォースは自己防衛機能が停止しているうちにはやてちゃんが見ていないところで自らを消去するように望み、それをなのはちゃんとフェイトちゃんに依頼したのだった。 いよいよその時が迫ったとき、桜台公園の広場まで車椅子で駆けつけたはやてちゃんがリィンフォースに消滅を思い直すように説得をしたのだけれど、リィンフォースの意志は固かった。 「主の危険を払い主を護るのが魔導の器の勤め。主はやて、あなたを護るための最善の策を選ばせてください。私はいつもあなたと騎士たちの傍にいます。一つだけ望むならば、願わくば、私の後を継ぐであろう者にも『祝福の風・リィンフォース』の名を与えてやっていただきたい。ずいぶん永い時を生きてきましたが最後の最後で私はあなたに綺麗な心と名前を頂きました。私は笑って行けます。私はもう、世界で一番幸福な魔導書ですから。ありがとう」 リィンフォースはそうはやてちゃんに言い残しこの世から旅立っていった。 はやてちゃんの手に、剣十字の紋章のペンダントと私たち守護騎士を残して。 瞑目した瞼の裏には海鳴に居た頃のはやてちゃんと私たち……そしてそれを優しい眼差しで見守っていたアインスの姿が浮かんでいた。 ……暫しの祈りの後、徐に目を開け深呼吸を一つ。 さて、せっかく海鳴に来たのだし挨拶周りもしないといけない。とはいっても大した数があるわけではないけれど。主だった行く先としては海鳴大学病院の石田先生のところとエイミィさんのところくらいかしら。ただ、さすがに挨拶周りに手ぶらでというわけにも行かないわよね。それに丁度お昼にはいい時間だし。 桜台公園から駅前に出て翠屋さんへ向かう。この時間だとお昼のピークも終わってちょっと落ち着いている頃かな。 定番といえば定番だけれど翠屋さんのスイーツは絶品。お店で食べるケーキも最高だし、テイクアウトのケーキもまた美味しい。流行っているのが良くわかる。はやてちゃんをはじめ私たちも大好き。あの甘いものには縁の無さそうなザフィーラまでもがファンなのだからもはや何も云う必要はないだろうと思う。 まぁ、なのはちゃんの実家だけにご両親に捉まりそうな気がしないでもないけれども、これも挨拶周りの一つだと思えばいいのかしら。 ドアを開けると『からん、からん』というベルの音。 「いらっしゃいませ、シャマル先生、お久しぶりです」 マスターの士郎さんがカウンターで迎えてくれる。 「いらっしゃいませ〜、あ〜シャマル先生、お久しぶりです」 「どうもご無沙汰しています」 ケーキをショーケースに並べていたパティシエの桃子さんも明るい笑顔で迎えてくれ、私はカウンターに席を取ることにする。 「なのはがいつもお世話になってます。こちらへは今日はお仕事ですか」 「こちらこそお世話になってます。今日は私用で来ちゃいました」 「そうですか。シャマル先生は確かホットミルクでしたよね」 「あとはアップルパイですね♪」 「ふふ、ありがとうございます」 士郎さんと桃子さんの息の合った接客。ここに来ると落ち着くのはきっとお二人の人柄のせいなのかしら。 「そういえば、今日はお二人だけなんですね」 「ええ、ちょうどお昼のピークも終わりましたし、バイトの子たちも休憩に入りましたのでちょっと一息なんですよ。もうすぐ美由希が来ますけれど」 笑顔の桃子さん。なのはちゃんの明るさはきっと桃子さん譲りなんだろう。ヴィヴィオもきっと明るくてよい子になるに違いない。でも頑固さも譲り受けちゃうのかな。だとしたらちょっと困っちゃうかも。そんなことをふと思う。 「なのは、ご迷惑をお掛けしてませんか?あの子も妙なところで妙に頑固だから」 桃子さんがそんな話を振る。いけない、顔に出てたかしら? 「いいえ、そんなことありませんよ。ヴィヴィオちゃんも親子揃って元気です」 「それにしてもなのはが母親とはねぇ。孫だなんて私たちも年をとるわけだね、ねぇ、母さん」 「そうねぇ。でもまだまだ老け込む年じゃないですよね、とーさん」 「ええ、お二人ともまだまだお若いですから」 「あら、いやだ、なのはの件がなくてもれっきとしたおじいちゃん、おばあちゃんなんですよ、私たち」 屈託のない明るい笑い。翠屋さんの雰囲気そのもの。 「あ、シャマル先生、いらっしゃいませ。ご無沙汰してます」 「美由希さん、ご無沙汰しています」 「美由希おばちゃんも早くいい人見つけないとね。剣術とは結婚できないんだから」 「うぅっ……突然そういうダメージの大きい話を振らないで欲しい……恭ちゃんが忍さんと一緒になっちゃったのはまだしも、なのはにまで先を越されちゃったと思っているんだから。それに『おばちゃん』ってひどいよ、かーさん」 「あら、そうかしらねぇ?この前なんて雫ちゃんに『みゆきおばちゃん』って呼ばれて喜んでいたくせに。かーさんが美由希くらいの頃にはもうとーさんと一緒になって随分経っていたというのに……なんで美由希はこう不器用なのかしら」 「あはは……お願いだからそういう話はちょっと勘弁して……」 「ふふっ」 苦笑の仕方もなのはちゃんとそっくり。やっぱり姉妹。 「お待たせしました。ホットミルクとアップルパイです」 桃子さんがカップとソーサーにスイーツを並べてくれる。 「ありがとうございます。あ、一つお願いしていいでしょうか?」 「はい、何でしょう?」 「シュークリームとお勧めのケーキをそれぞれ十個、別々に箱詰めして頂けないでしょうか?」 「はい、シュークリームとケーキア・ラ・カルトでそれぞれ十個、別々にですね。美由希、お願いしてもいい?」 「はぁい。それではお帰りのときにお渡しできるようにしておきますね」 美由希ちゃんの元気な声。 『からん、からん』ドアのベルが鳴った。お客さん? 「いらっしゃいませ〜。あ、石田先生」 入ってきたのは石田先生。 「お邪魔します、桃子さん。え?シャマルさん……」 「石田先生……ご無沙汰しています」 席を立って一礼。まさかここで石田先生に出会うことになるとは。予定外といえば予定外。まったくもって世の中は不思議。 石田先生も鳩が豆鉄砲を喰らった様な目をしている。たぶん私もそうなんだろう。何年ぶりだろう。はやてちゃんが車椅子から降りられるようになってからもしばらくは定期検査でお世話になっていたからかれこれ五年弱くらいだろうか。 「はやてちゃんやシグナムさん、ヴィータちゃんはあれからお元気ですか?」 「ええ、みんなこれ以上はないほどに。無駄なほどに元気ですね」 「皆さん、お仕事もお忙しそうですし、無茶だけはしないようにってお伝えくださいね。こちらへはお仕事で?」 「ありがとうございます、確かに承りました。今日はちょっとした私用です」 「お席、どうされます?ご一緒がよろしいですか?」 桃子さんが水を向けてくれる。 「ええ、それでお願いします」 と石田先生。 「じゃあ、シャマル先生の分はお持ちしますね。こちらへどうぞ」 ちょっと奥まった、でも窓際で明るいボックス席に案内してくれる桃子さん。 「ありがとうございます」 そう答えて私は石田先生と同じ席に移動する。 「石田先生、その節は大変にお世話になりました」 「いいえ、こちらこそお世話になりました。わたしもはやてちゃんにはいろいろ教えてもらいましたから」 「実は、今日は先生のところにご挨拶にお伺いしようかと思っていたんです」 「あら、じゃぁここでお会いできてよかったです。実は今日は夜勤明けで、今上がってきたところなんですよ。行き違いになっちゃうところでしたね」 「石田先生、いつものでよろしいですか?」 お冷を運んできてくれた美由希さんがオーダーを尋ねる。 「ええ、それでお願いします」 「はい、ではごゆっくりどうぞ」 さすがは翠屋さん。常連のお客さんのオーダーは阿吽の呼吸で通じるほど。こういうところも翠屋さんの人気がある理由なんだろう。 「はやてちゃんは私にとって初めての長期の患者さんで、今だから云っちゃいますけれど症状がなかなか好転しなくて私もかなり焦っていたところがあったのでずいぶん強引な医者だったんじゃないかなと反省していたんですよ。まぁ、それ以来、余裕を持って患者さんと接するようにしようって心掛けられるようになったんです」 「お待たせしました。石田先生はミルクティとフレンチトーストですね。シャマル先生はホットミルクとアップルパイで」 桃子さんがテーブルにオーダーを並べてくれる。え?これって…… 「……あの、桃子さん……」 「なのはがいつもお世話になっていますから。わたしたちからの気持ちということで」 にっこり笑ってウィンクする桃子さん。こういうところもさすが。私も見習わないといけない。 「ではごゆっくりどうぞ」 「……あの、失礼かもしれませんがさっきの桃子さんの『シャマル先生』って……」 「あ、申し遅れて済みません。実は私も向こうで医師をしてましてなのはちゃんを診させていただいているんです。とはいってもこちらでは診療は出来ないんですけれど」 「そうだったんですか。それは失礼しました」 「いいえ、私も申し上げていませんでしたから。お気になさらないでください」 「ということは、はやてちゃんも、でしょうか?」 「ええ。身内ですけれどはやてちゃんも診ています」 「シャマル先生のような方がかかりつけのドクターならばはやてちゃんも安心ですね」 「だといいんですけれど」 「大丈夫ですよ、きっと。シャマル先生はお優しい方ですし、きっと患者さん思いのいい先生なんでしょうねえ。わたしなんて見習わないといけませんね」 にっこり微笑む石田先生。厳しいけれど患者さん思いでヴィータちゃんが『いい先生だ』と云っていたのがよく解るような笑顔。私にとっては医師としての目標のような人。 「そんなことありませんよ。私のほうこそ石田先生を見習わさせていただかないといけませんから」 そんな会話をしていると、入り口のベルがまた鳴った。 「いらっしゃいませ」 小柄で綺麗なシルバーブロンドのストレートロングヘアをした女性が入ってきた。 「あ、フィリス先生、こっちです」 石田先生が軽く手を上げると、『フィリス先生』と呼ばれたその女性はこちらに歩み寄ってきた。 「石田先生、お話中じゃないんですか?」 「あ、私は大丈夫です。お席、空けましょうか?」 「いいえ、結構ですよ、シャマル先生。フィリス先生はわたしの隣でいいですよね」 「ええ、構いません」 「フィリス先生、いらっしゃいませ。先生はいつものでよろしいですか?」 お冷を持ってきた桃子さんが笑顔でオーダーを取る。 「ええ、お願いします」 「はい、かしこまりました。少々お待ちください」 「紹介しますね。こちら、フィリス矢沢先生。わたしの先輩で今はご実家の矢沢病院の副院長でうちの大学病院の神経内科の非常勤外来担当です。フィリス先生、こちらはシャマル先生。五年ほど前にわたしが担当していた八神はやてちゃんのご親族で、今は向こうではやてちゃんを診てくださっているそうです」 「フィリス矢沢です。はじめまして。よろしくお願いします」 小柄な女性が挨拶をする。お若い感じで可愛らしい。 「シャマル八神です。こちらこそはじめまして。よろしくお願いします」 これが私とフィリス先生の出会いだった。 ▼next ▲prev |