
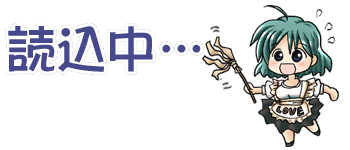
正解
正解
正解
不正解
不正解
不正解

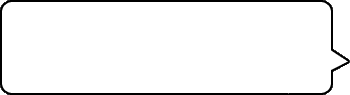
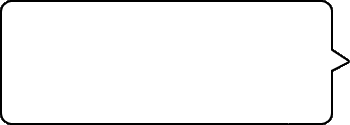

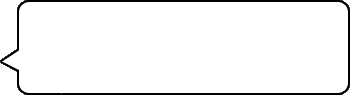
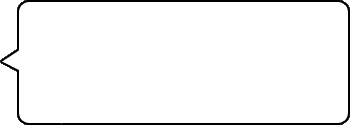

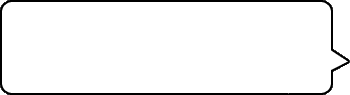
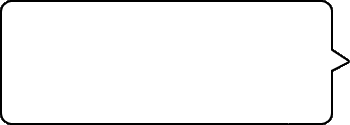


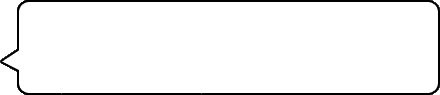


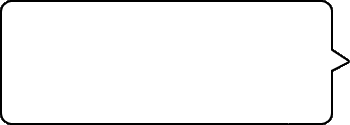
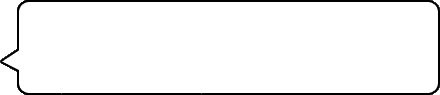








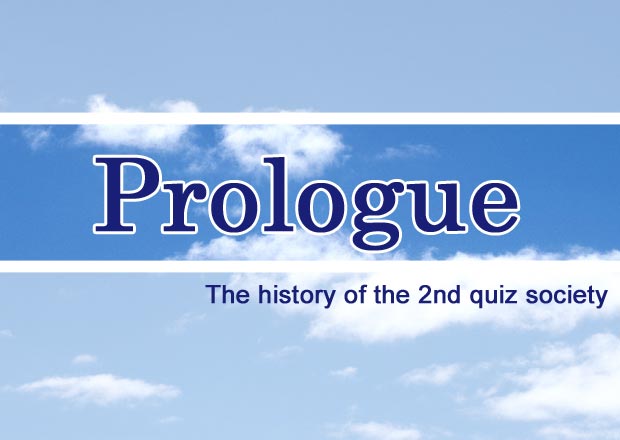




 背景:夜景
背景:夜景

 2025年4月
アメリカ
2025年4月
アメリカ



 背景:学校
背景:学校

 2027年7月
日本
2027年7月
日本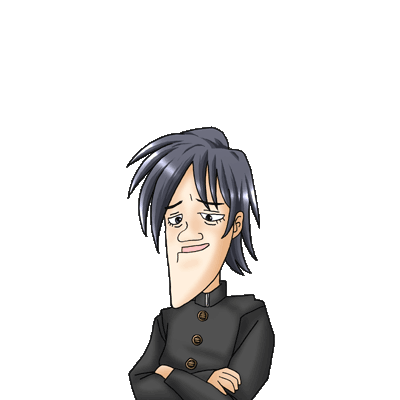

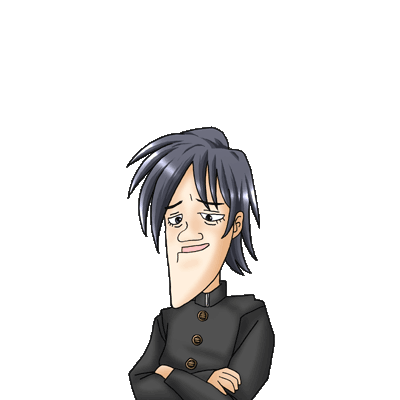


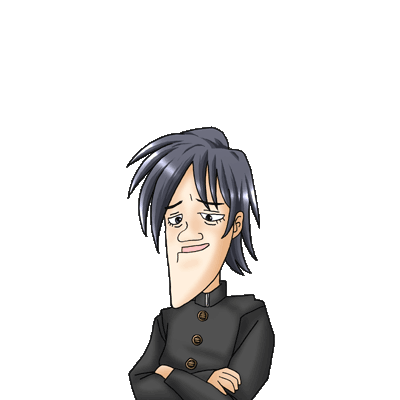
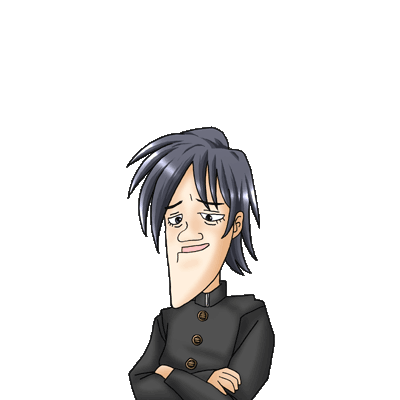

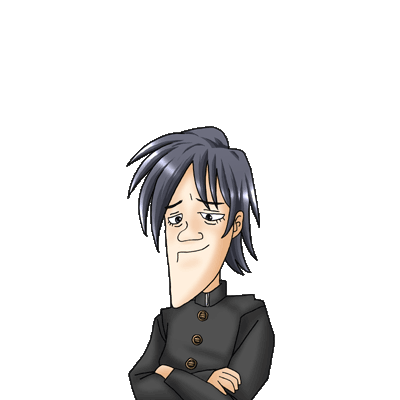

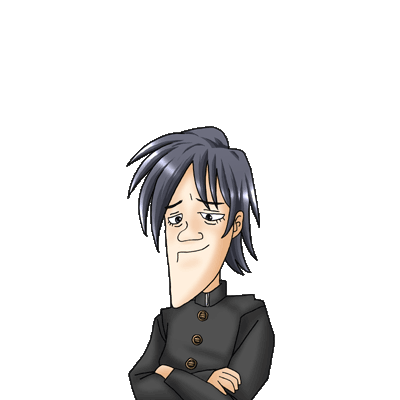



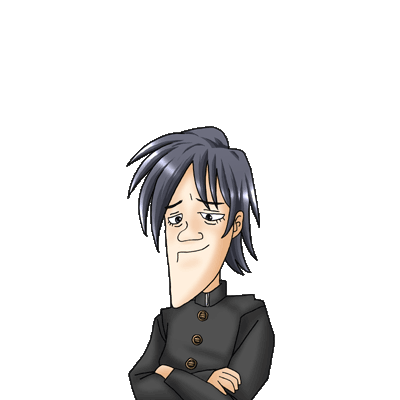

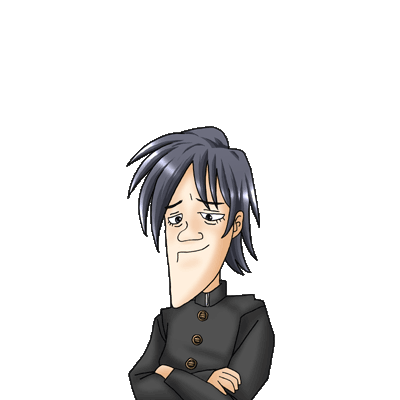
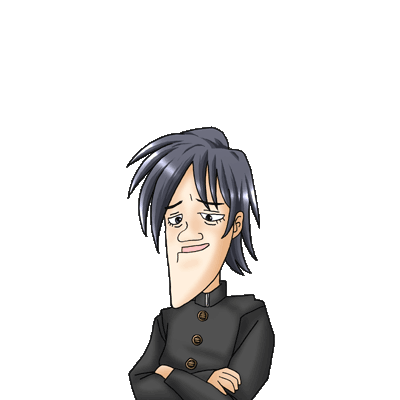









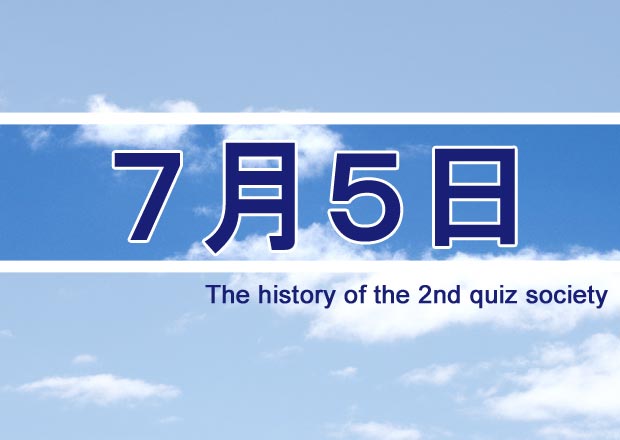
 背景:自室
背景:自室

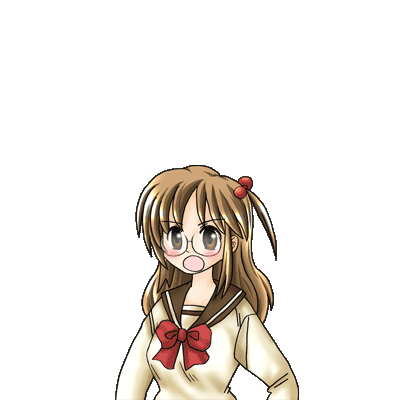


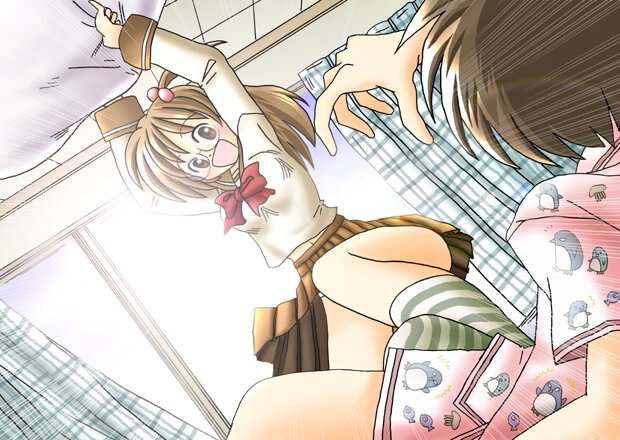

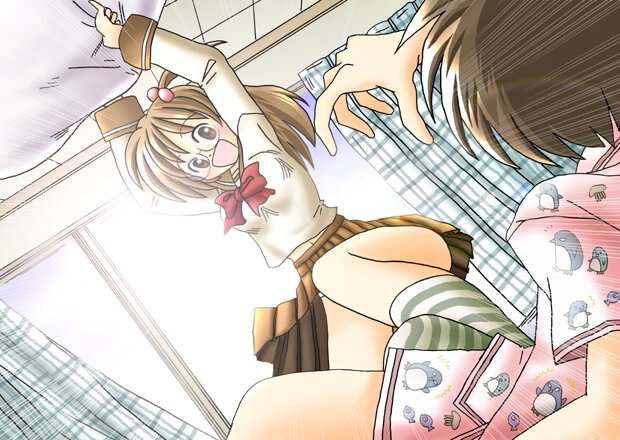

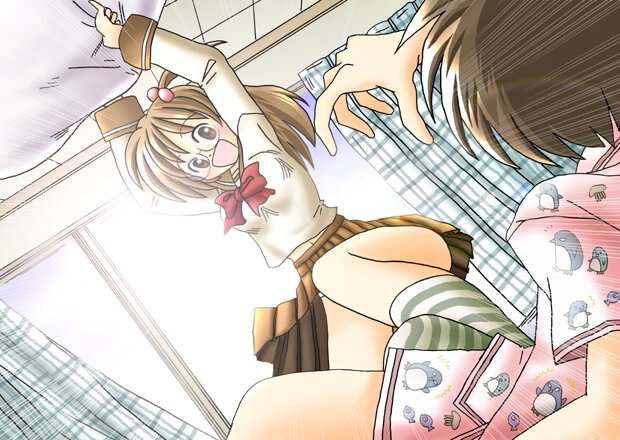




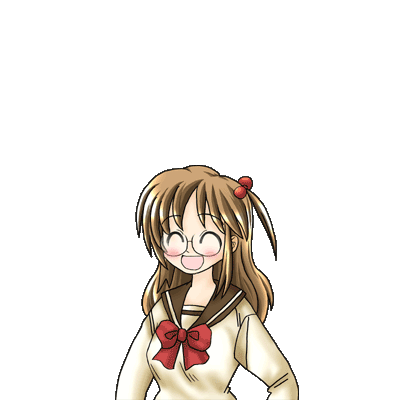



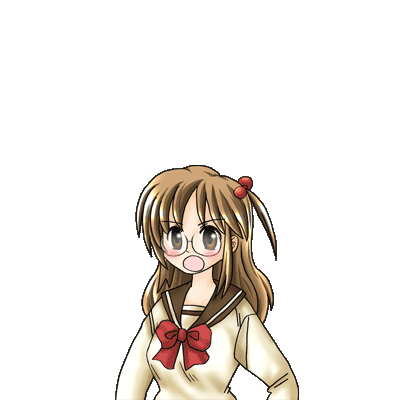
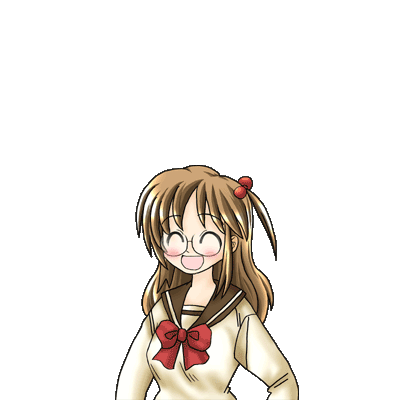





 背景:台所
背景:台所








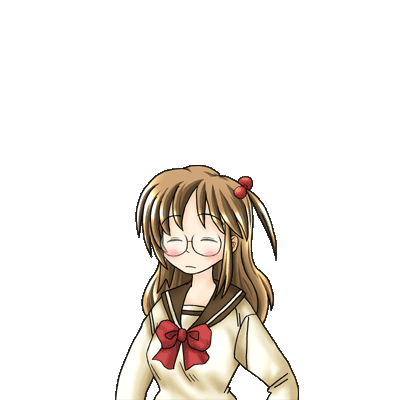




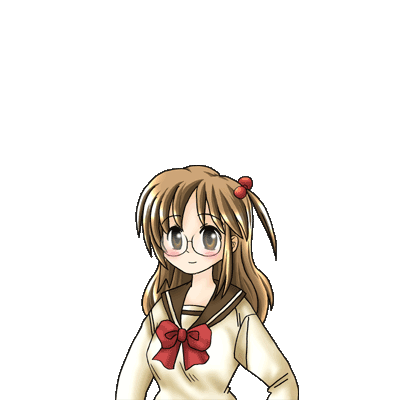
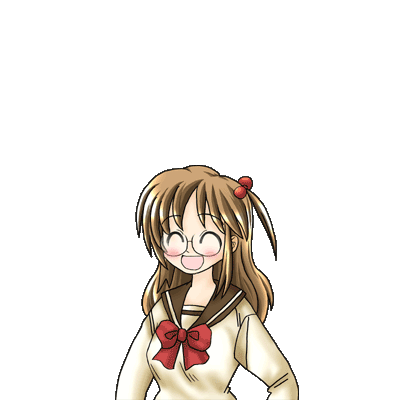
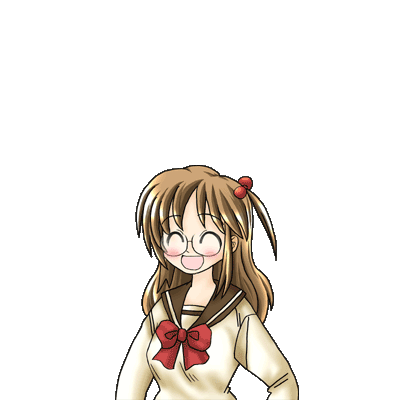





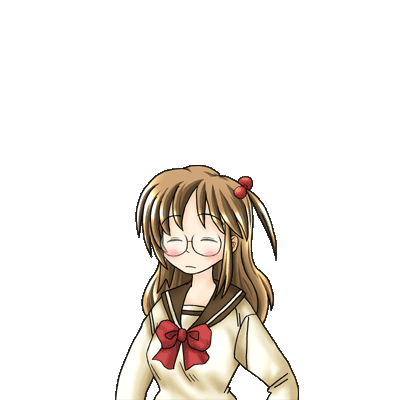



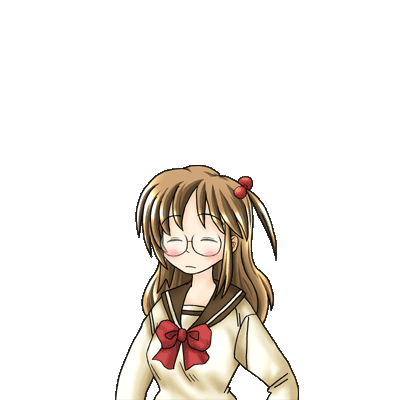



 背景:自宅前
背景:自宅前


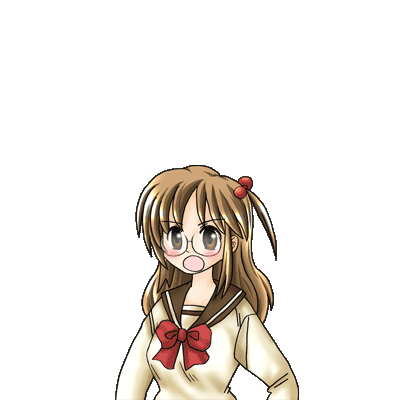


 背景:通学路
背景:通学路

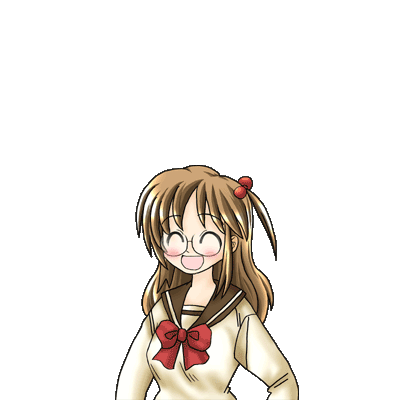



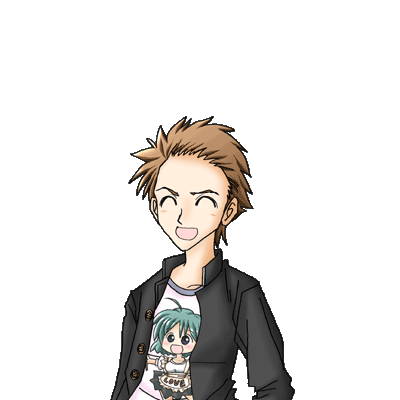
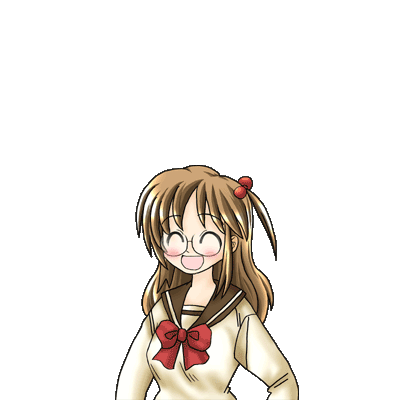










 背景:通学路
背景:通学路
 背景:廊下
背景:廊下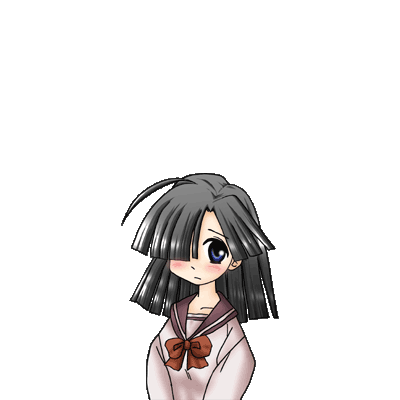

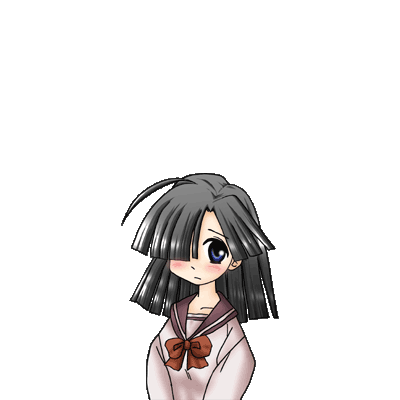
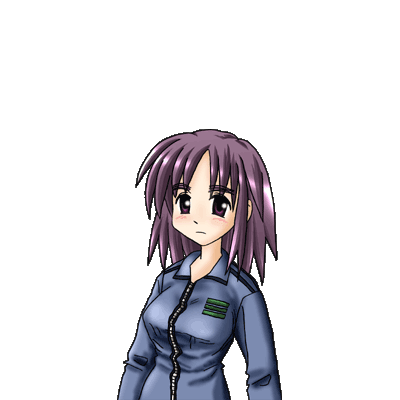
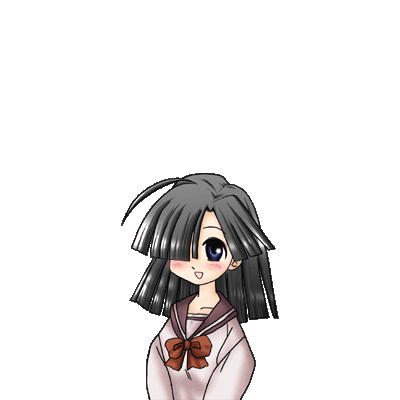
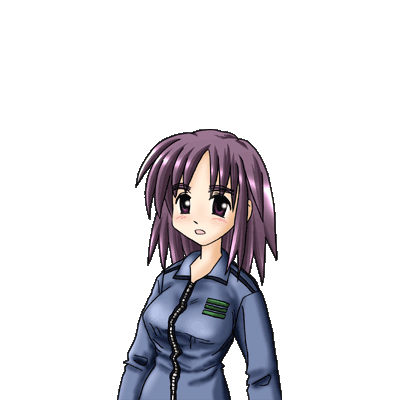
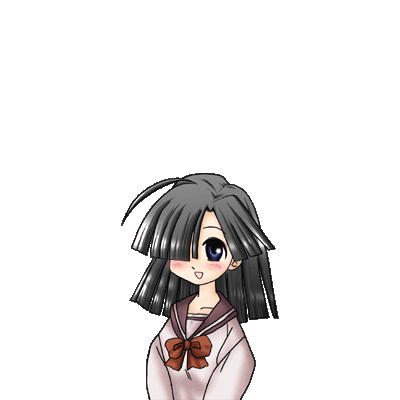
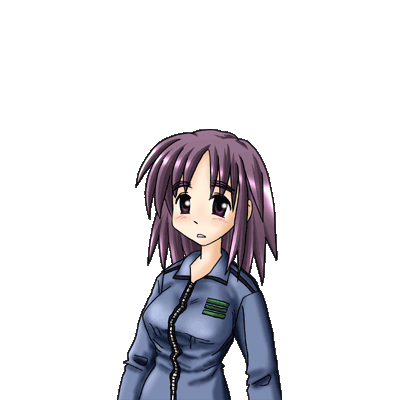
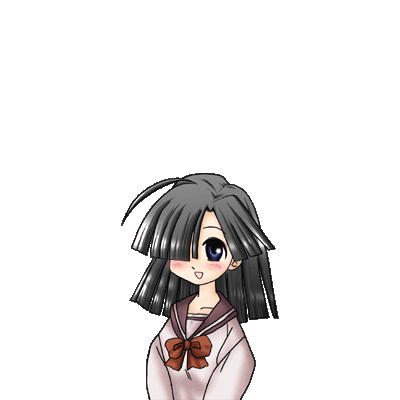

 背景:部室棟
背景:部室棟

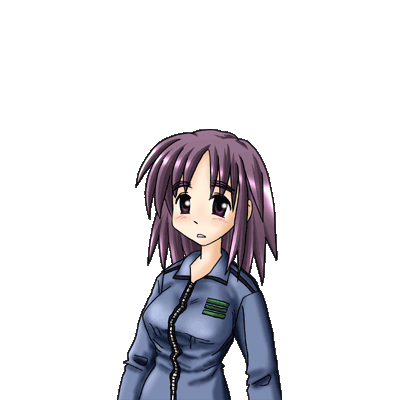


 背景:通学路
背景:通学路 背景:本屋
背景:本屋
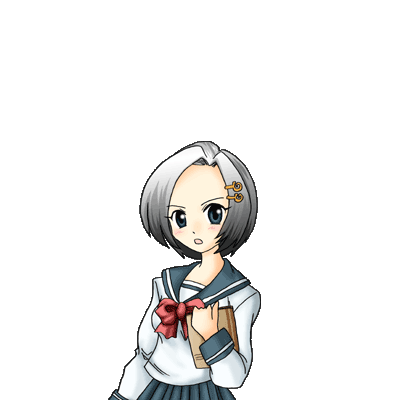

 背景:公園
背景:公園
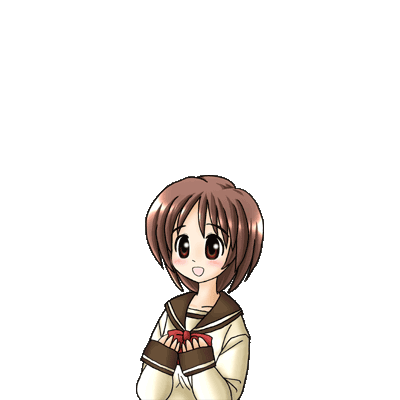

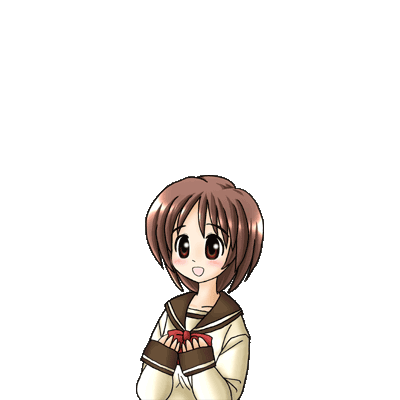
 背景:スーパー
背景:スーパー
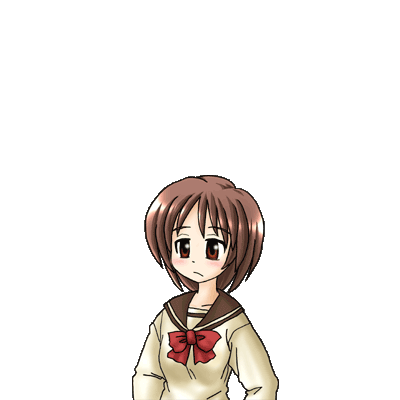

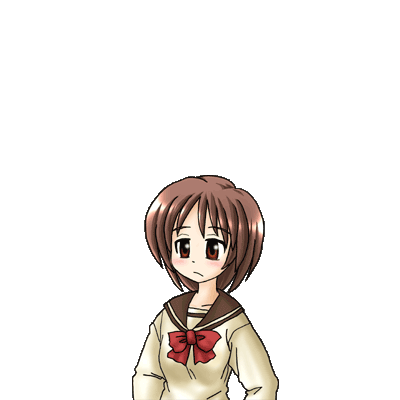
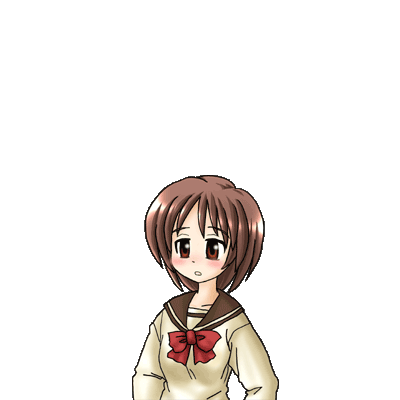





 背景:部室
背景:部室

 第2クイズ研究会。
第2クイズ研究会。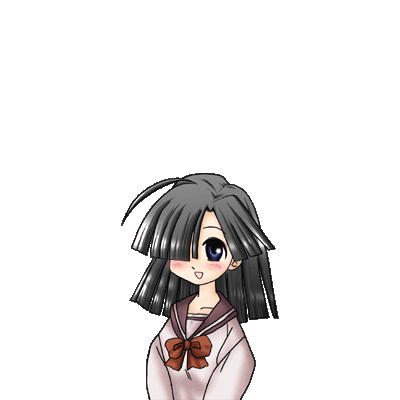
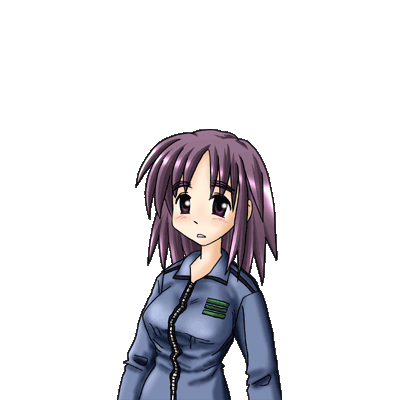
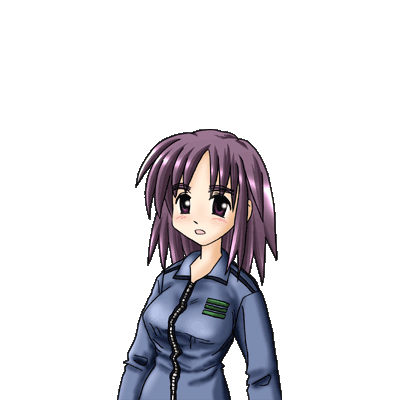
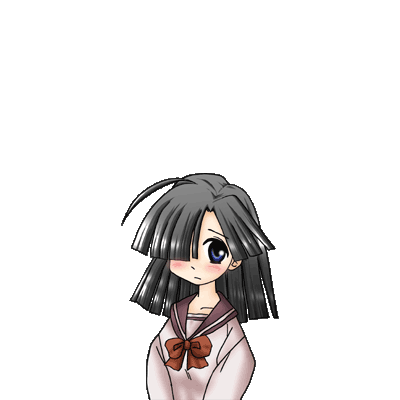



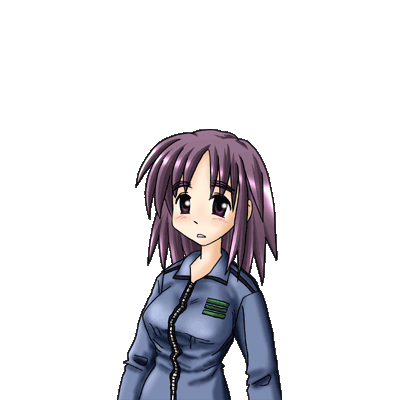



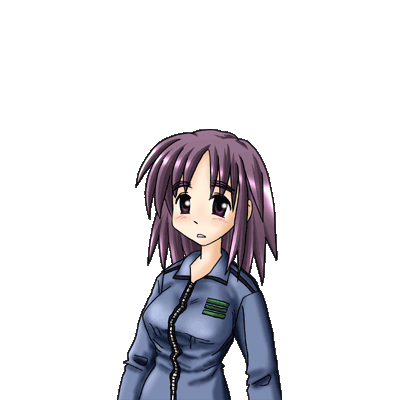

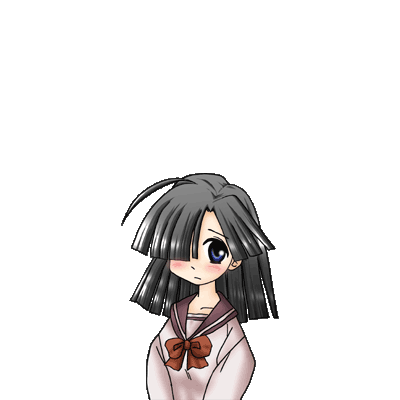

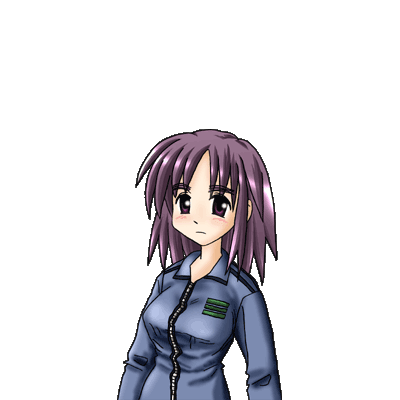

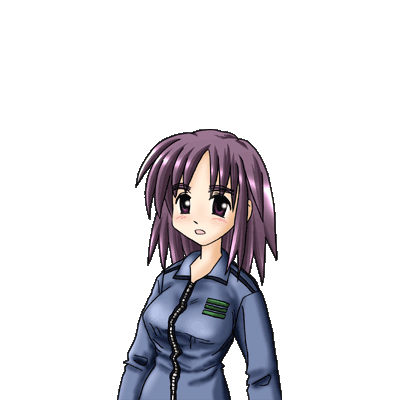

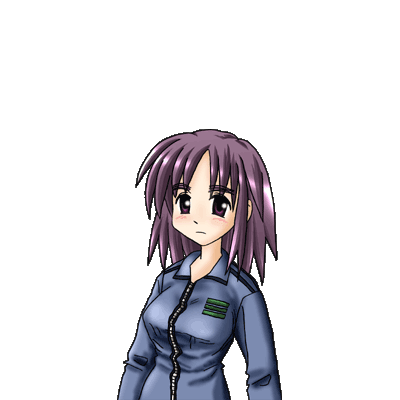
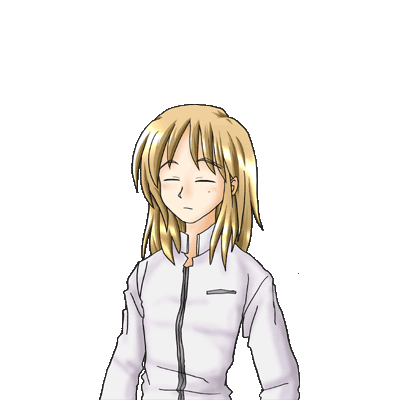
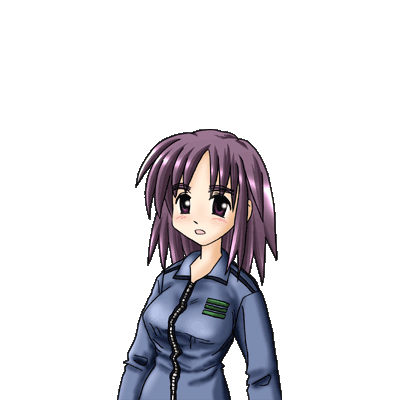






 背景:自宅前
背景:自宅前


 背景:台所
背景:台所








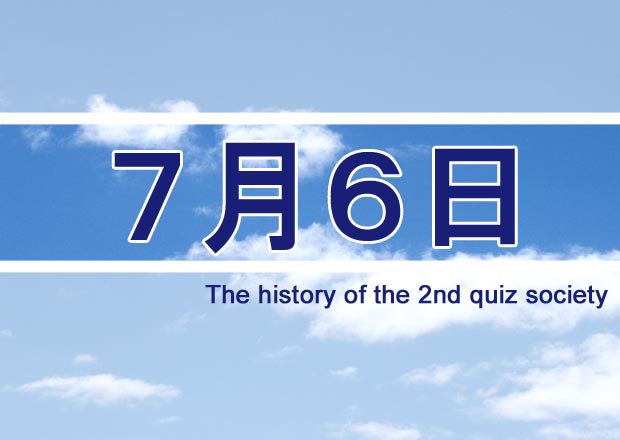
 ノイズ
ノイズ





 ノイズ
ノイズ




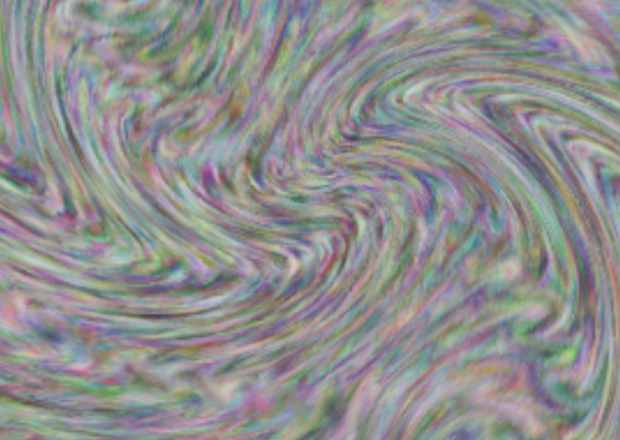 背景:歪んだ空間
背景:歪んだ空間
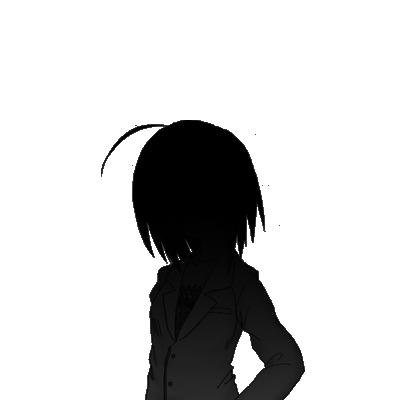

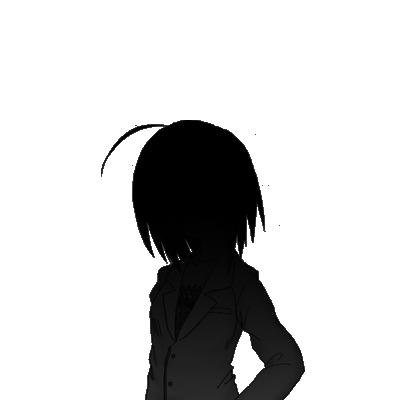

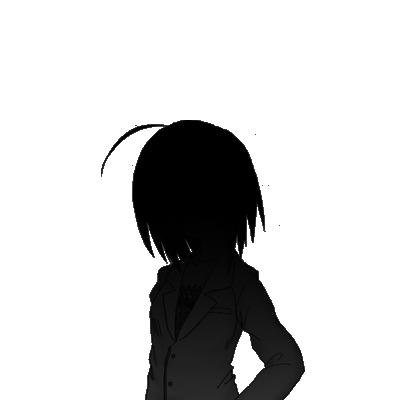

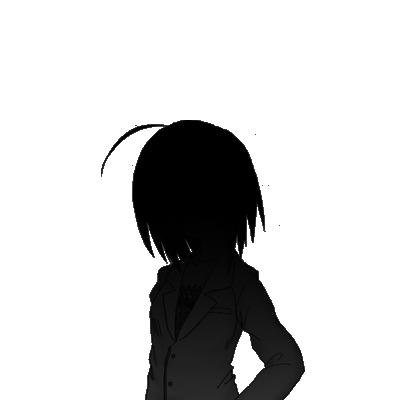
 背景:自室
背景:自室


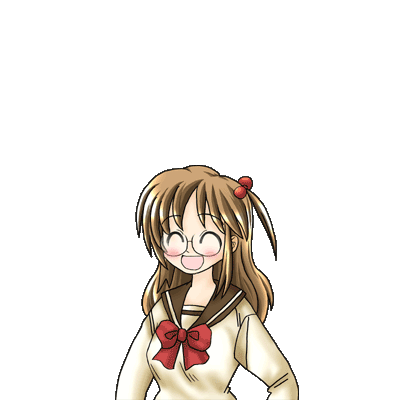

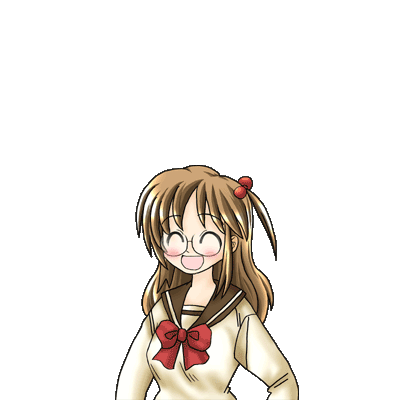





 背景:通学路
背景:通学路















 背景:下駄箱
背景:下駄箱
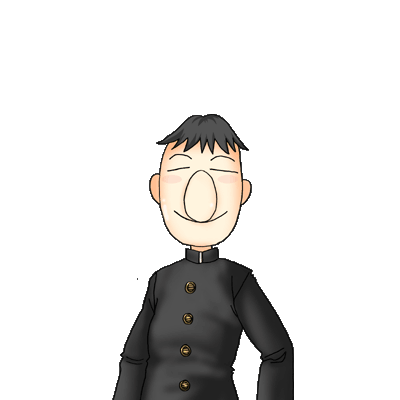

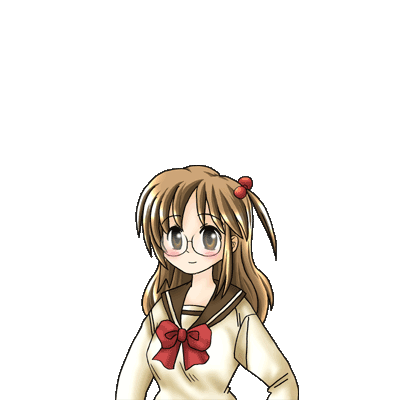






 背景:階段
背景:階段
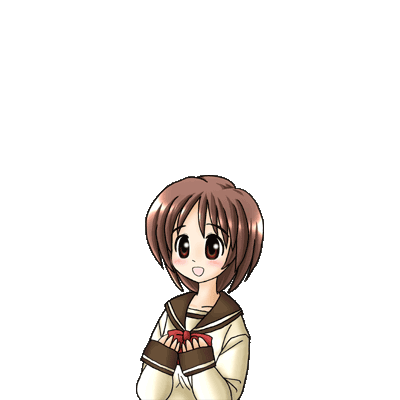





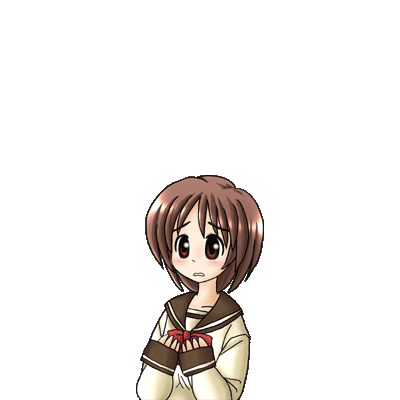

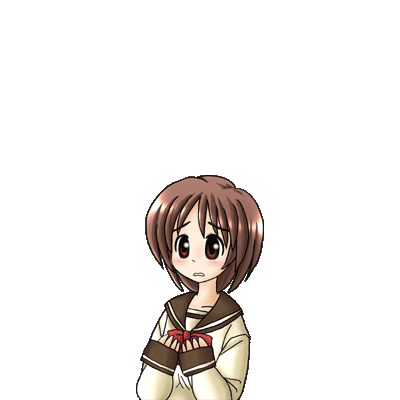

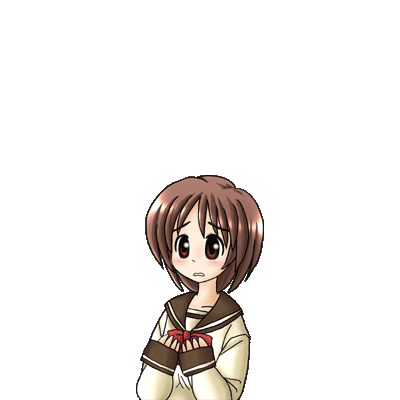

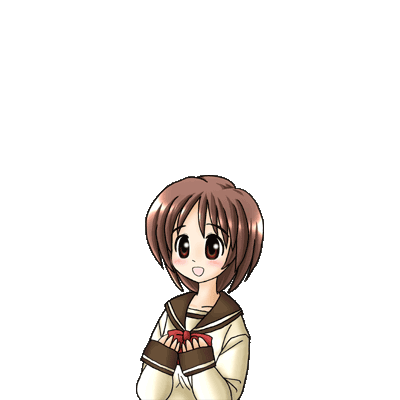

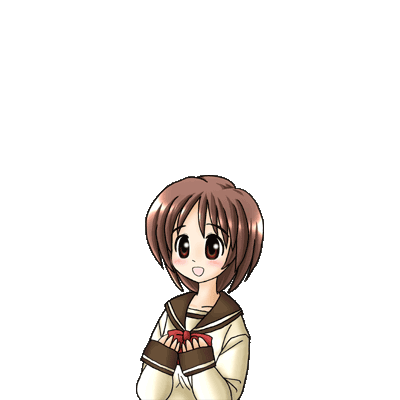

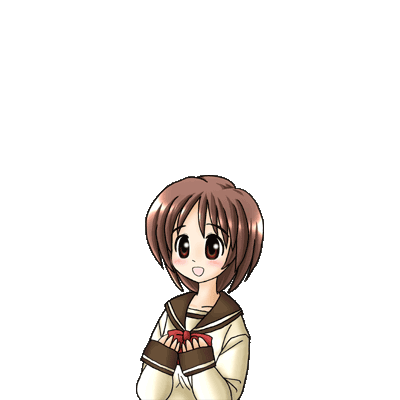
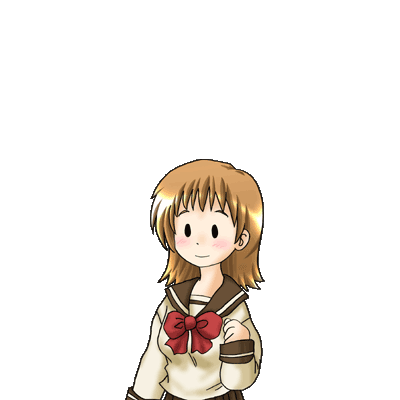
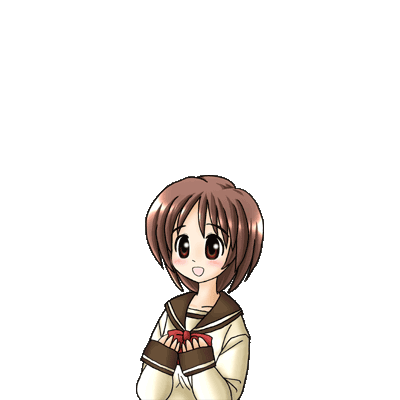
 背景:階段
背景:階段



 背景:教室
背景:教室



 背景:学食
背景:学食 背景:階段
背景:階段 背景:屋上
背景:屋上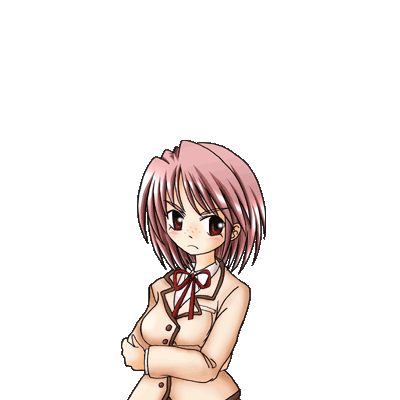




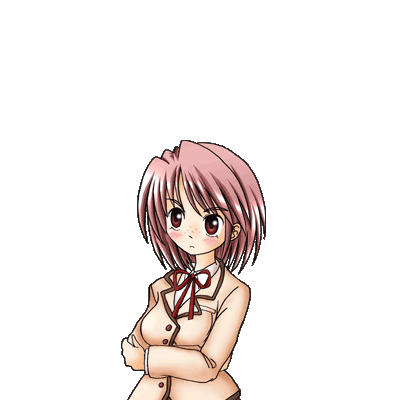


 背景:階段
背景:階段



 背景:教室
背景:教室

 授業が終ると同時に榊が教室に飛び込んできた。
授業が終ると同時に榊が教室に飛び込んできた。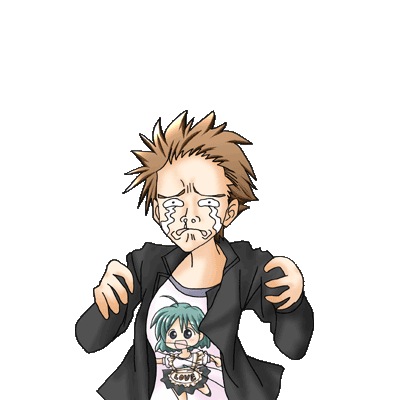

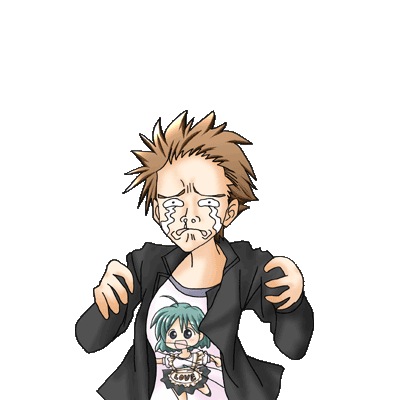
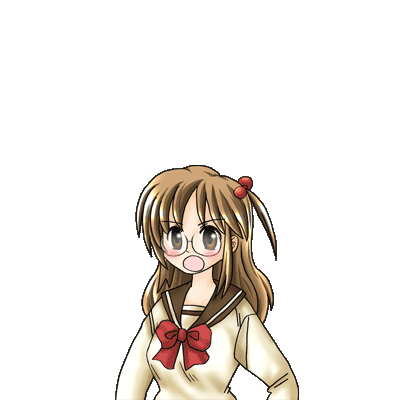
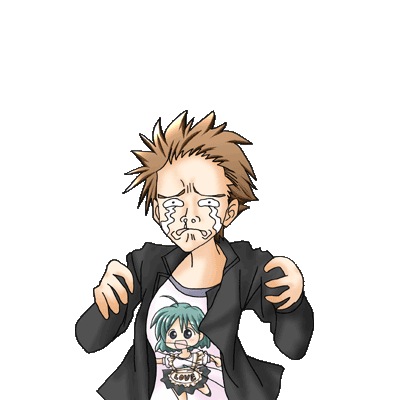
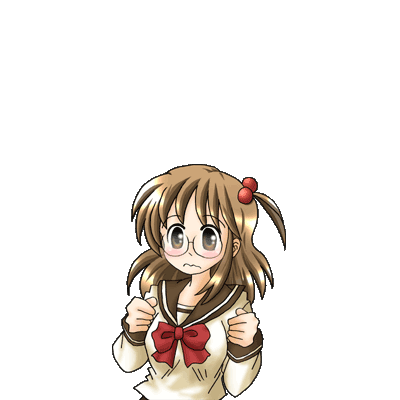
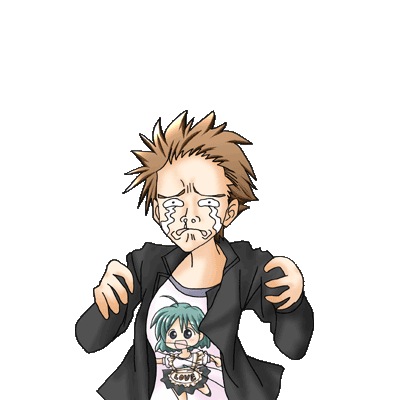
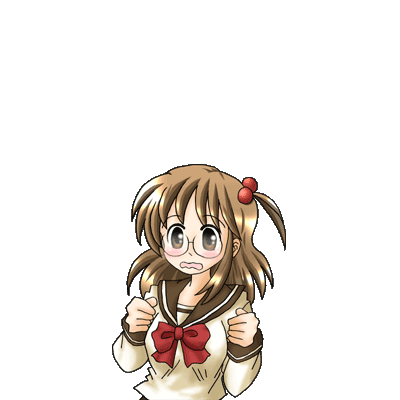

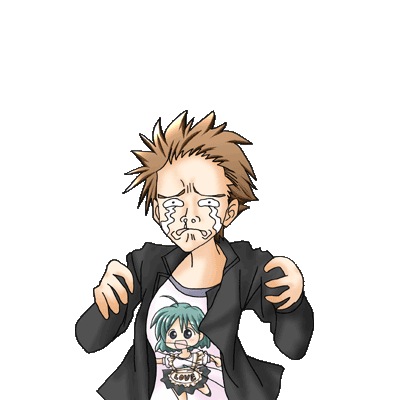
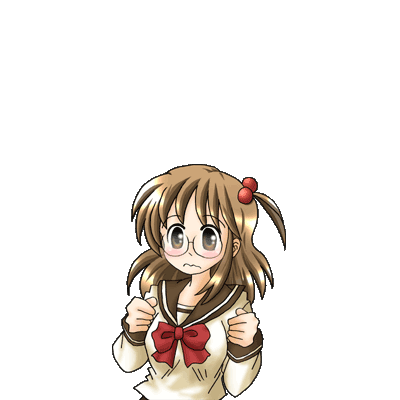
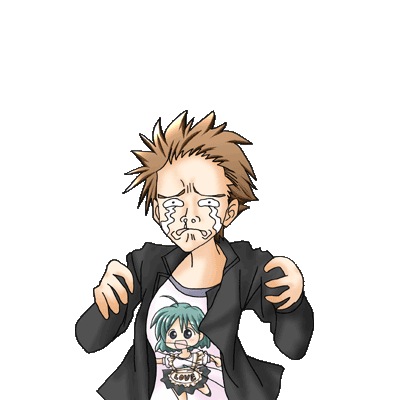

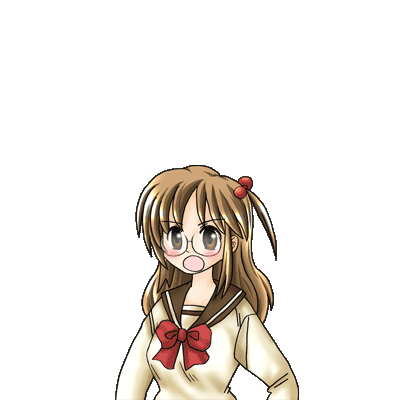




 背景:生徒会室
背景:生徒会室





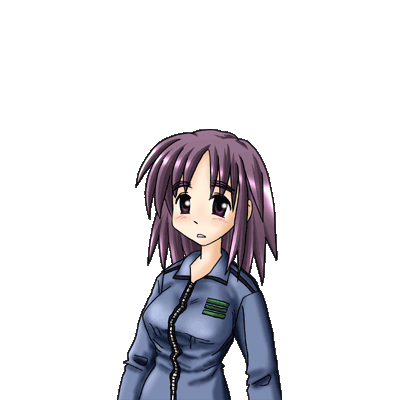







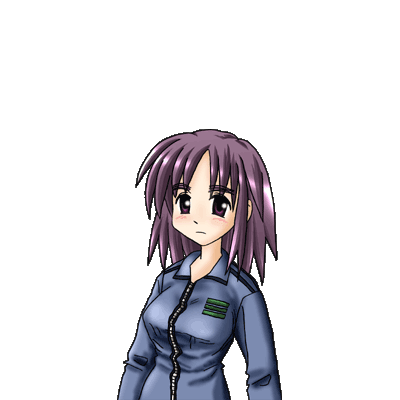

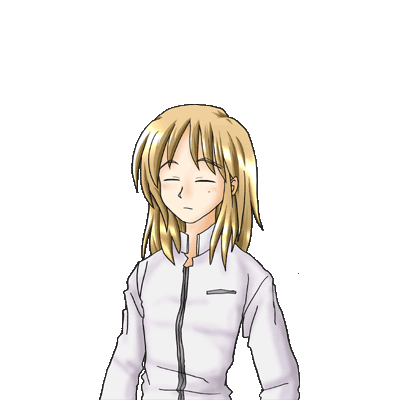

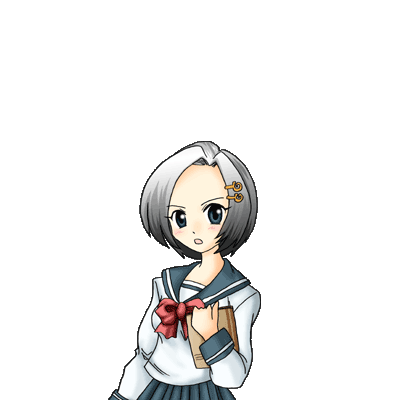

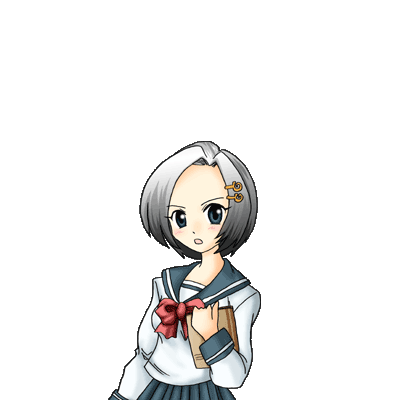

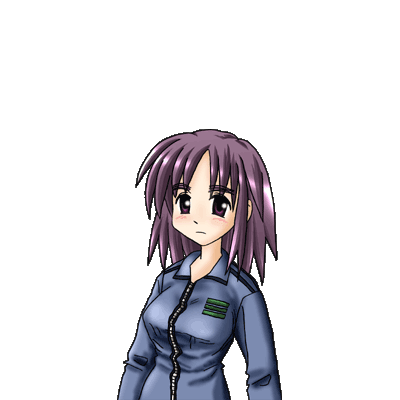

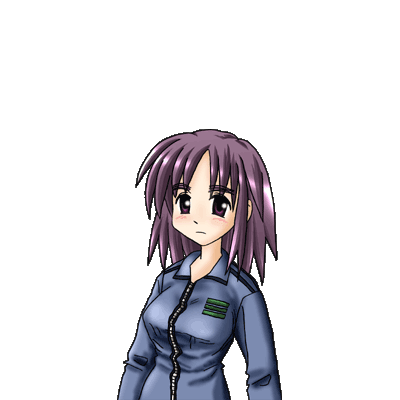

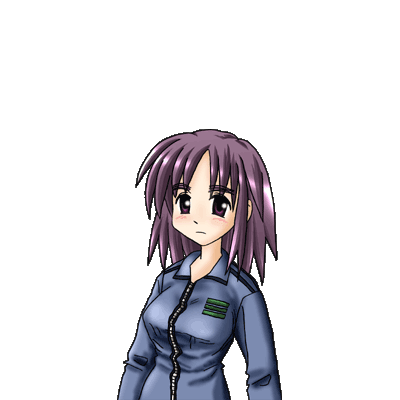

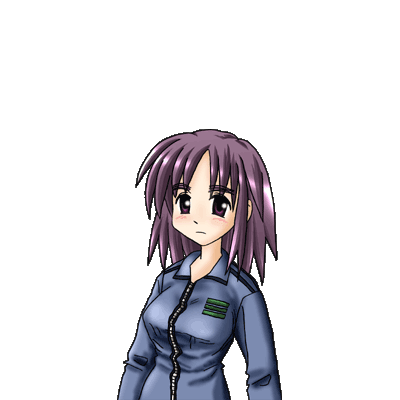

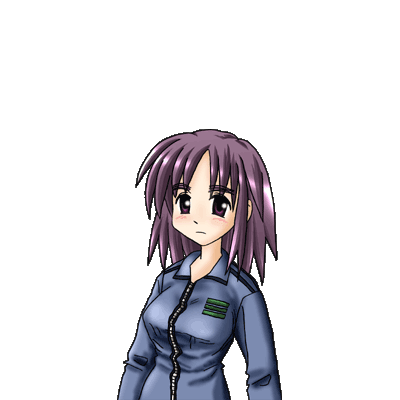

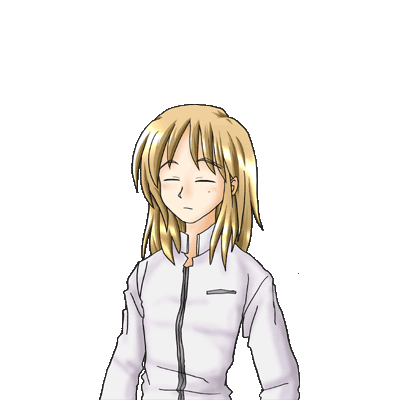

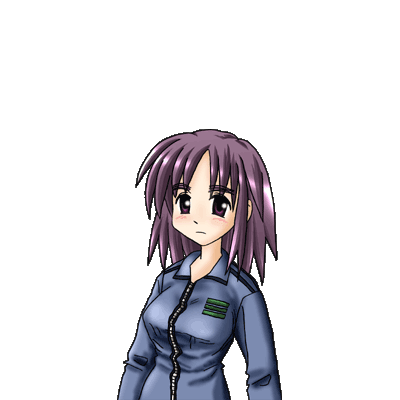

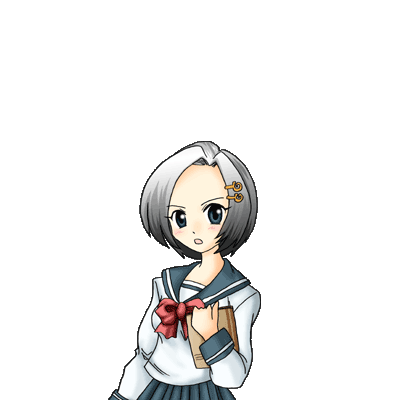



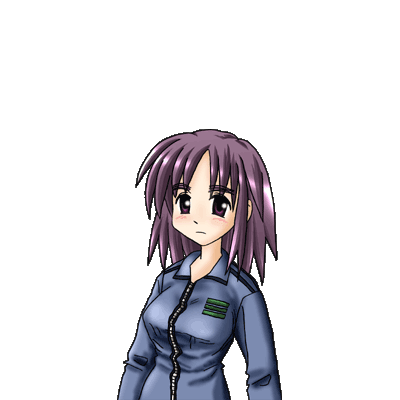





 背景:教室
背景:教室


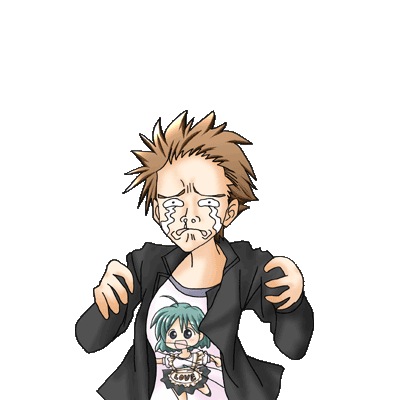
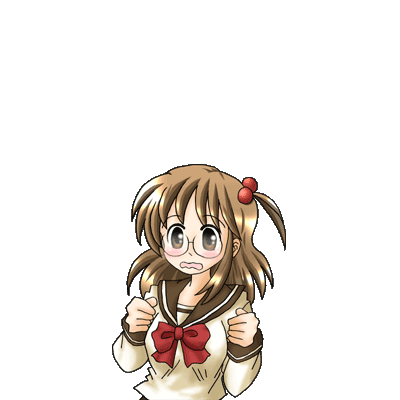
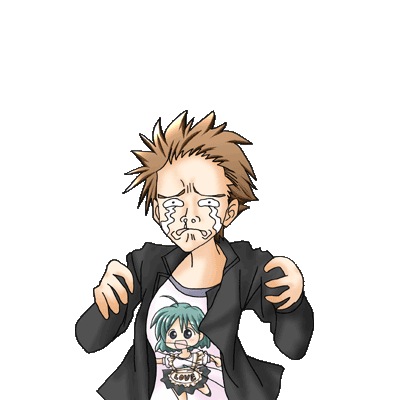

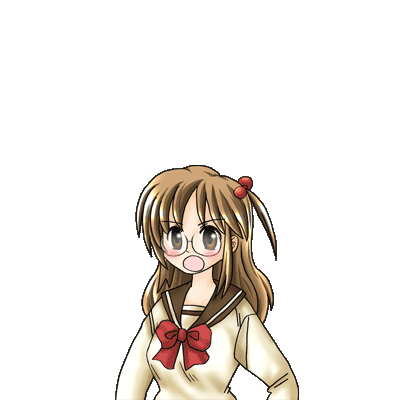
 背景:廊下
背景:廊下




 背景:町
背景:町



 背景:ゲーセン
背景:ゲーセン




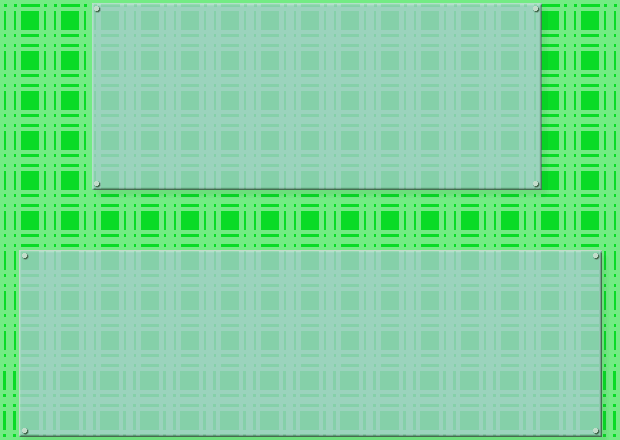







 背景:ゲーセン
背景:ゲーセン

 30分経過。
30分経過。

 背景:スーパー
背景:スーパー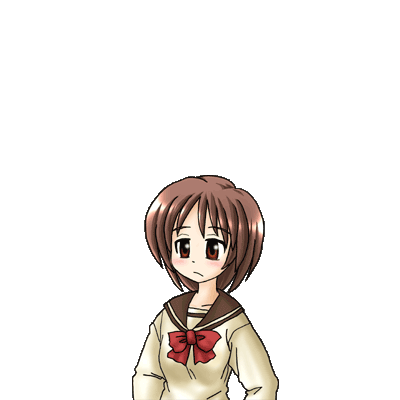
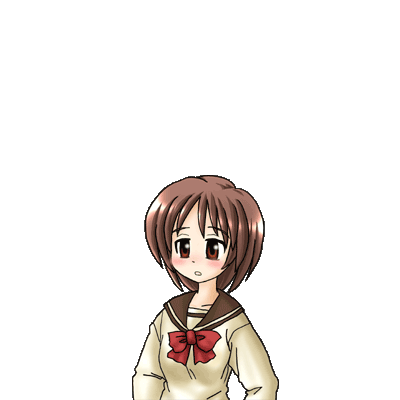

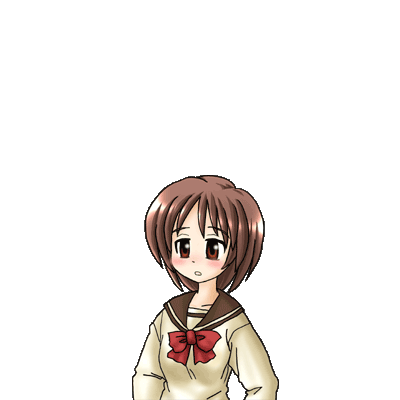

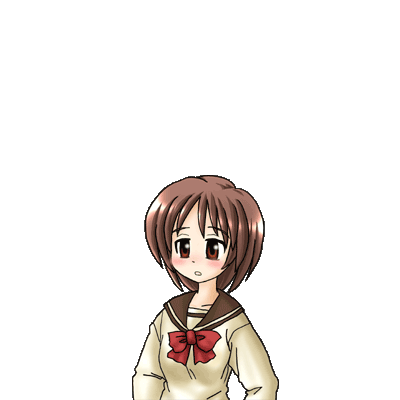

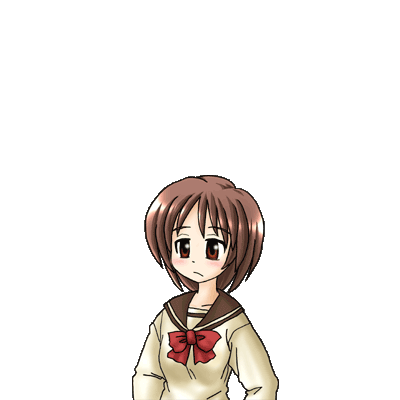

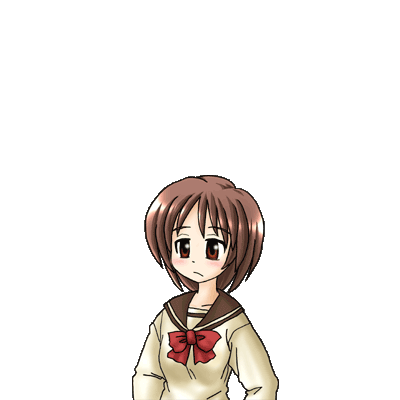

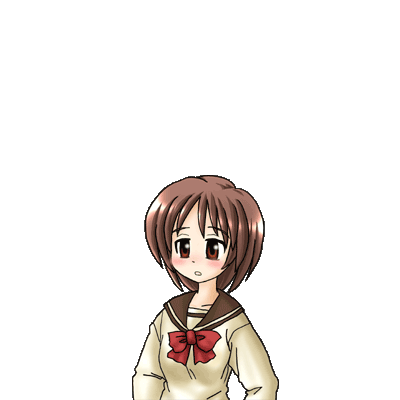

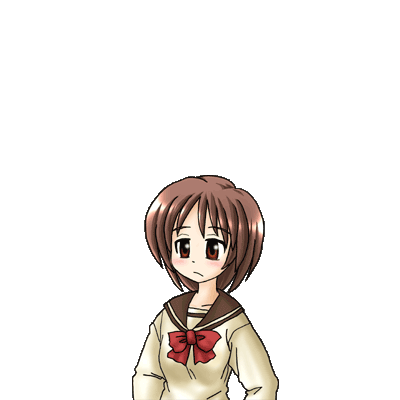
 背景:自宅前
背景:自宅前



 背景:台所
背景:台所




 背景:本屋
背景:本屋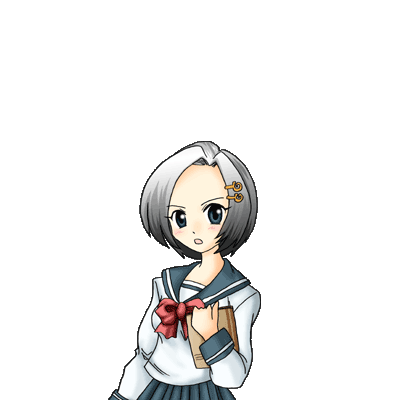

 背景:本屋
背景:本屋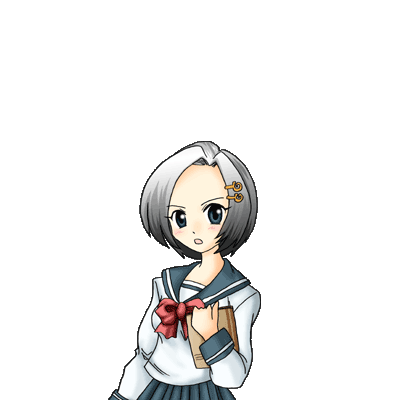

 背景:商店街
背景:商店街



 背景:台所
背景:台所











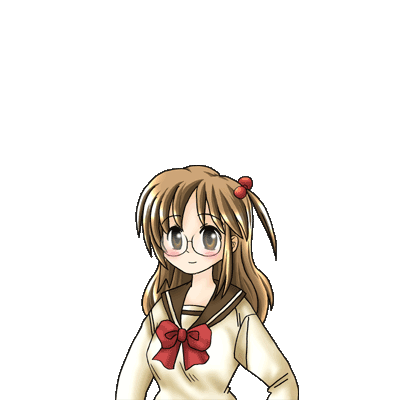
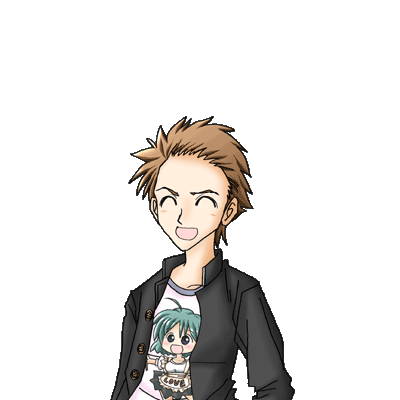




 背景:町
背景:町


 背景:通学路
背景:通学路 背景:ゲームセンター
背景:ゲームセンター
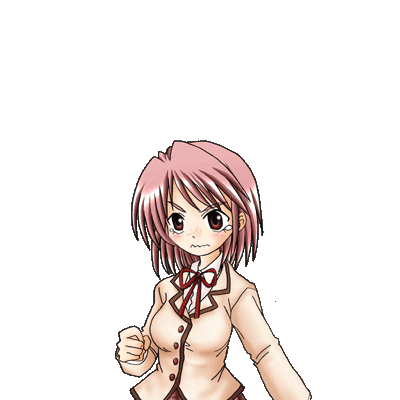








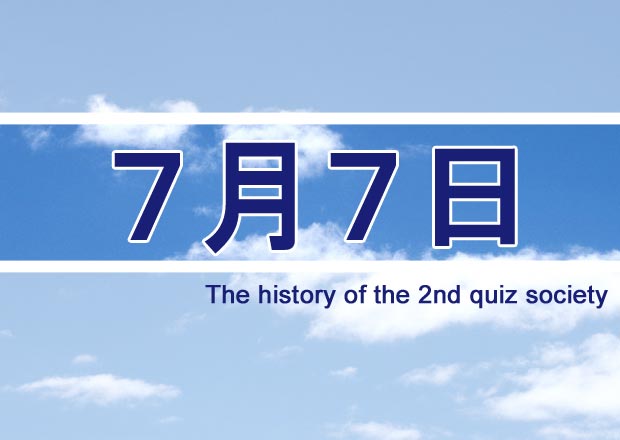
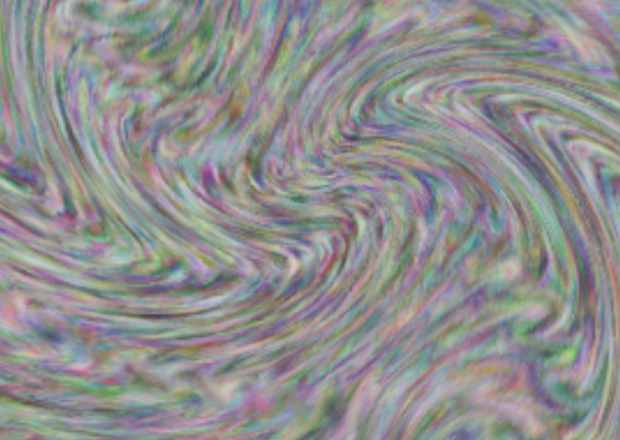 背景:ぐにゃ~
背景:ぐにゃ~
 背景:自室
背景:自室








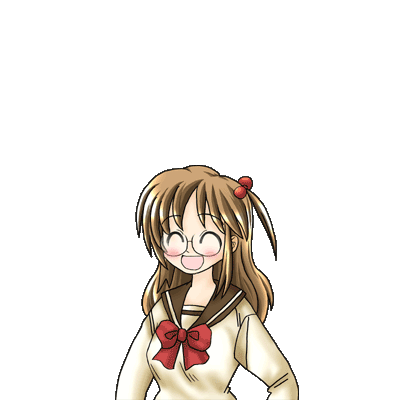







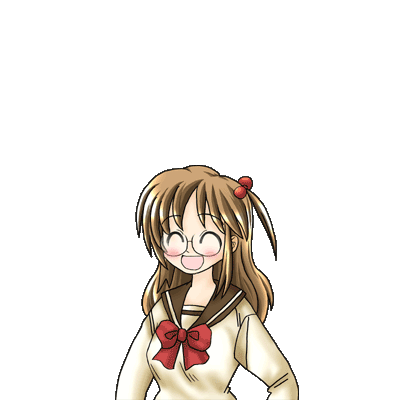



 背景:マンション前
背景:マンション前





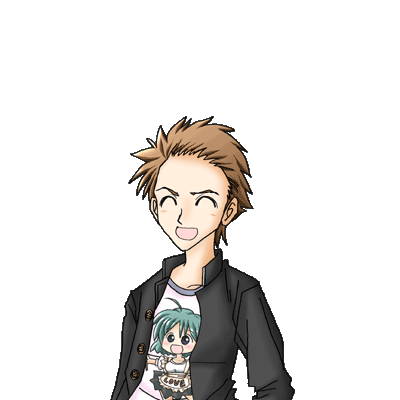

 背景:学校
背景:学校



 背景:教室
背景:教室



 背景:売店
背景:売店
 背景:屋上
背景:屋上


 背景:屋上
背景:屋上
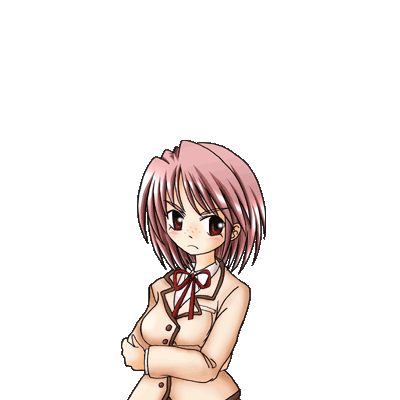








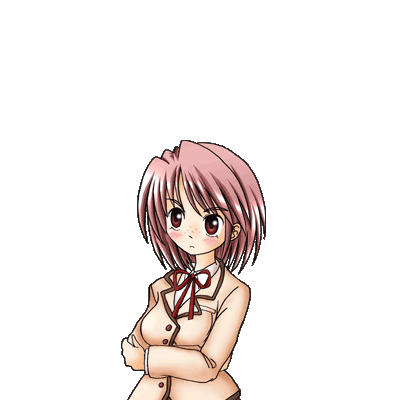

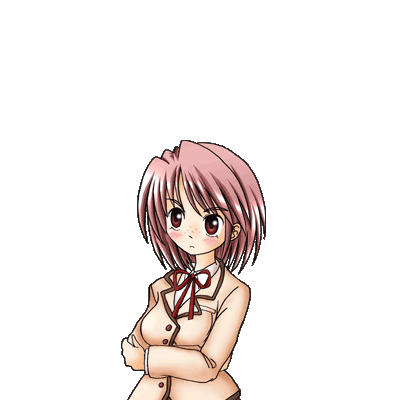

 背景:階段
背景:階段 背景:廊下
背景:廊下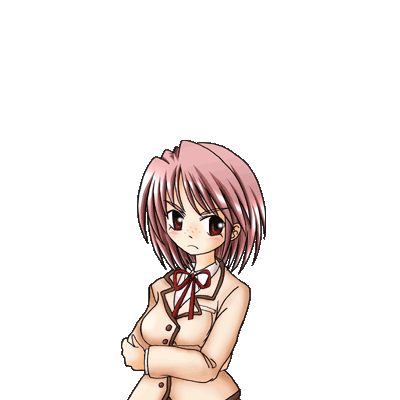




 背景:教室
背景:教室

 放課後。
放課後。


 背景:学校
背景:学校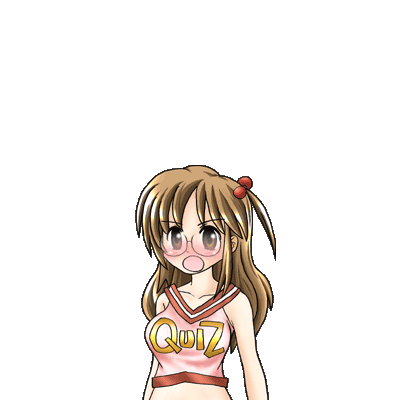
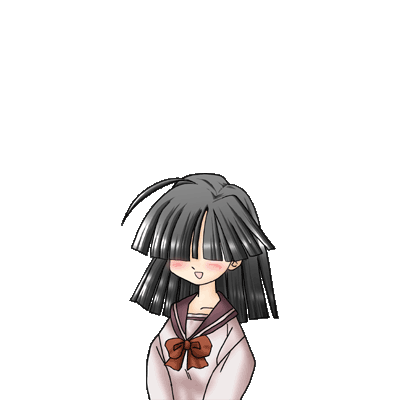

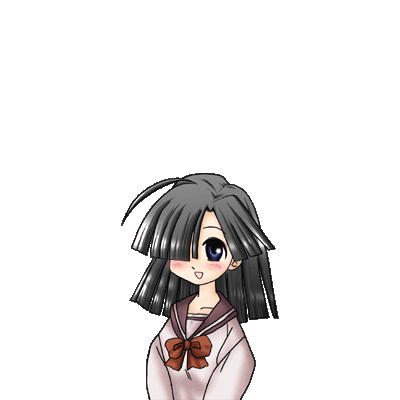
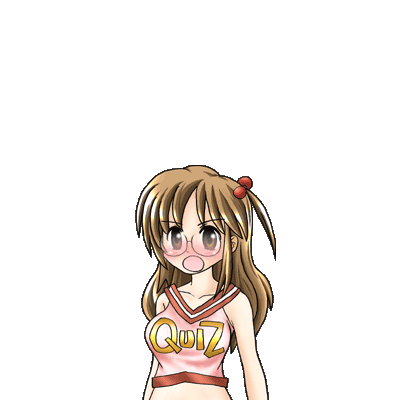

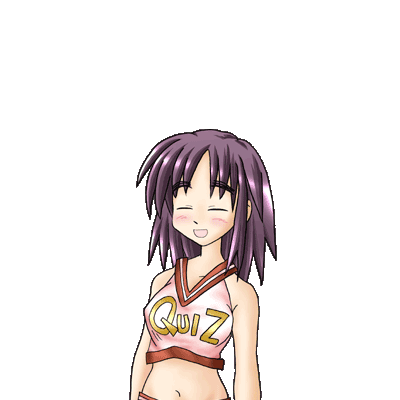
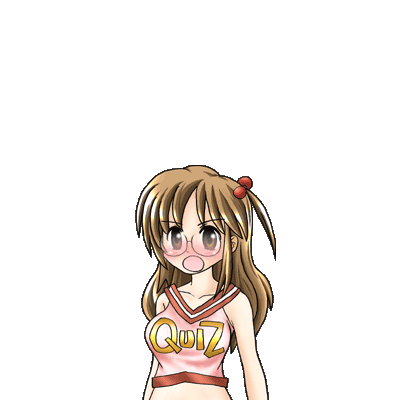

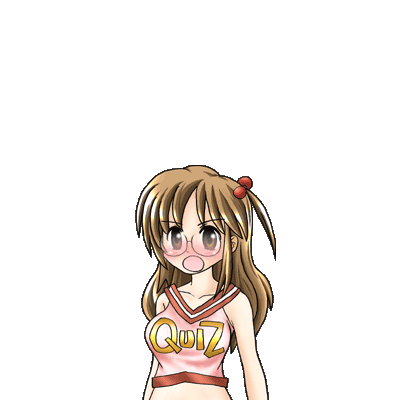



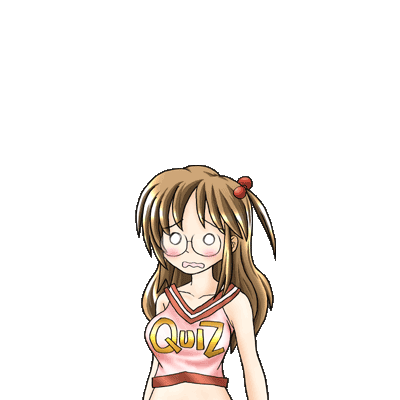

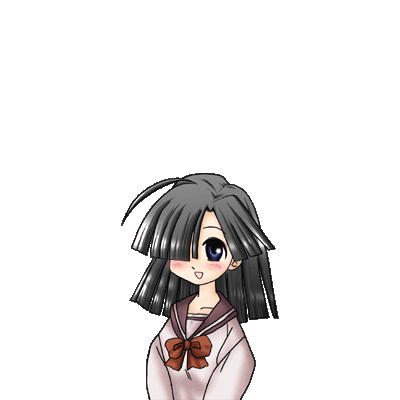
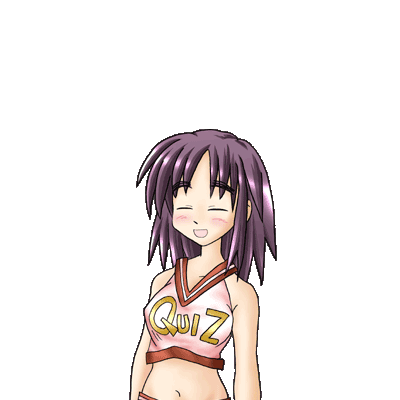
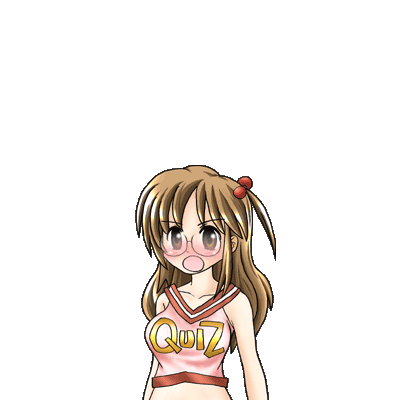
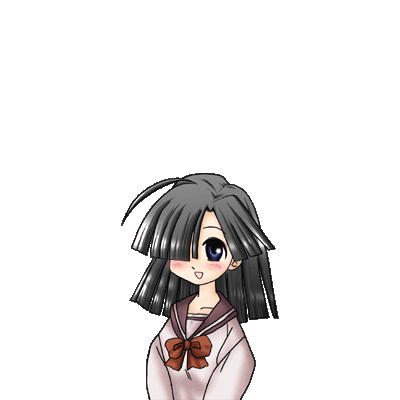
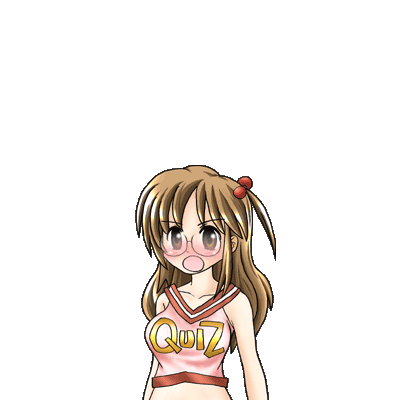


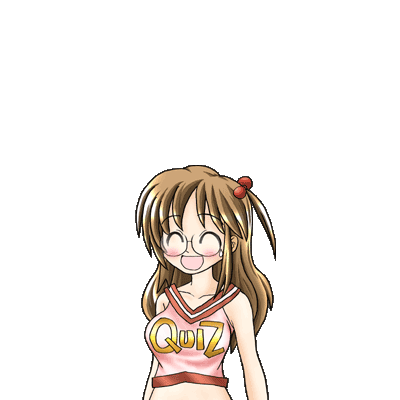


 背景:裏門(新しく探す)
背景:裏門(新しく探す)



 背景:本屋
背景:本屋


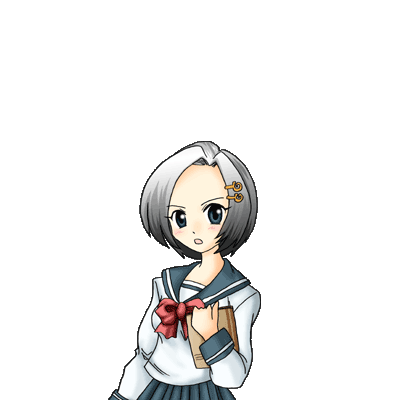
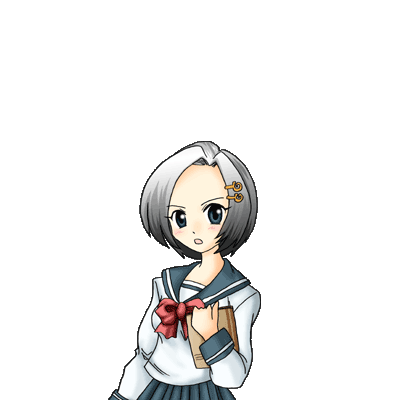



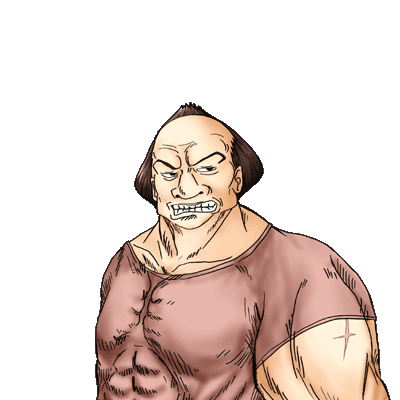
 背景:通学路
背景:通学路




 背景:部室
背景:部室


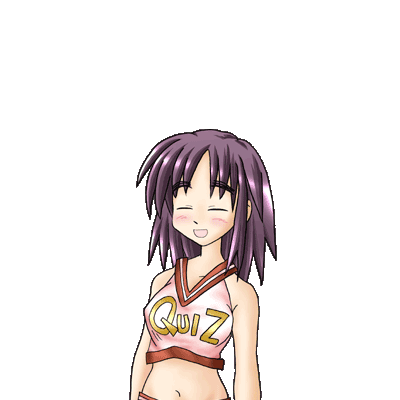
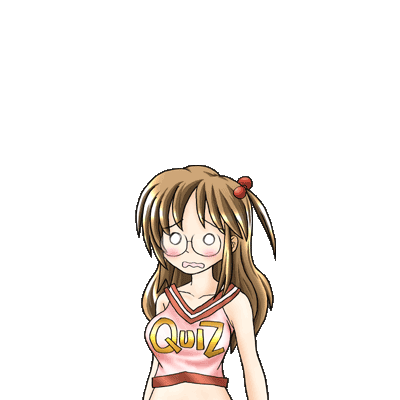

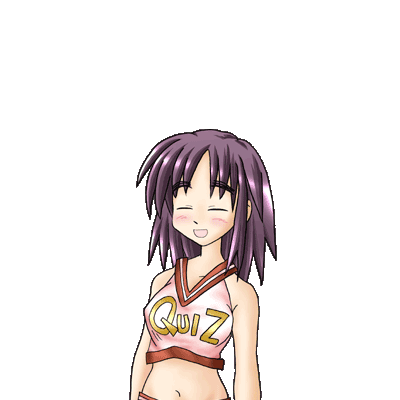

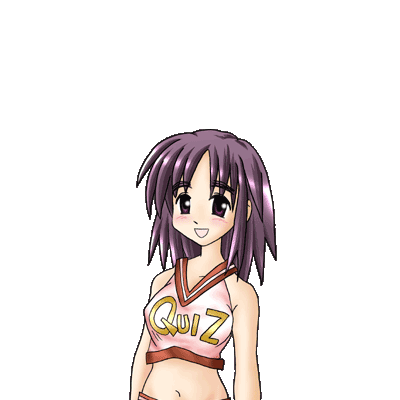
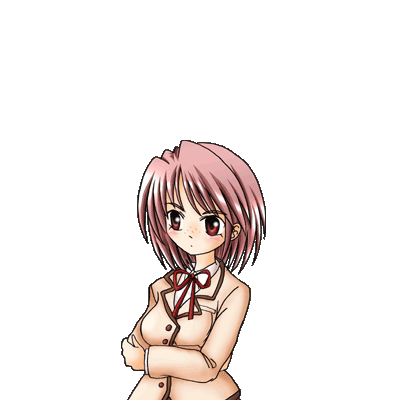

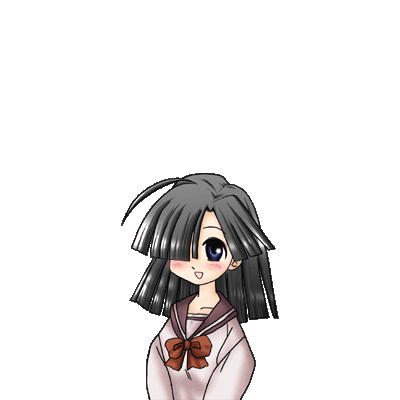
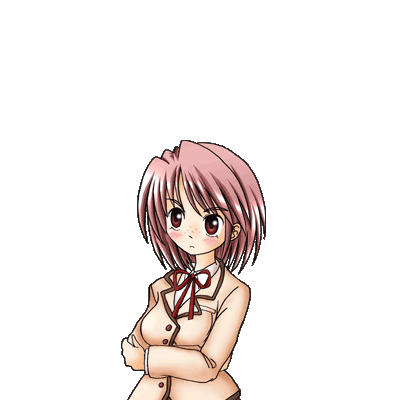
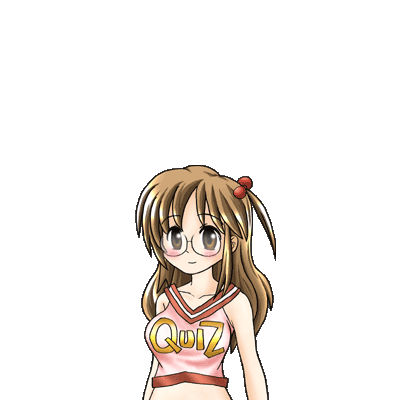

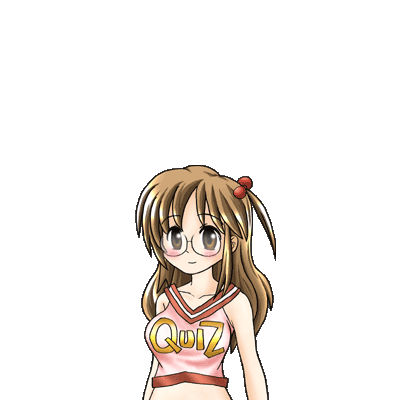


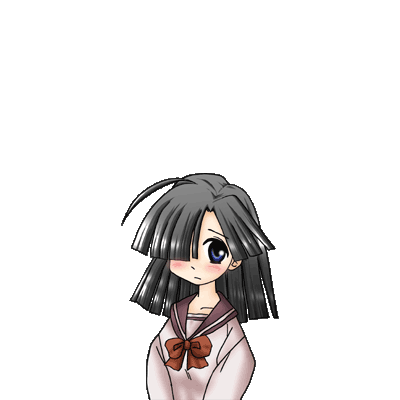



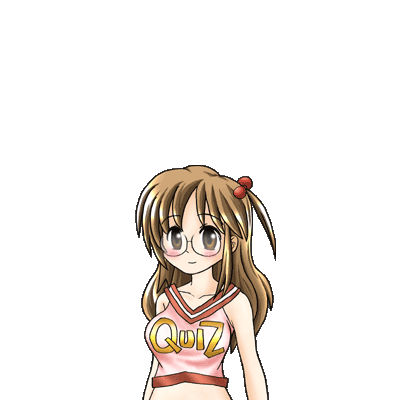

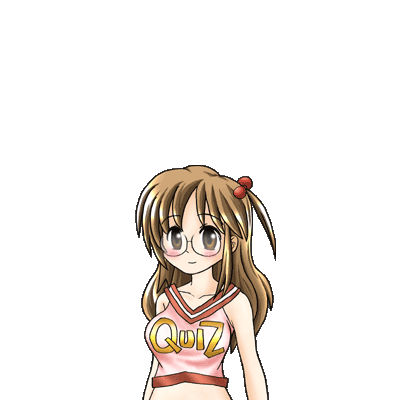

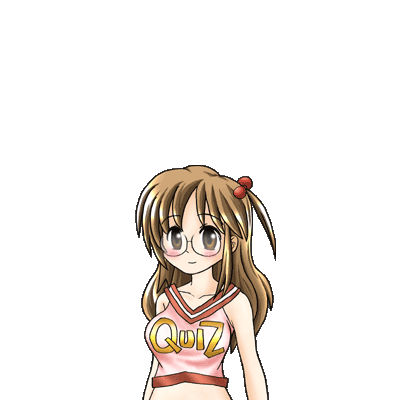
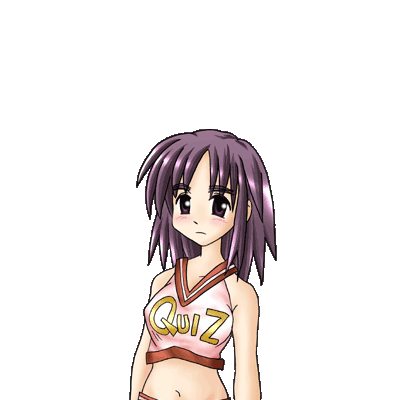
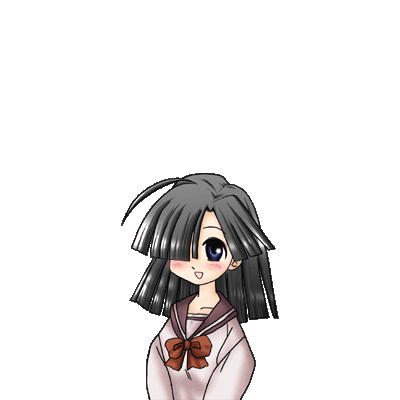









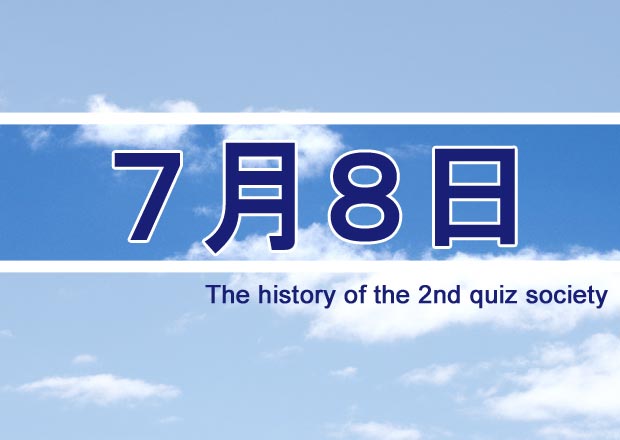





 背景:部室
背景:部室





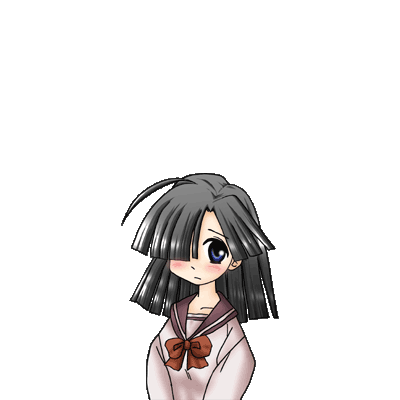

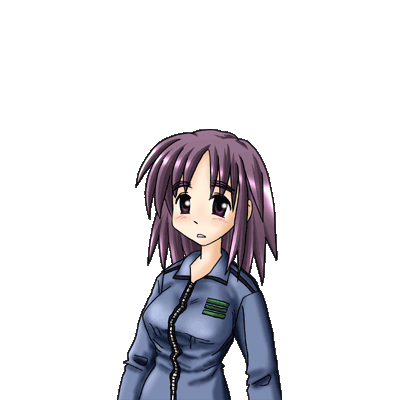




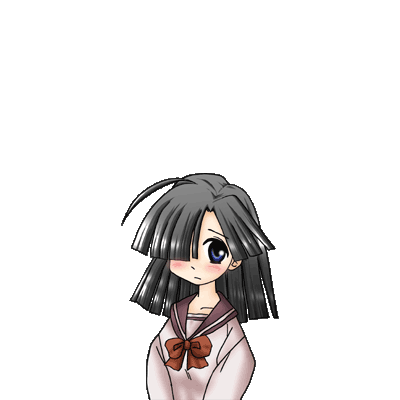






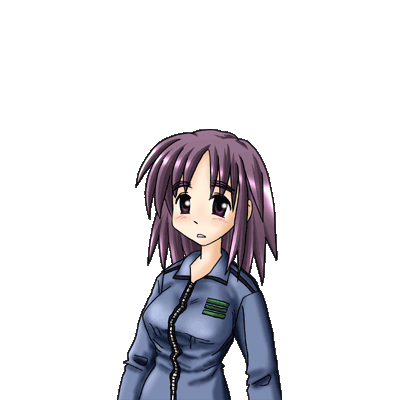
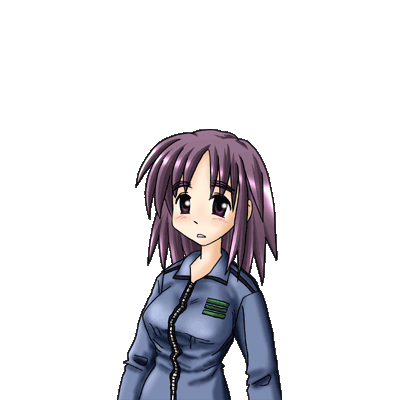


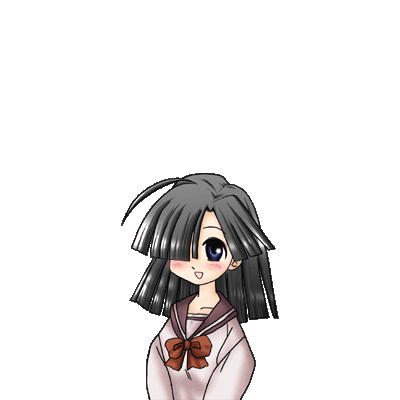
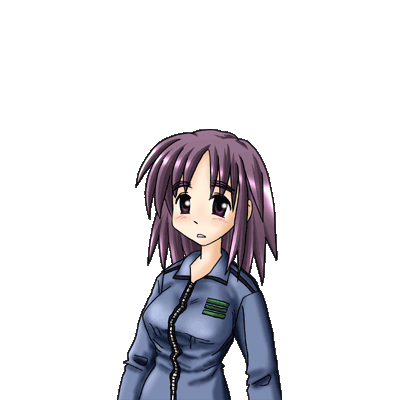
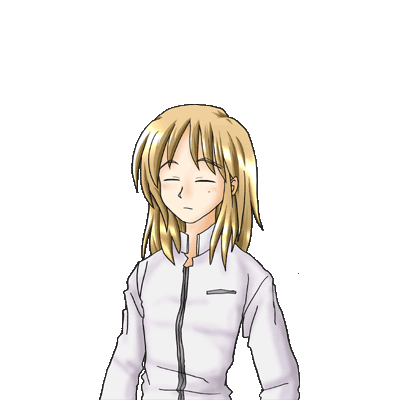
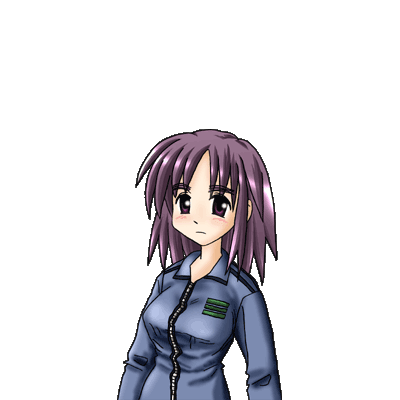




 背景:通学路
背景:通学路




 背景:学校
背景:学校 背景:教室
背景:教室




 背景:生徒会室
背景:生徒会室






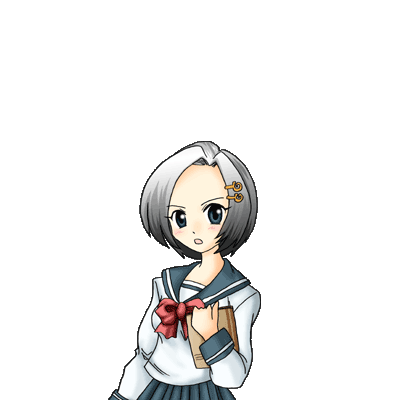





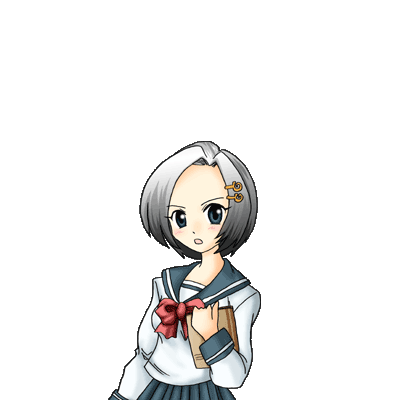

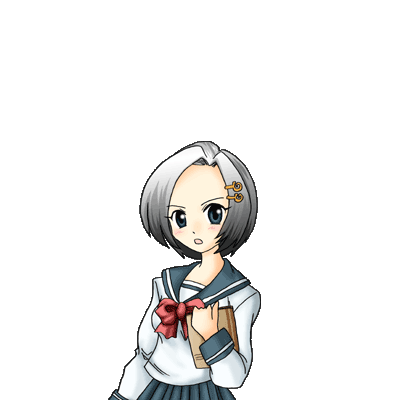





 背景:部室棟
背景:部室棟


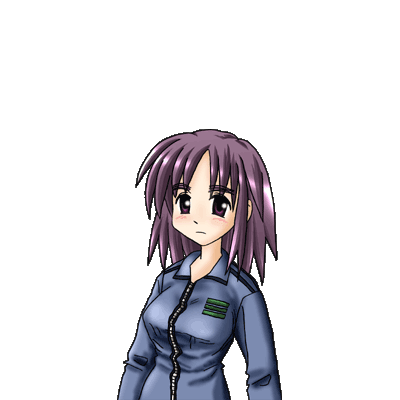






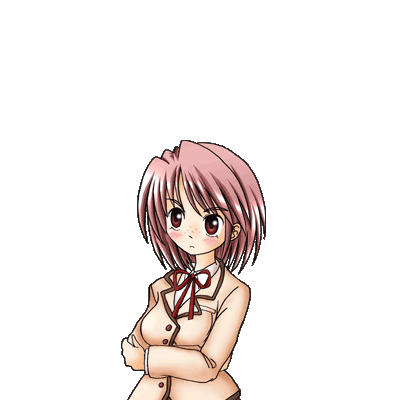


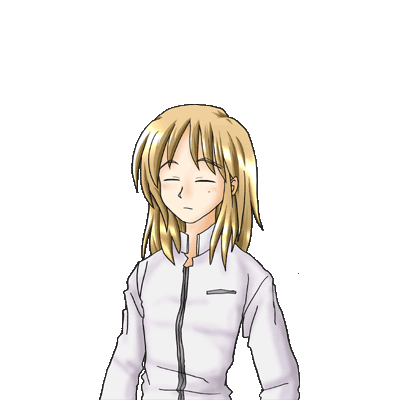
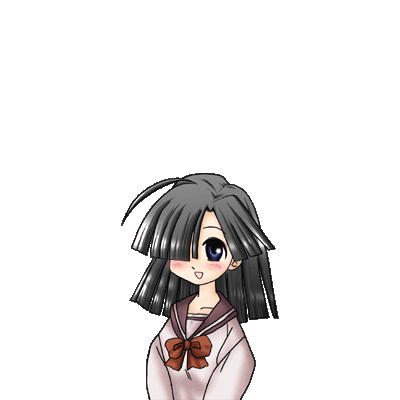
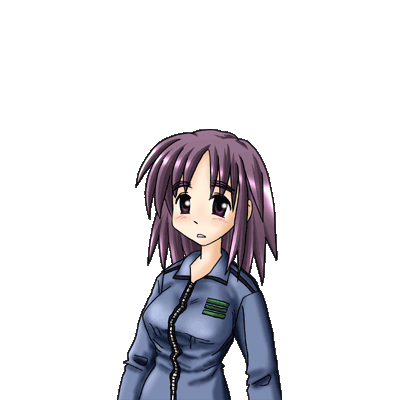




 背景:教室
背景:教室





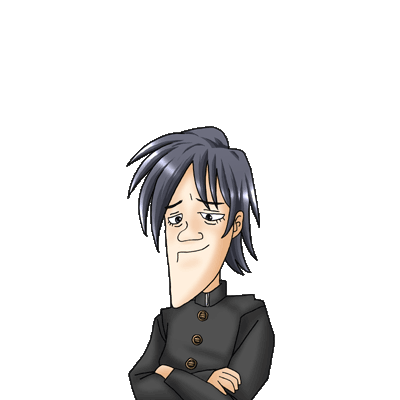
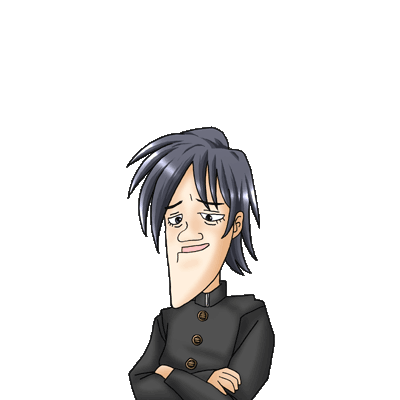
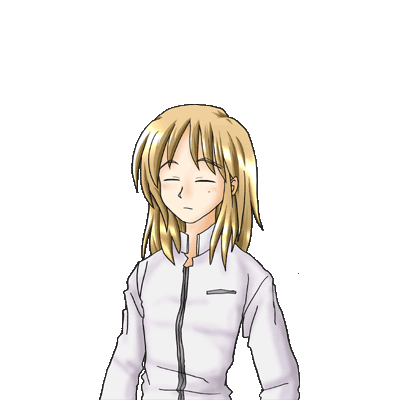
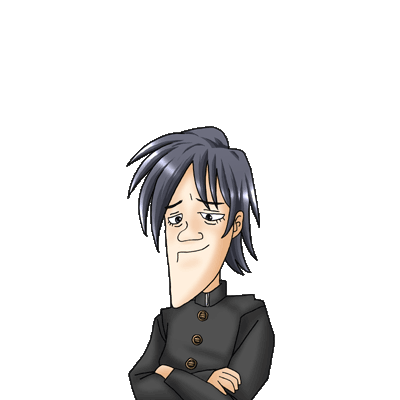
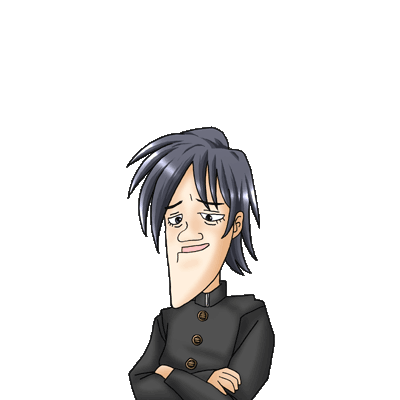




 背景:会場
背景:会場


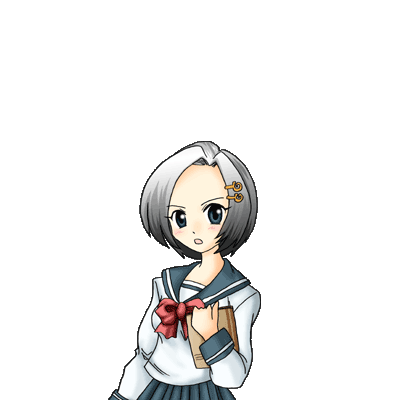
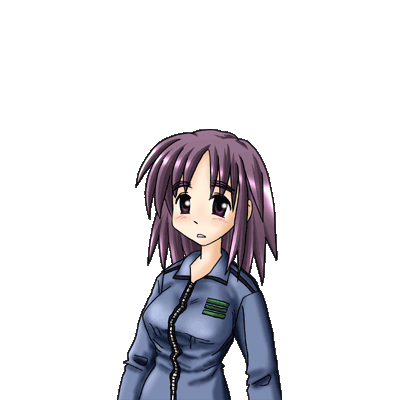
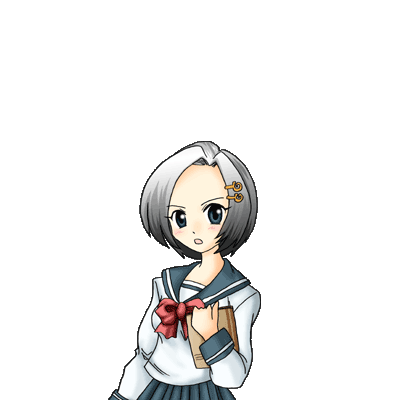
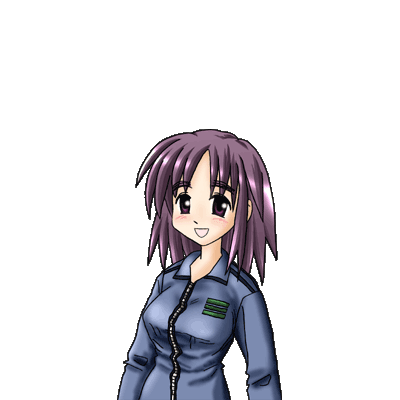
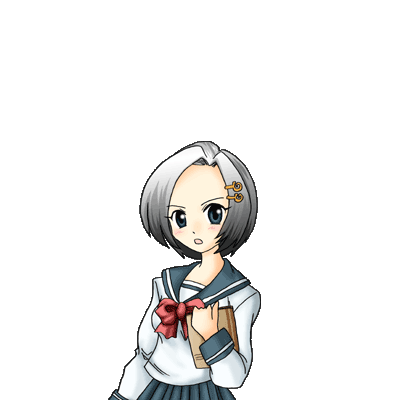
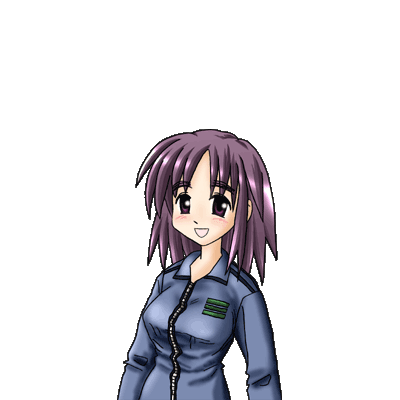
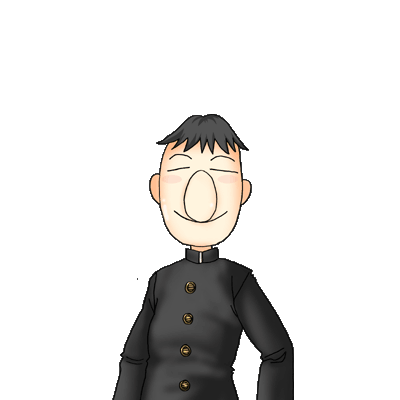
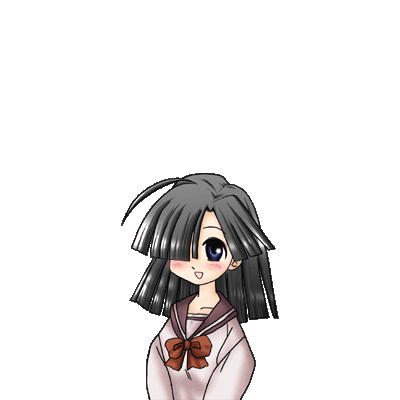

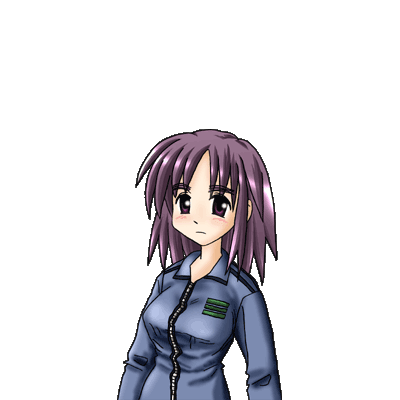
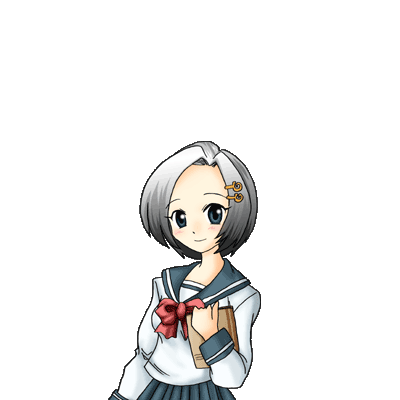




 背景:廊下
背景:廊下



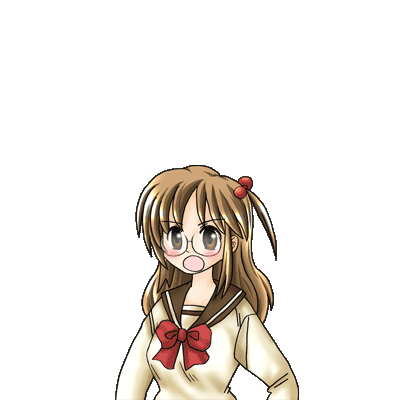

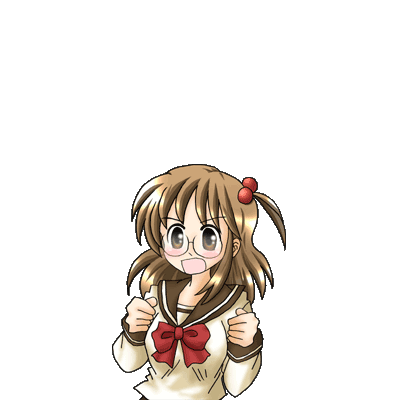
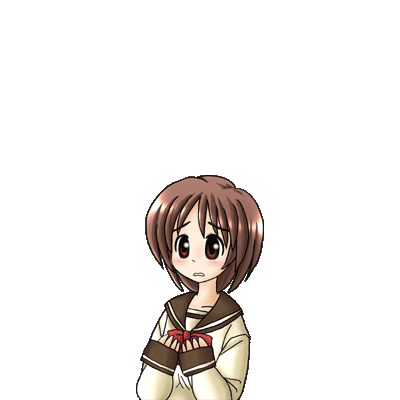
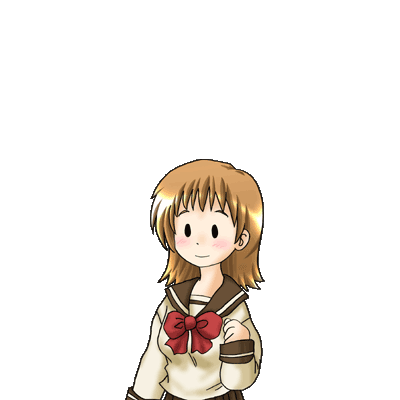
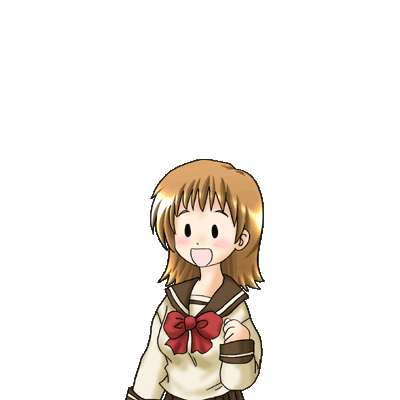




 背景:教室
背景:教室





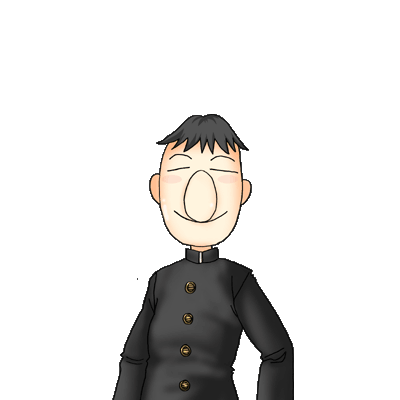

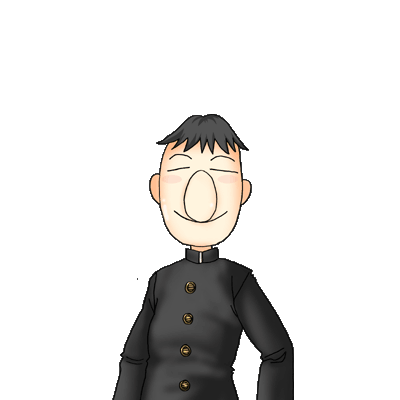





 背景:会場
背景:会場

 わあああああああああ!!!
わあああああああああ!!!
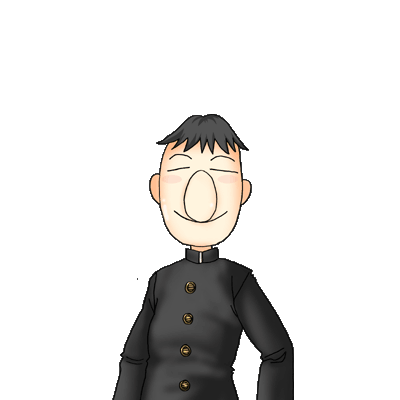

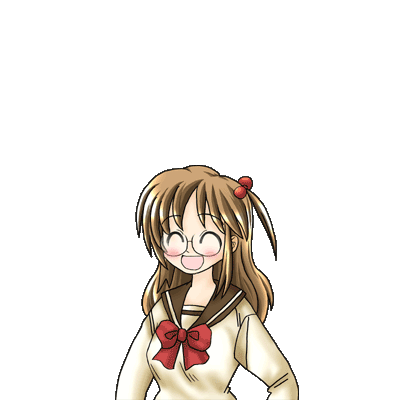
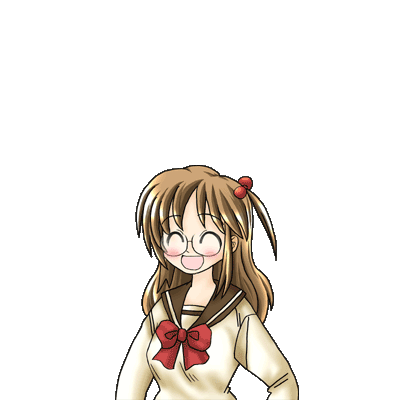
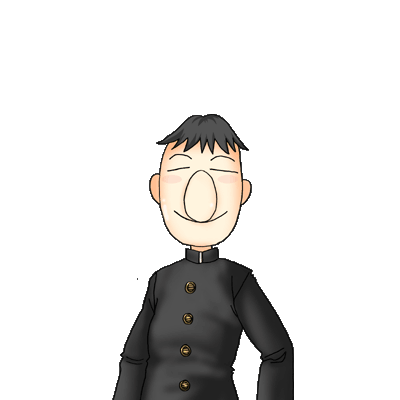
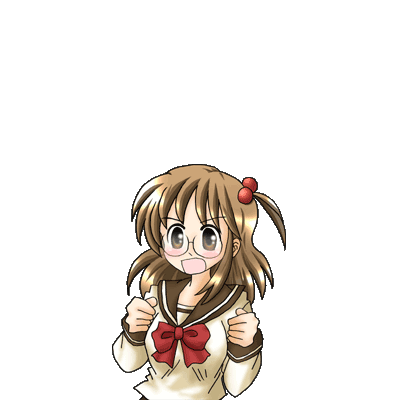
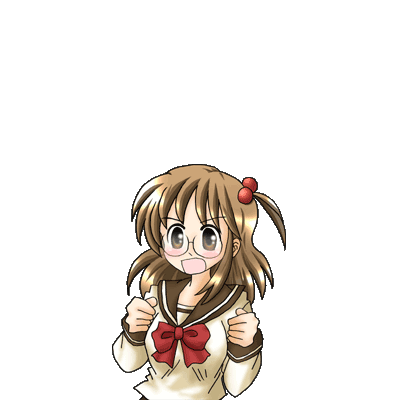

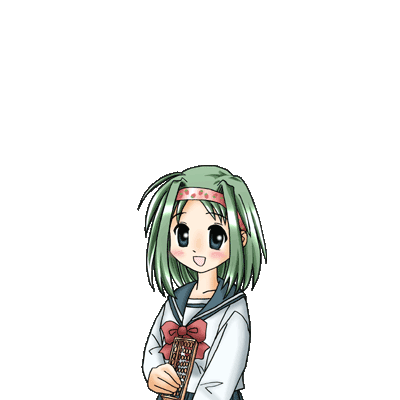
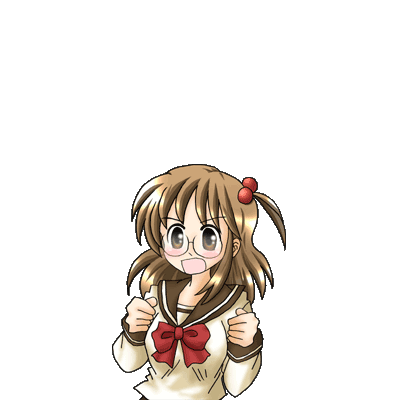
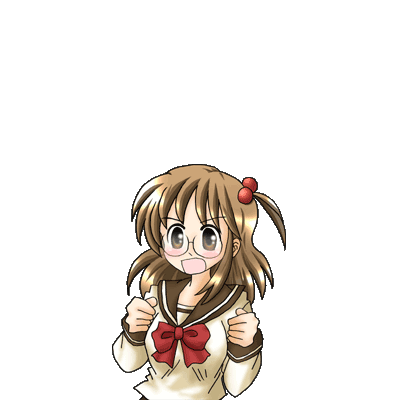
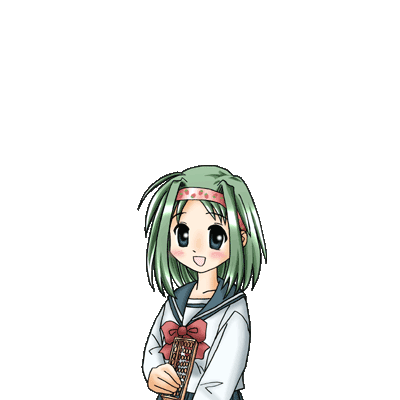
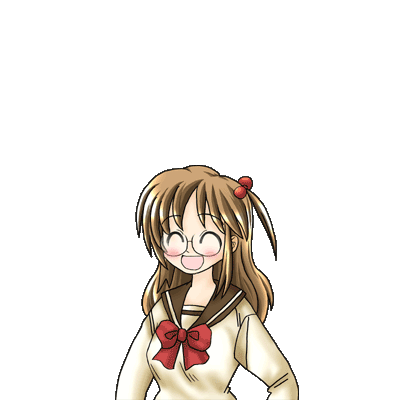
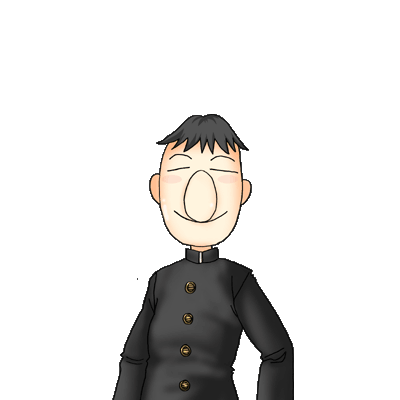

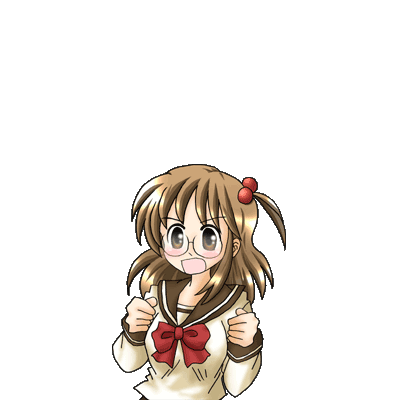









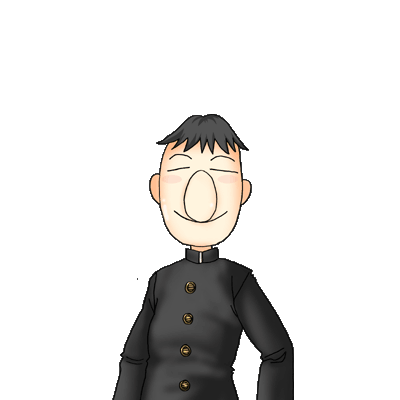

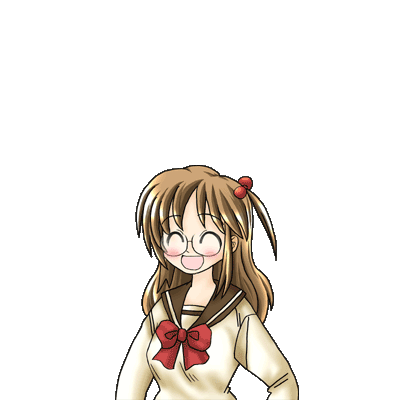

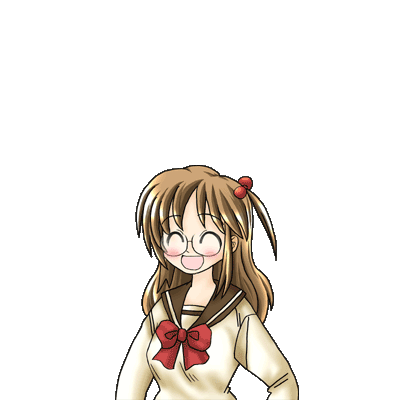
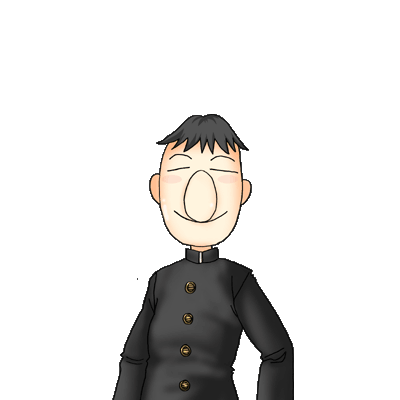


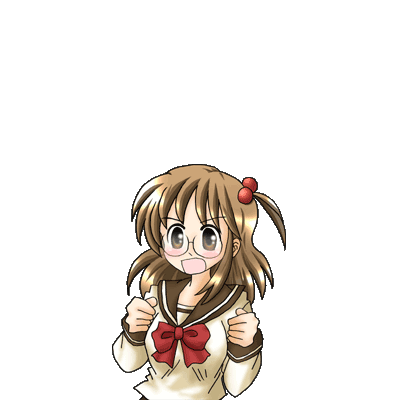
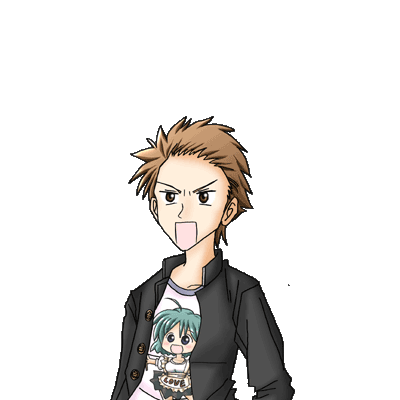
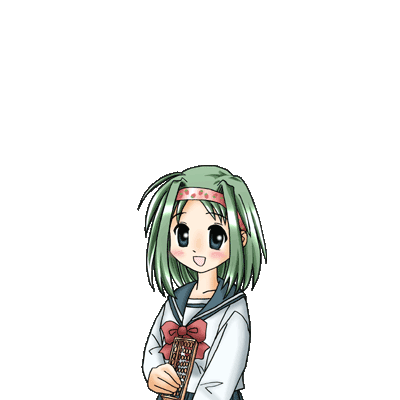
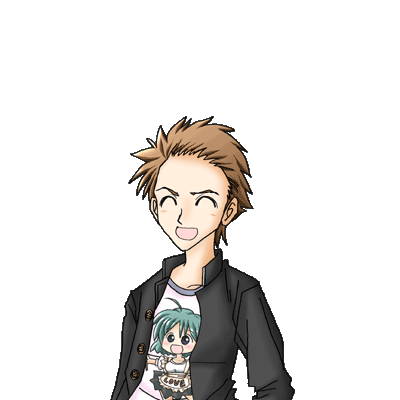
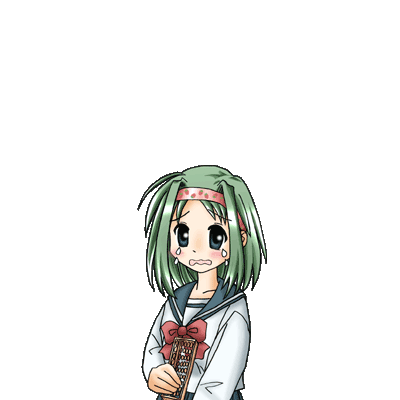
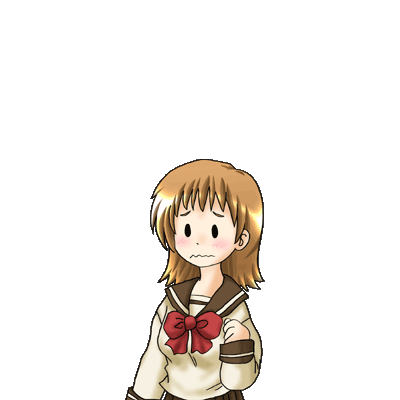
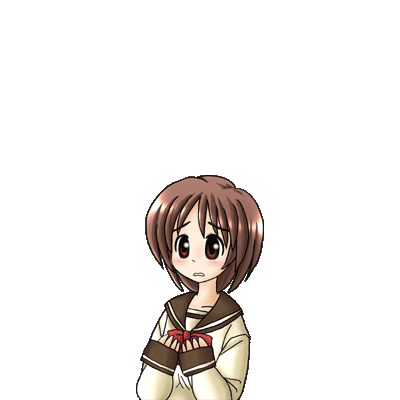
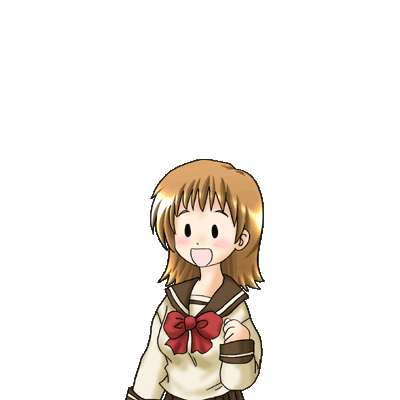
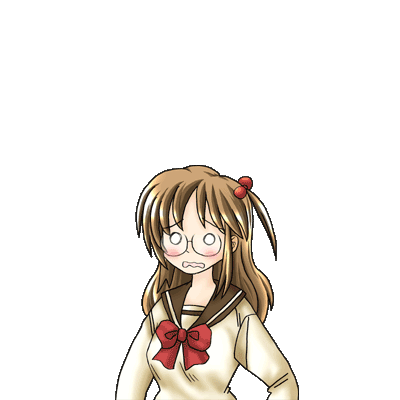
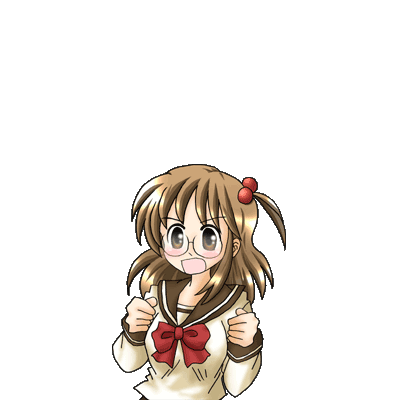
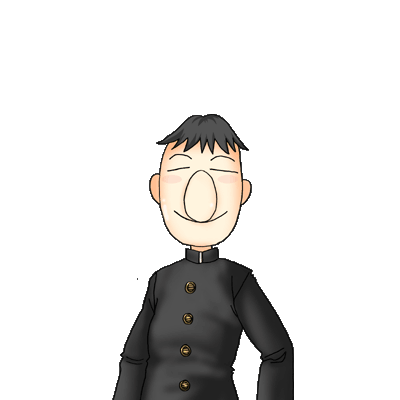

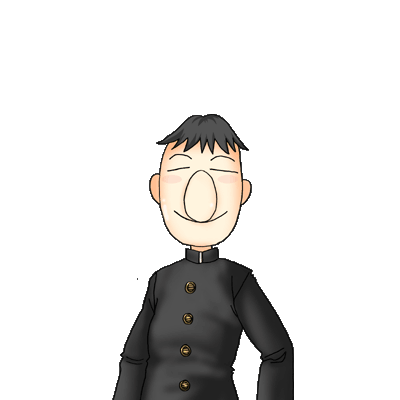

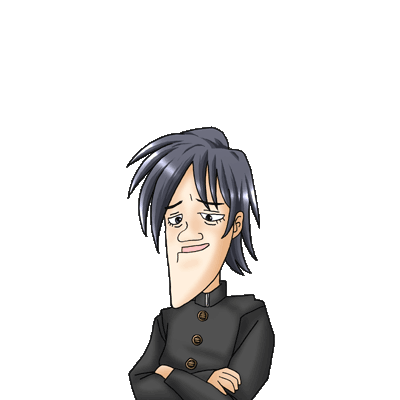


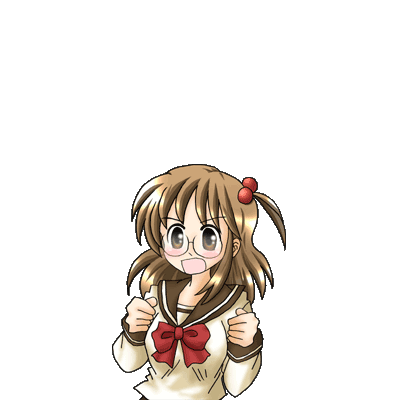
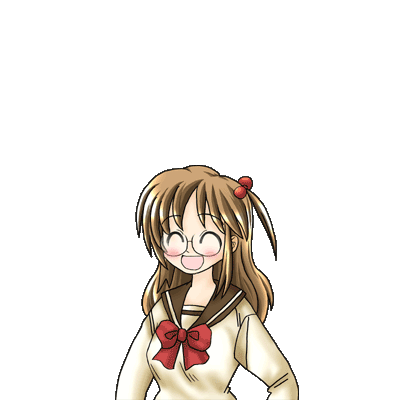

 背景:会場(赤)
背景:会場(赤) 背景:会場
背景:会場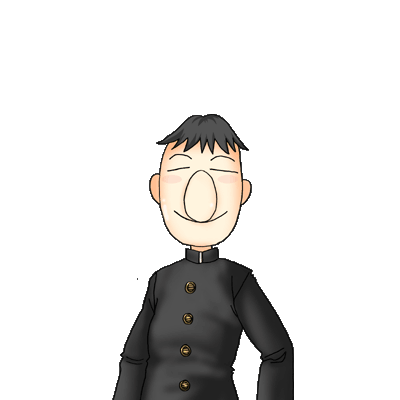

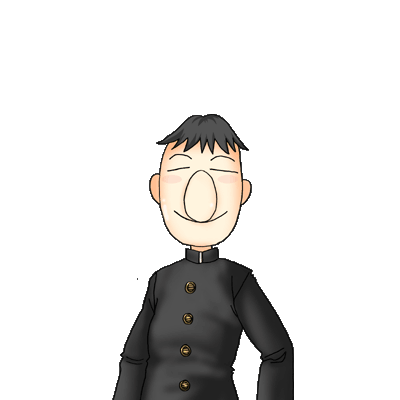

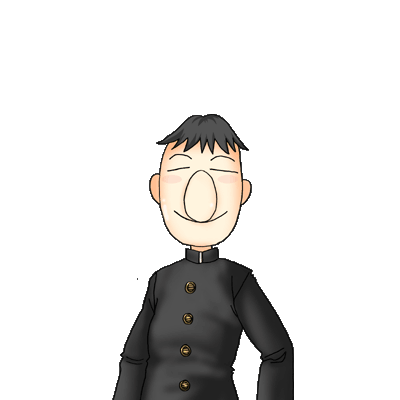






 背景:会場(夜)
背景:会場(夜)

 結局、最後の早押しクイズは木ノ下サニーの勝ちだった。
結局、最後の早押しクイズは木ノ下サニーの勝ちだった。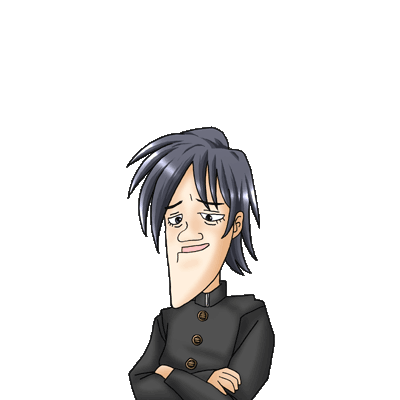

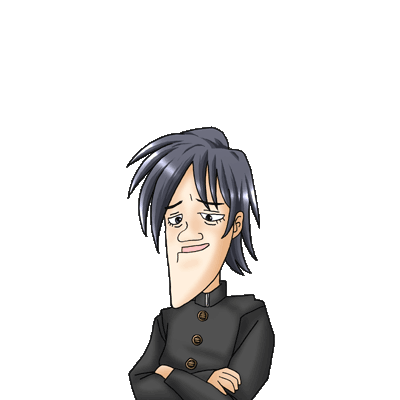

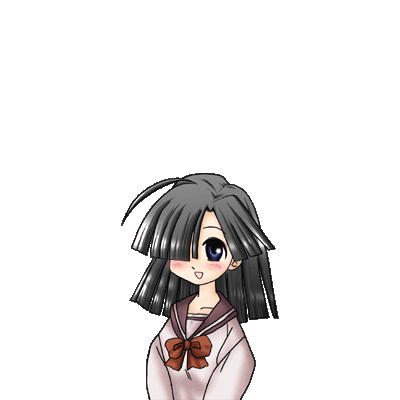
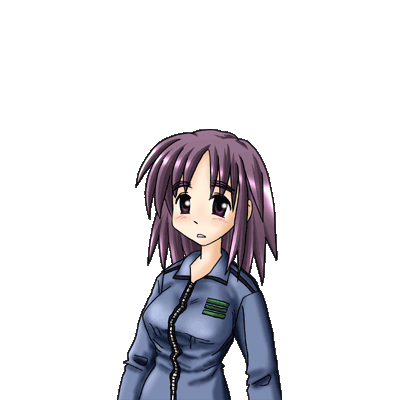
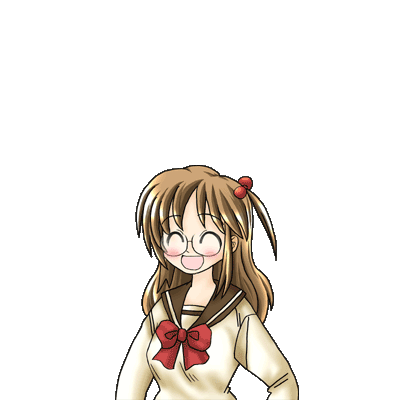
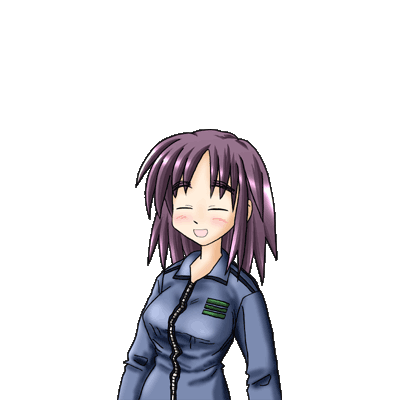

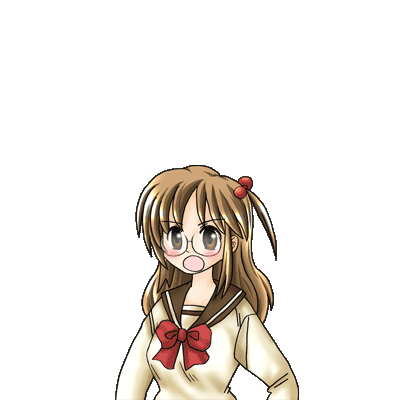


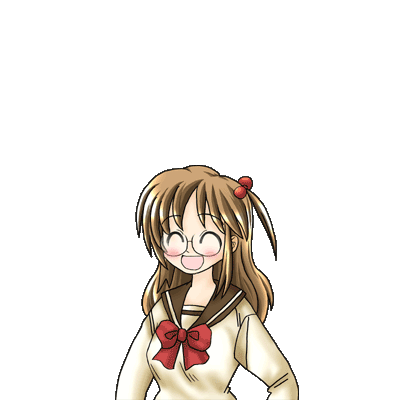

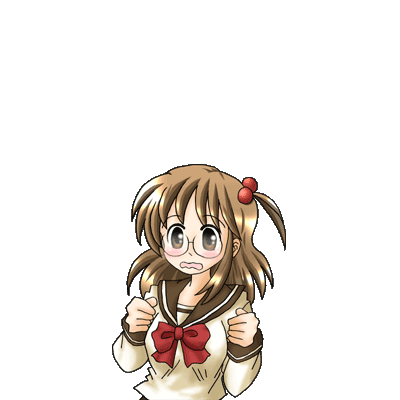













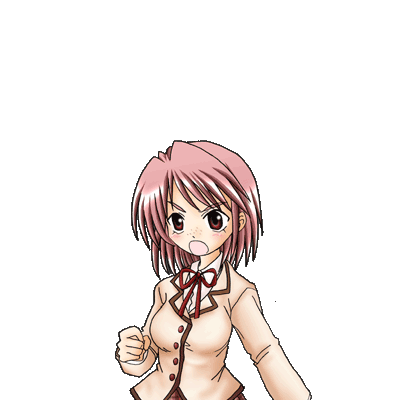


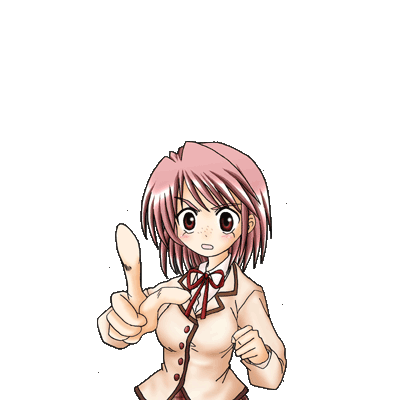








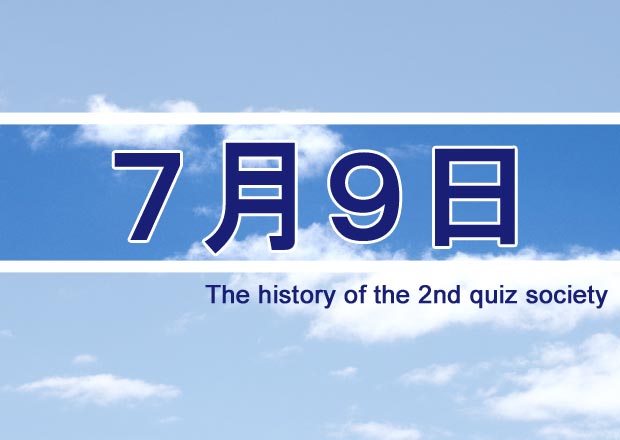





 背景:寝室(ちまき)
背景:寝室(ちまき)


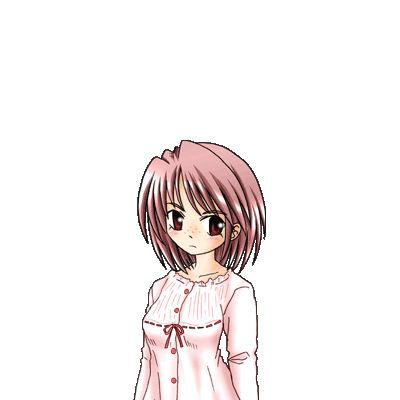
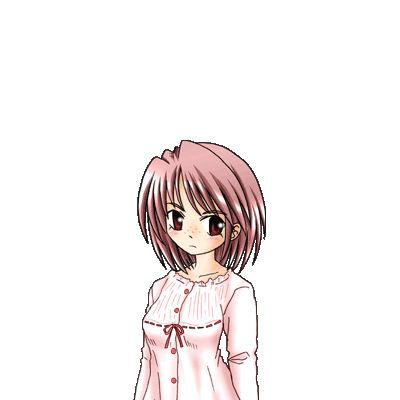




 背景:会場(グレー)
背景:会場(グレー)

 彼は、ゆっくりと身体を折った。
彼は、ゆっくりと身体を折った。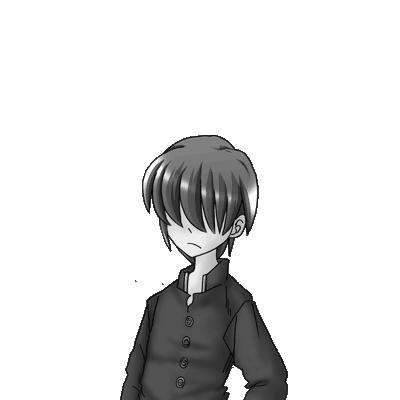
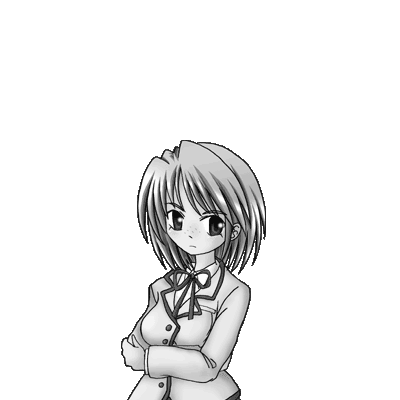
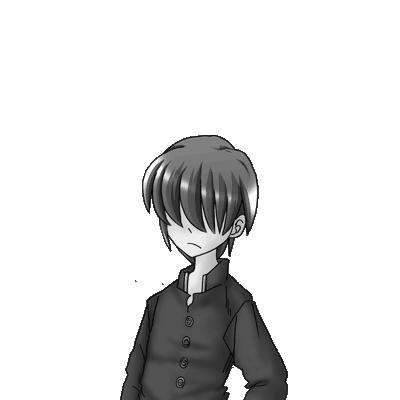
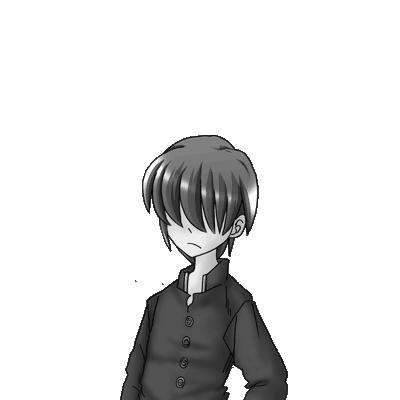
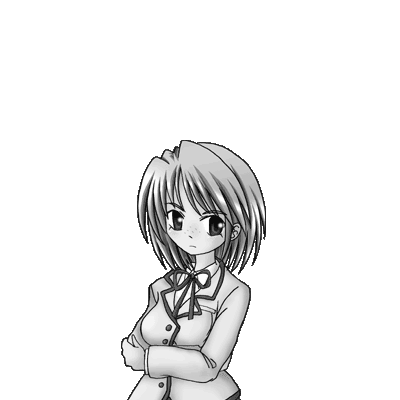
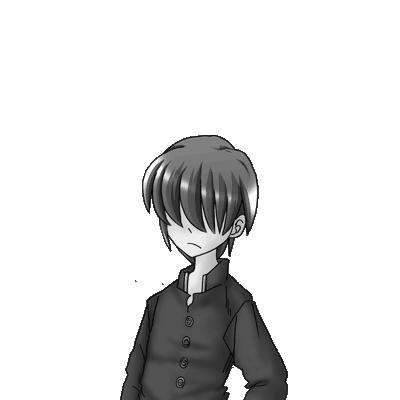
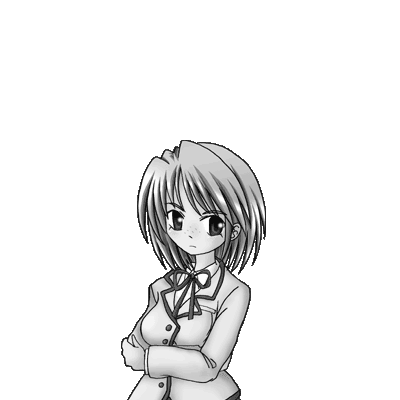
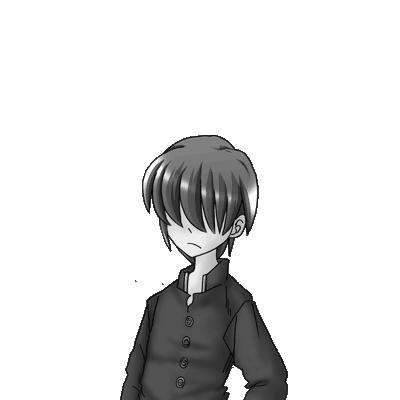
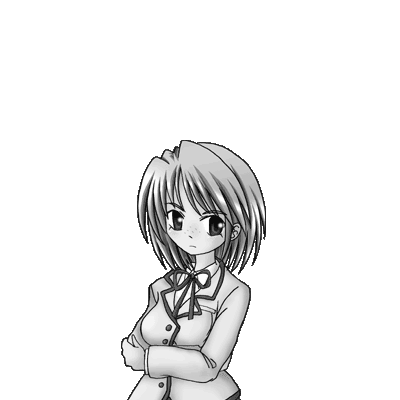
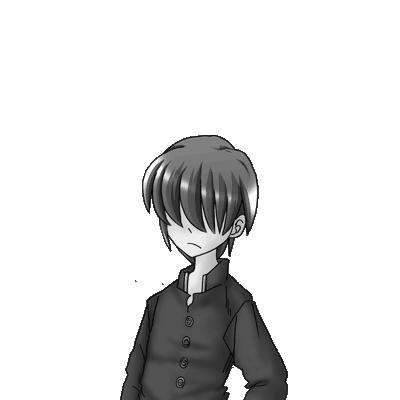
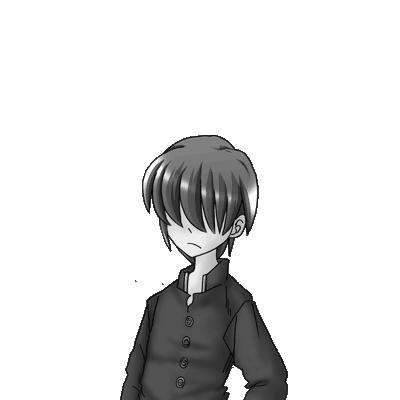




 背景:寝室(ちまき)
背景:寝室(ちまき)


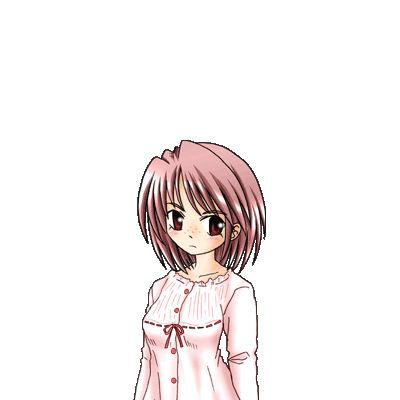




 背景:アメリカ
背景:アメリカ

 2025年4月
アメリカ
2025年4月
アメリカ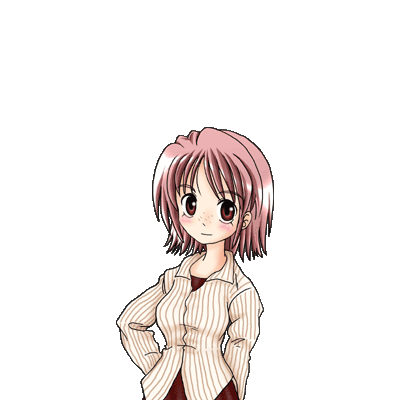
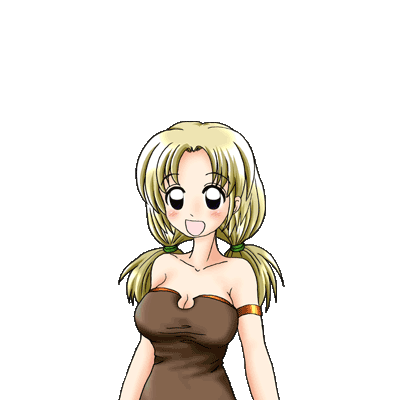
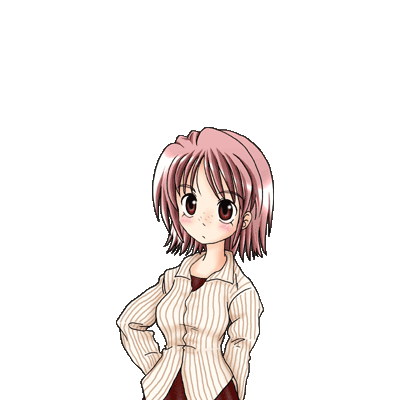
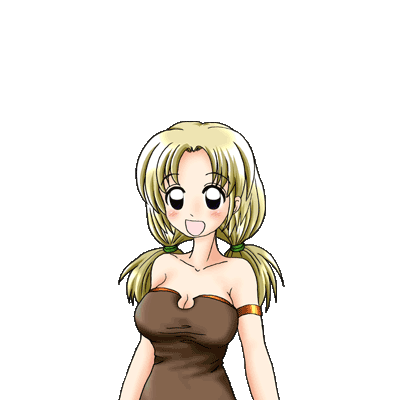
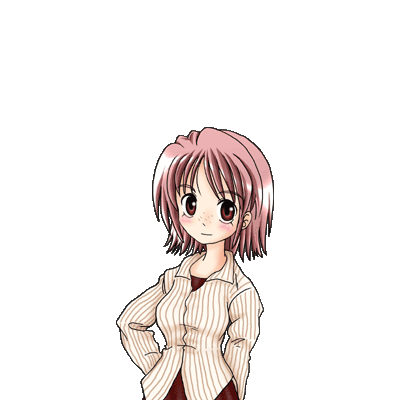
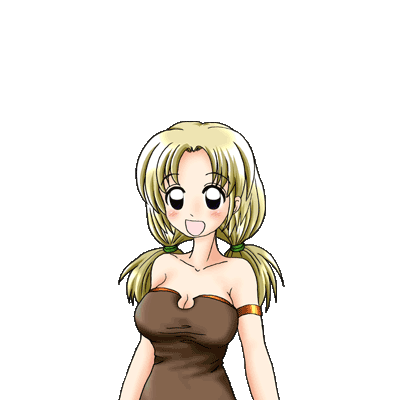
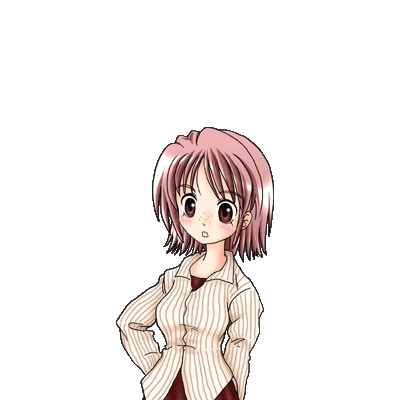
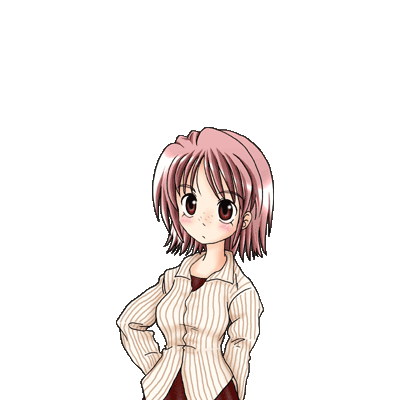
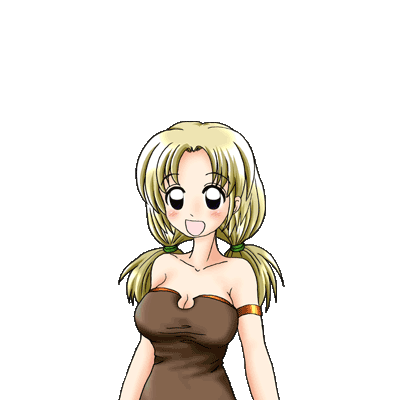
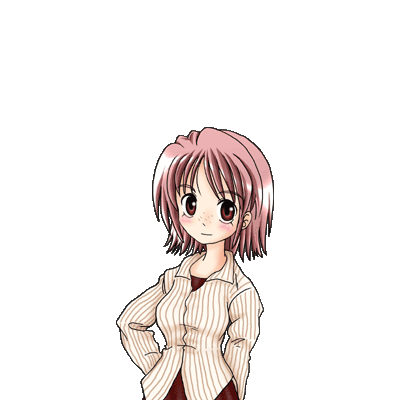
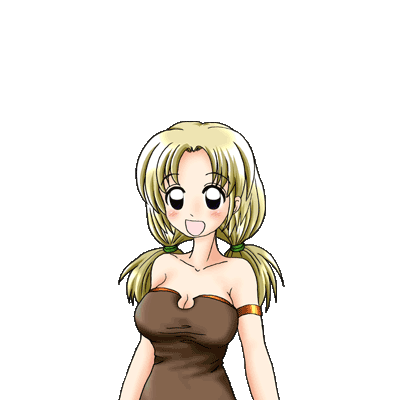
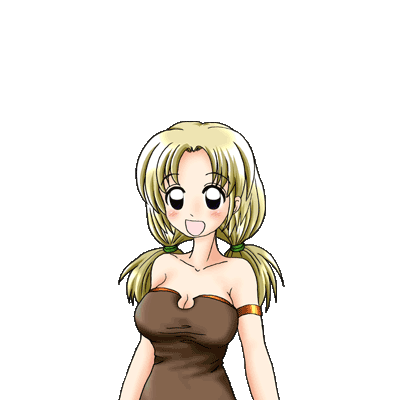
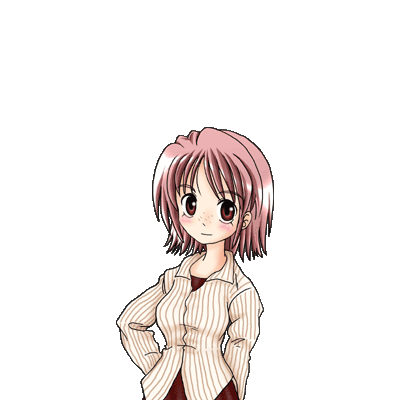
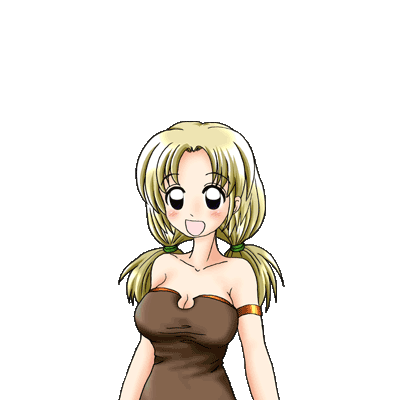
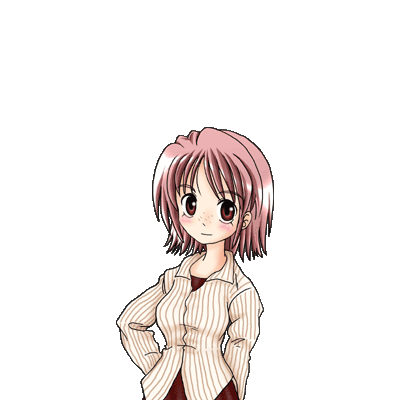
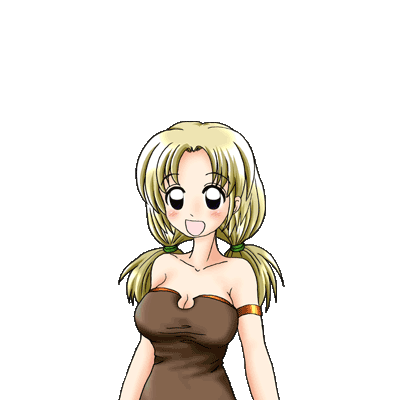
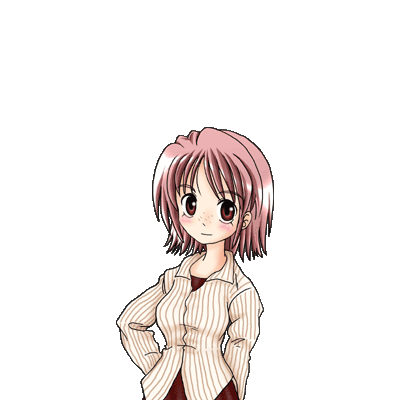
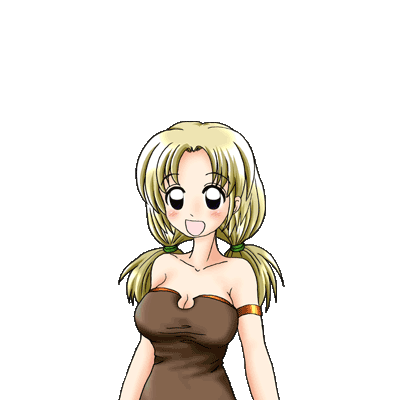
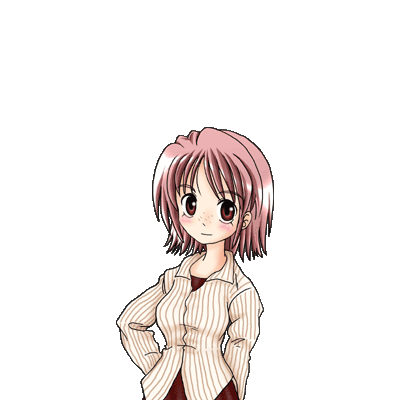
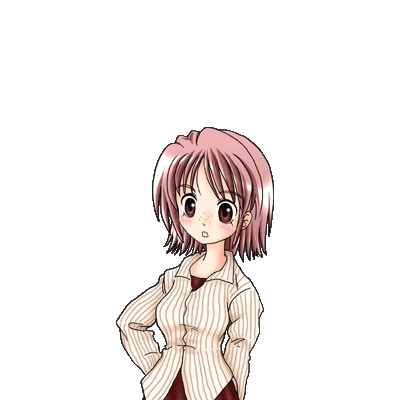
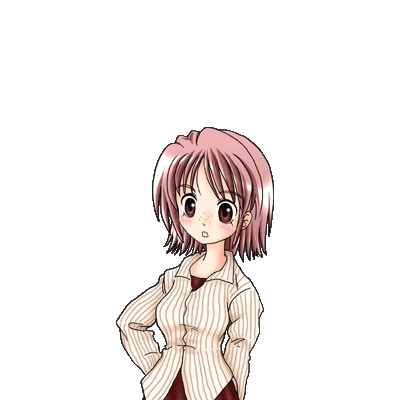
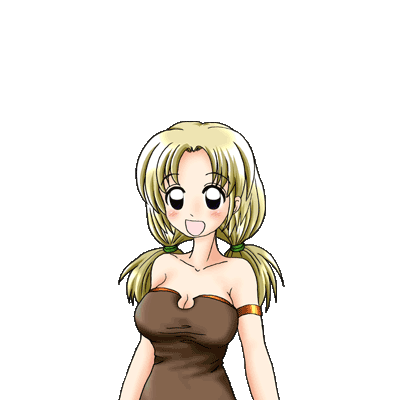
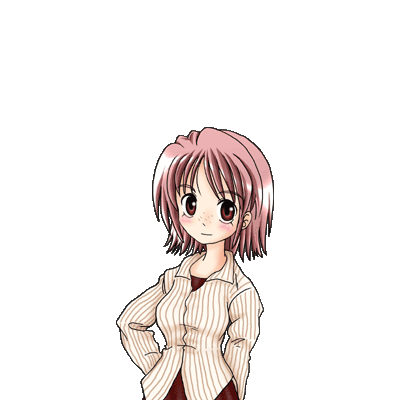
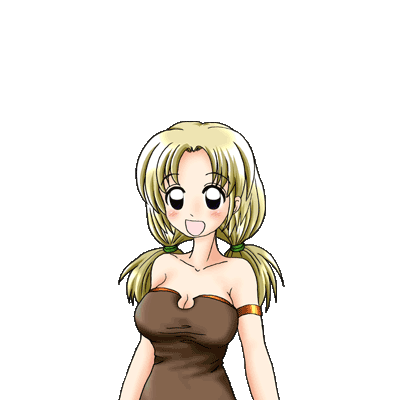
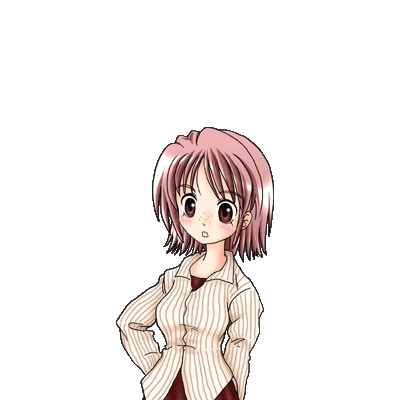
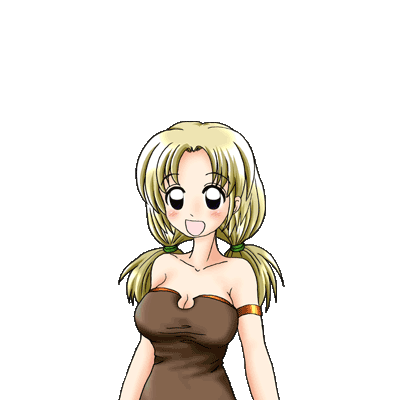
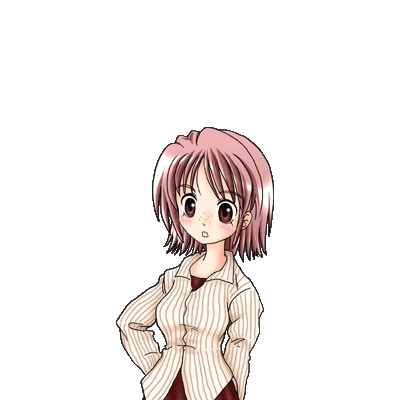
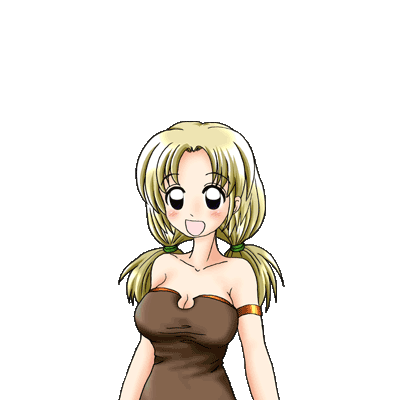
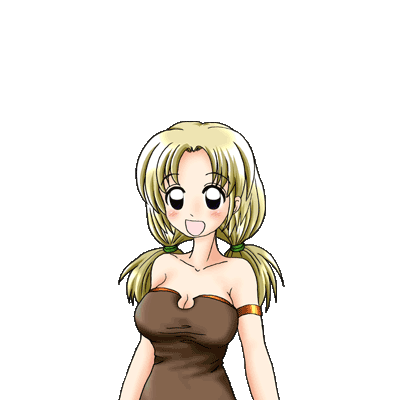




 背景:アメリカ
背景:アメリカ

 午後の部が始まった。
午後の部が始まった。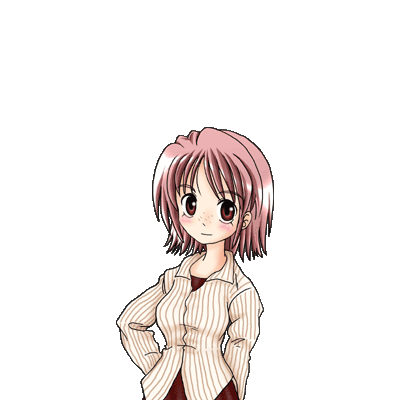
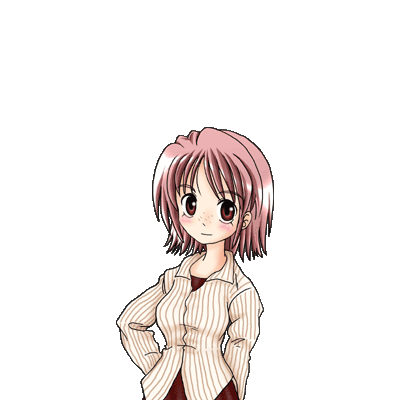
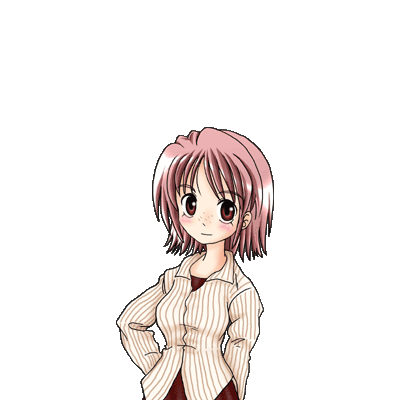
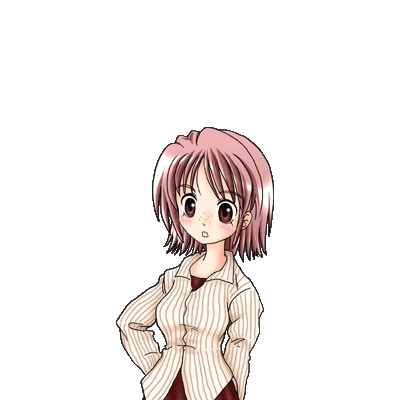
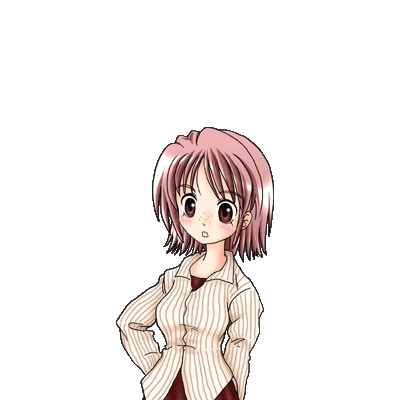
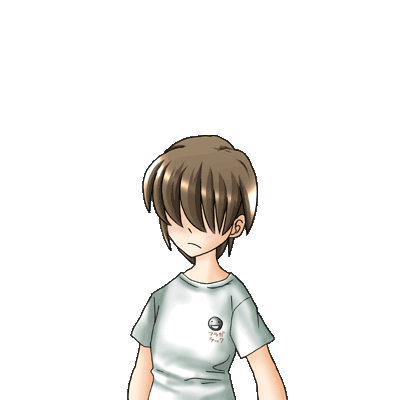
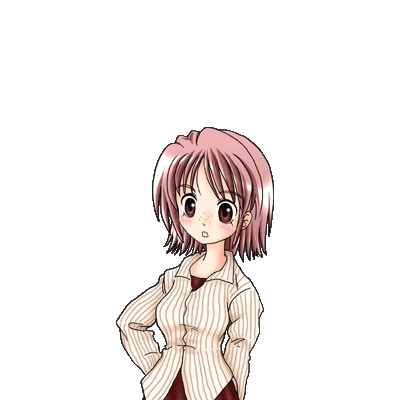
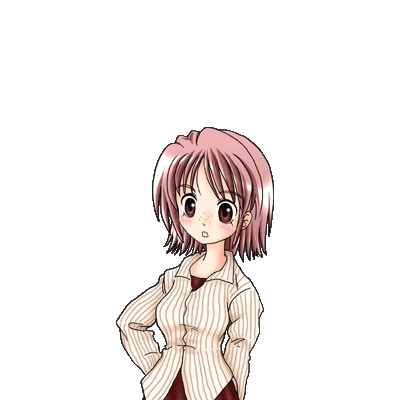
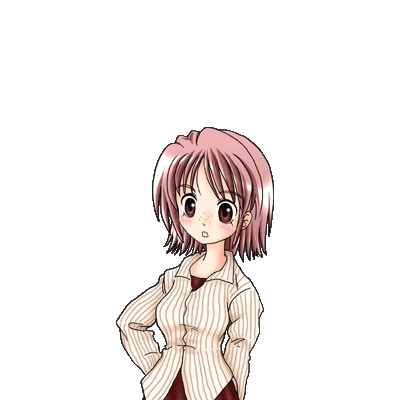
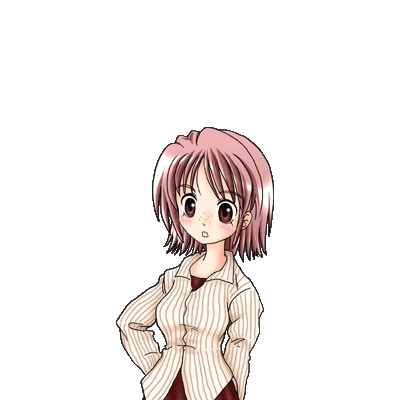
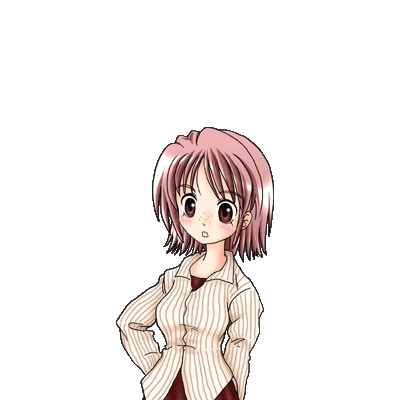




 背景:寝室(ちまき)
背景:寝室(ちまき)


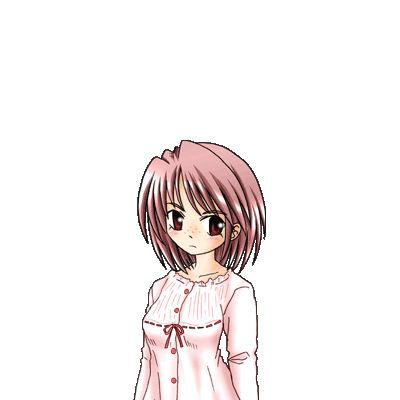




 背景:病院
背景:病院

 大会が終ってから1週間後、ちまきはエイリーの見舞いに病院を訪れた。
大会が終ってから1週間後、ちまきはエイリーの見舞いに病院を訪れた。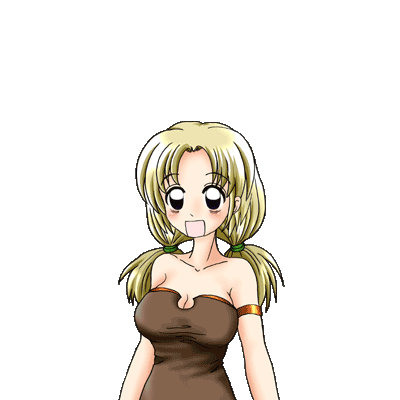
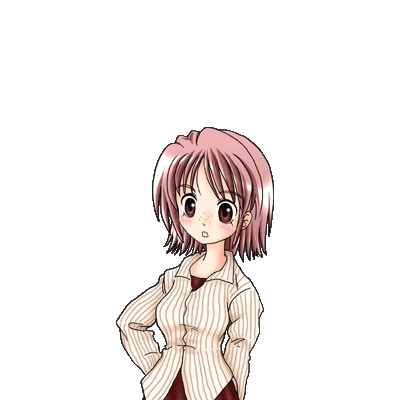
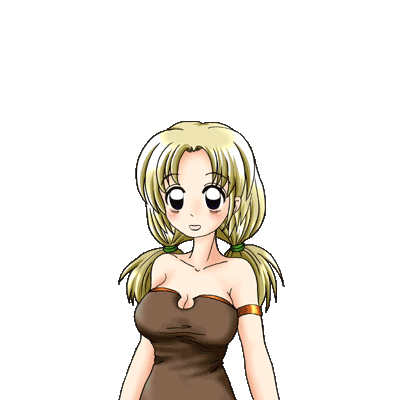
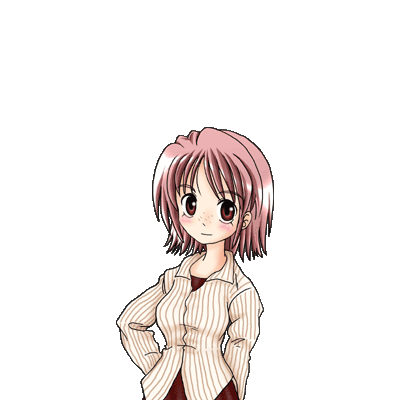
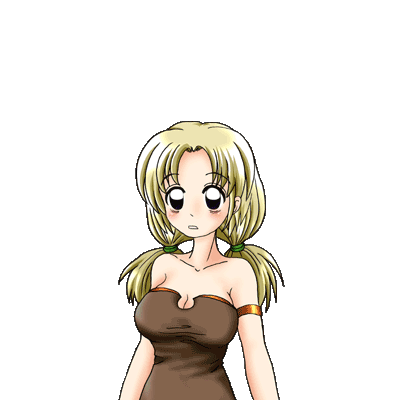
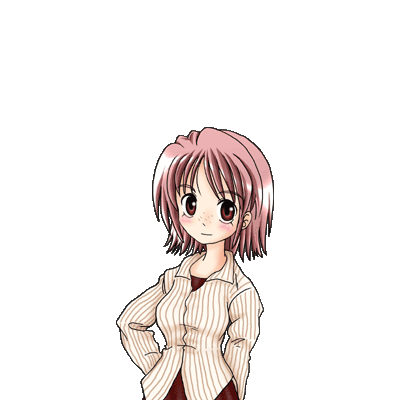
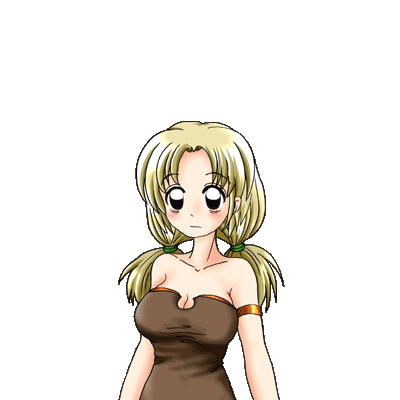
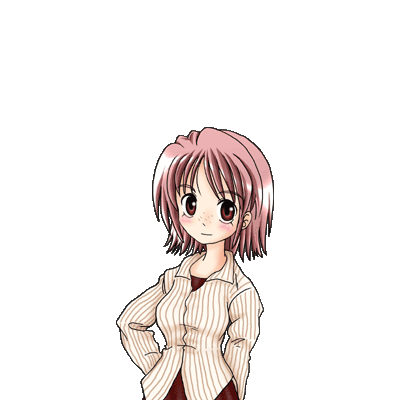
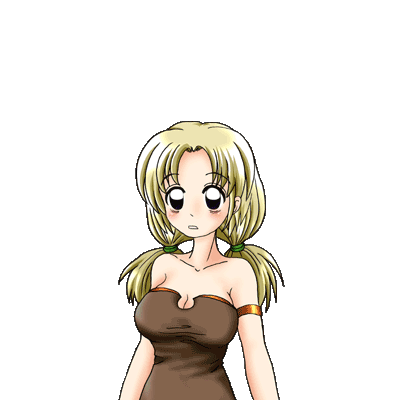
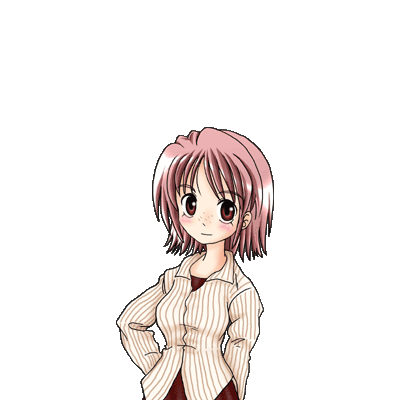
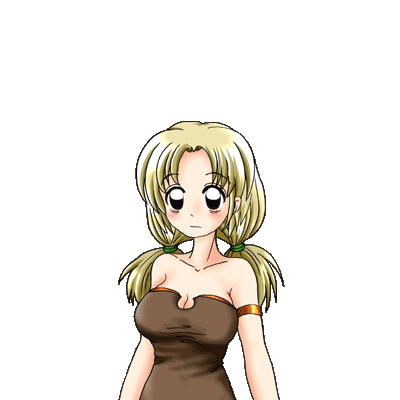
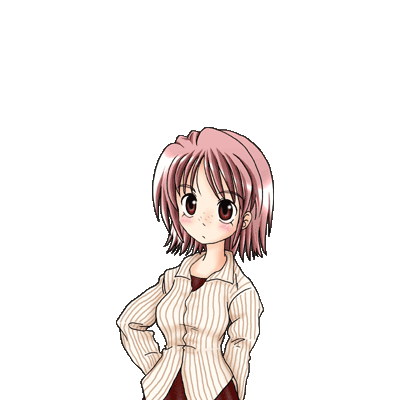
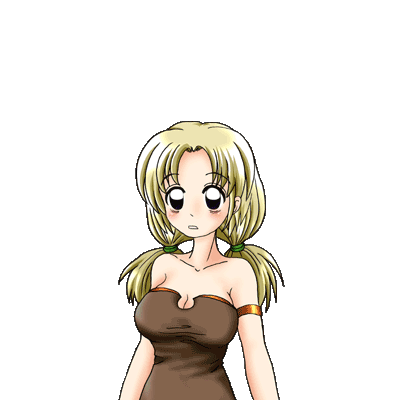
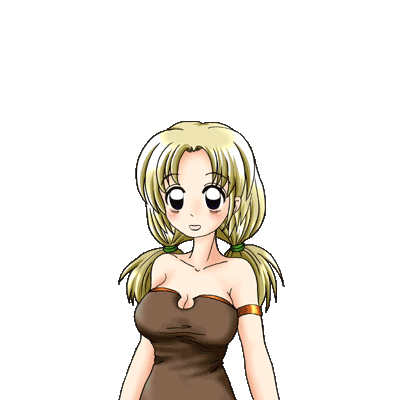
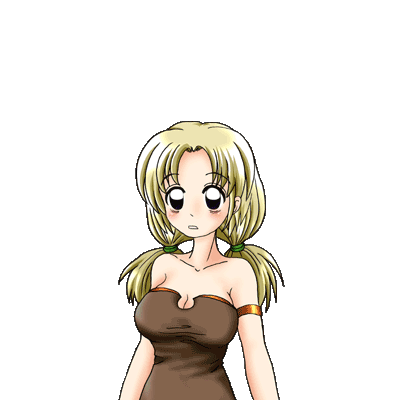
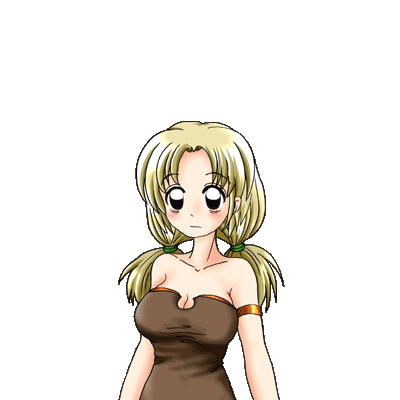
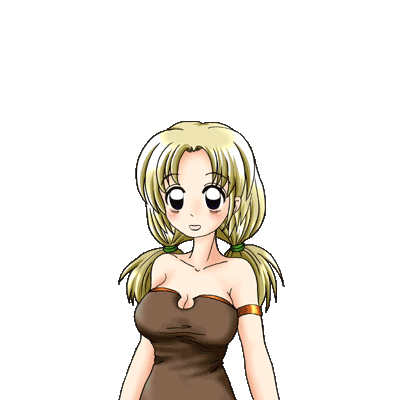
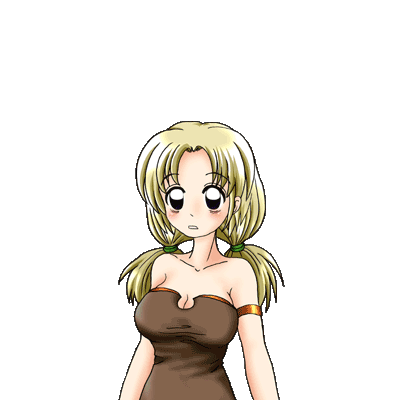
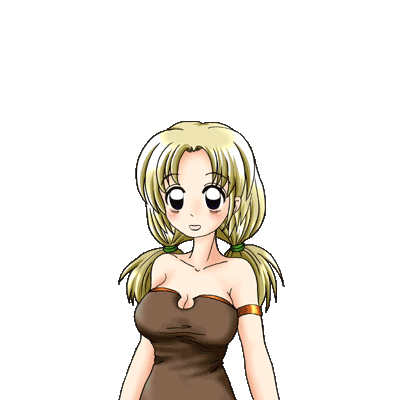
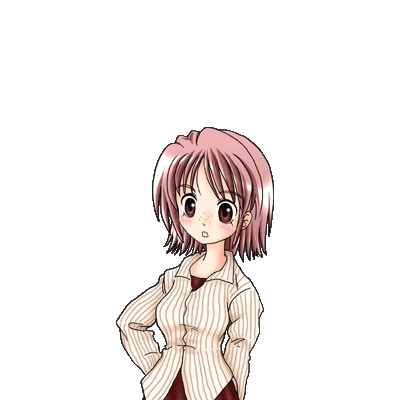
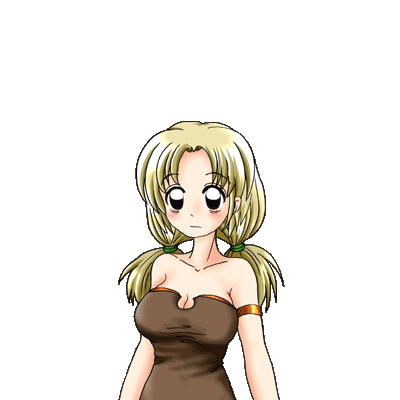
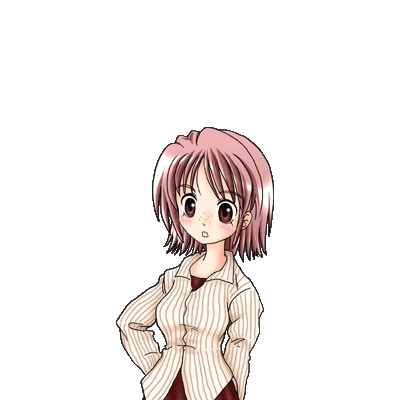
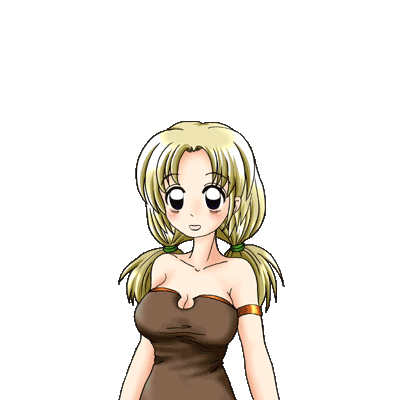




 背景:空
背景:空

 それはPTSDによって誇張された妄想だったのかもしれない。
それはPTSDによって誇張された妄想だったのかもしれない。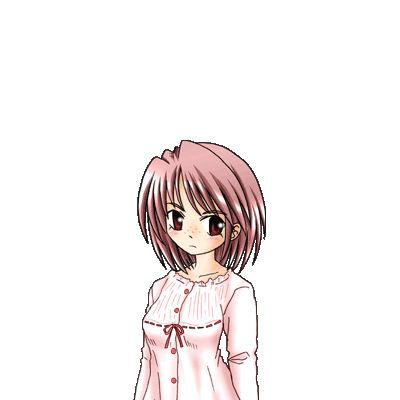




 背景:寝室(和海)
背景:寝室(和海)




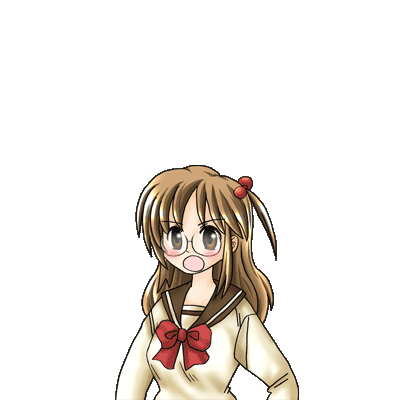


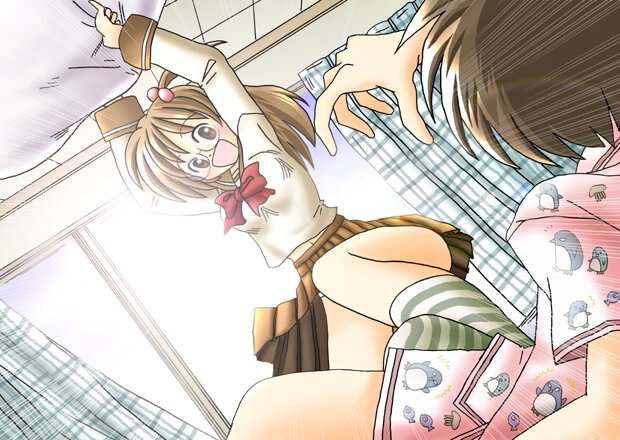

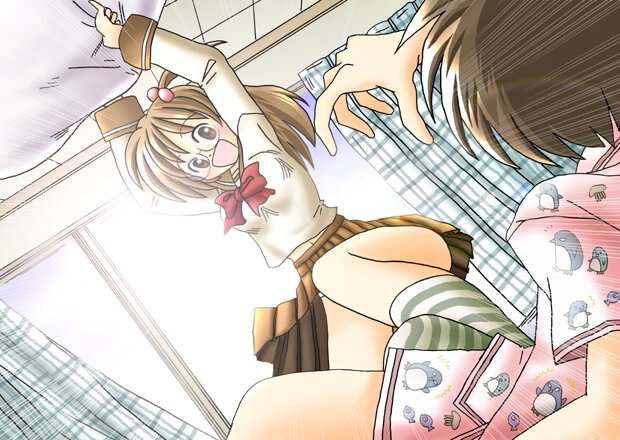

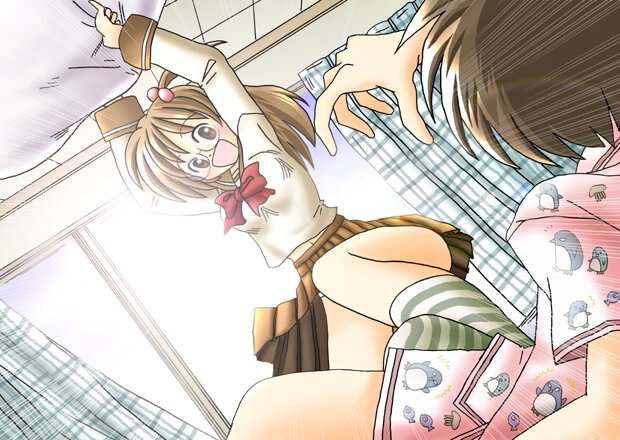


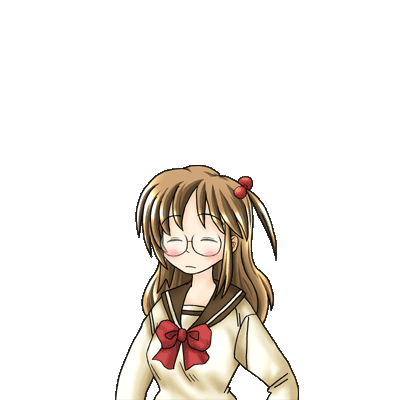

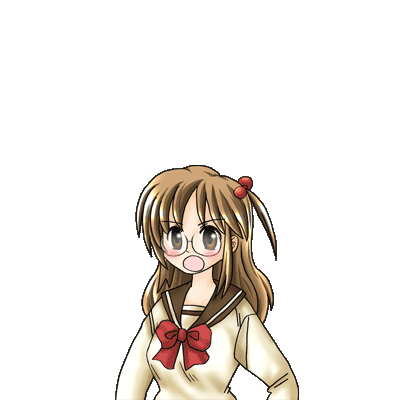

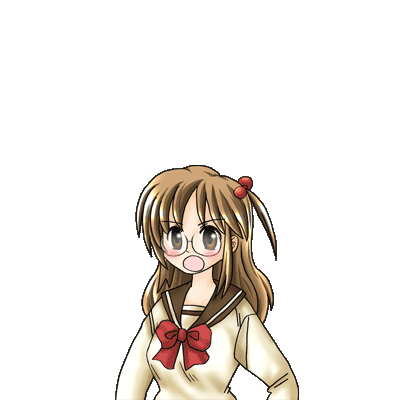




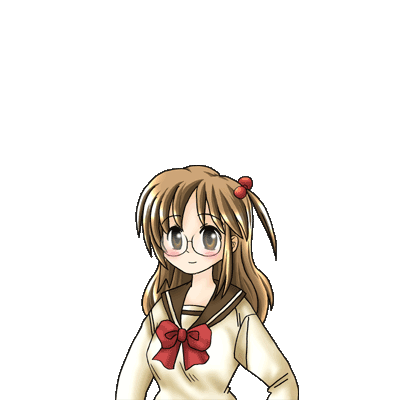





 背景:台所
背景:台所

 一夜明けて、落ち着いてはいたものの、昨夜、脳の一部がタイムスリップした状況は変わらなかった。
一夜明けて、落ち着いてはいたものの、昨夜、脳の一部がタイムスリップした状況は変わらなかった。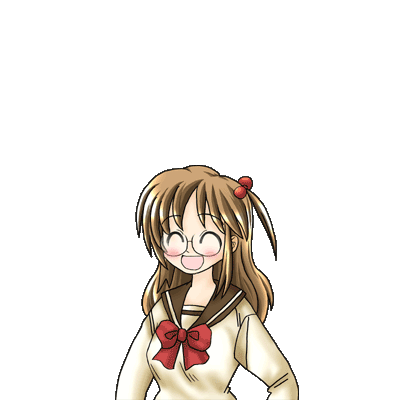















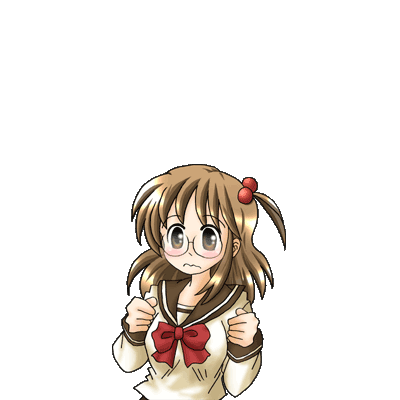

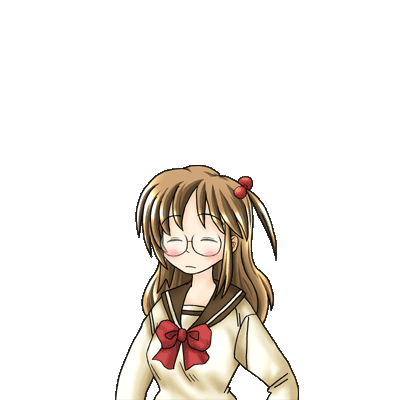



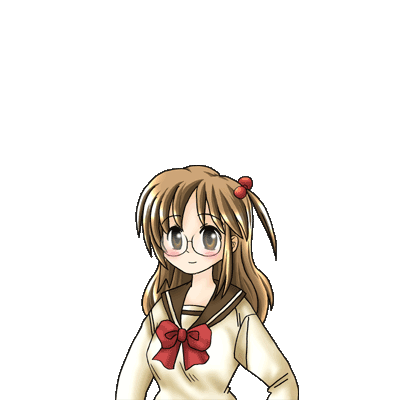





 背景:階段
背景:階段 背景:屋上
背景:屋上


 背景:廊下
背景:廊下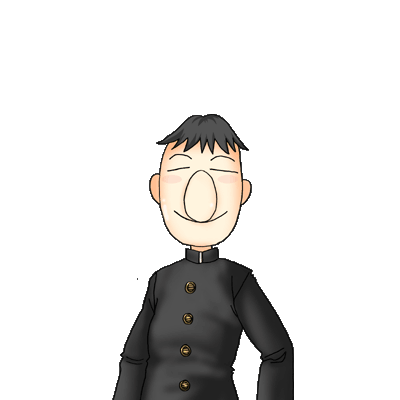

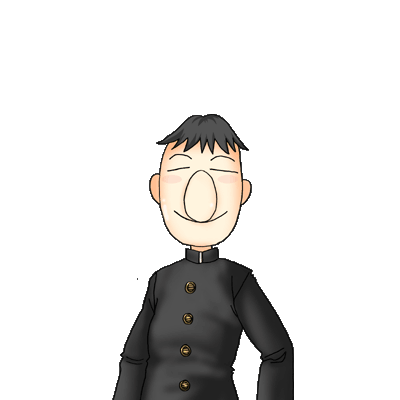

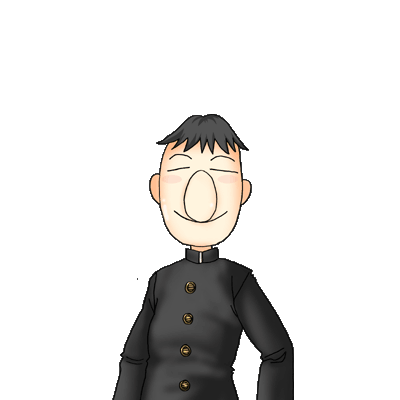

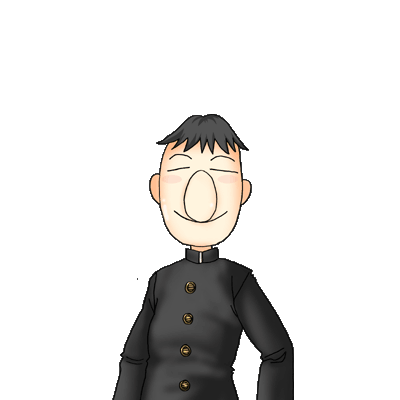

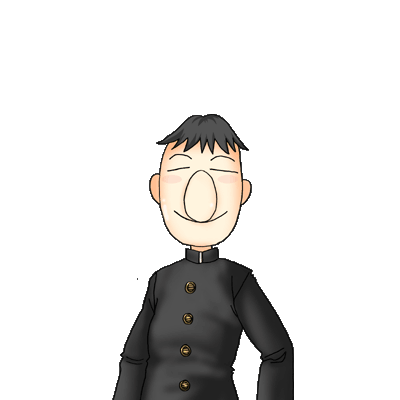

 背景:階段
背景:階段 背景:廊下
背景:廊下



 背景:廊下
背景:廊下 背景:保健室
背景:保健室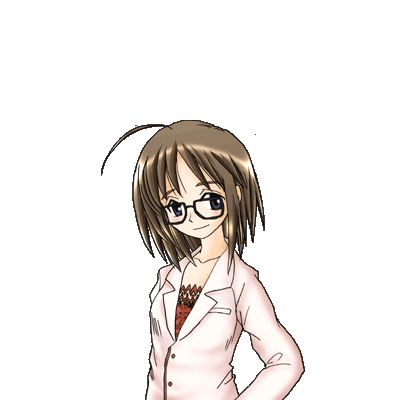




 背景:廊下
背景:廊下







 背景:廊下
背景:廊下



 背景:部室棟
背景:部室棟 背景:部室
背景:部室
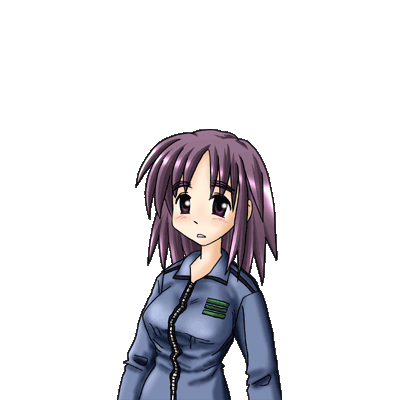


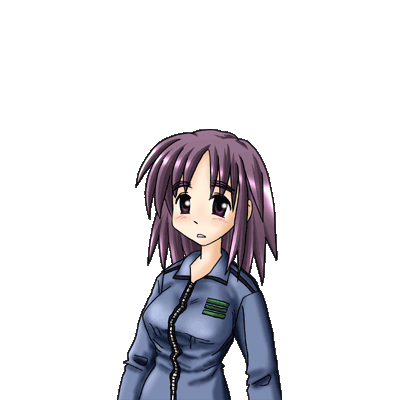

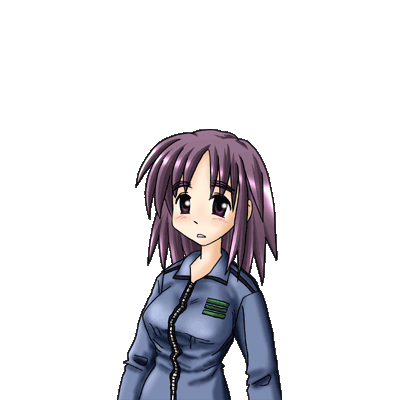
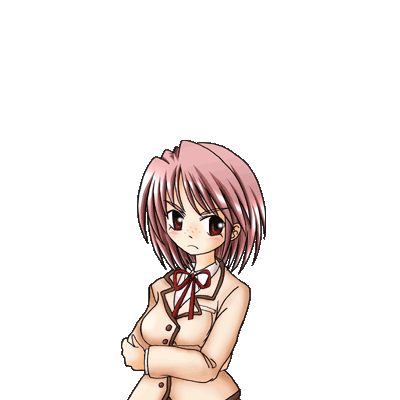

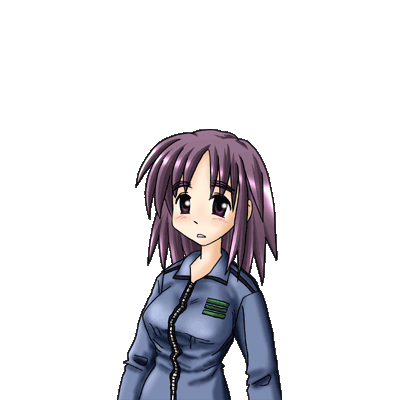




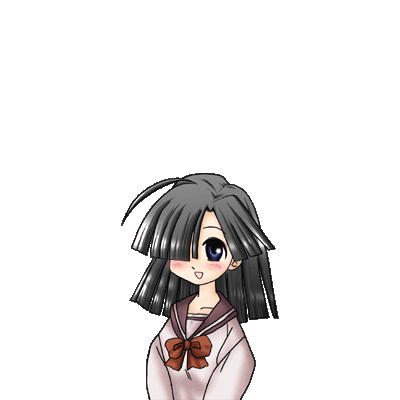
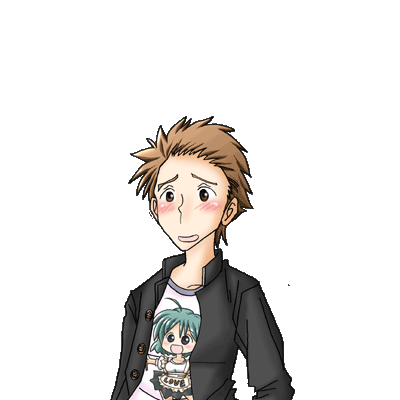
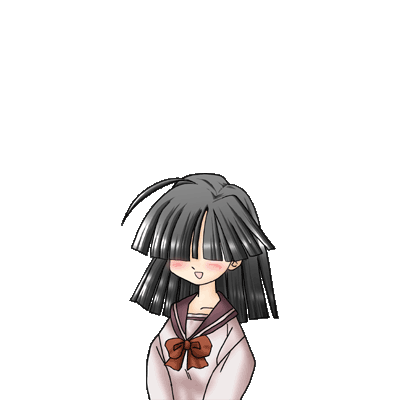
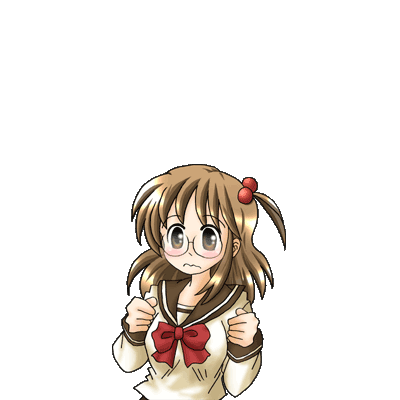
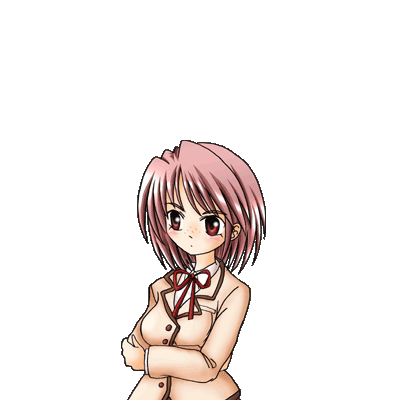






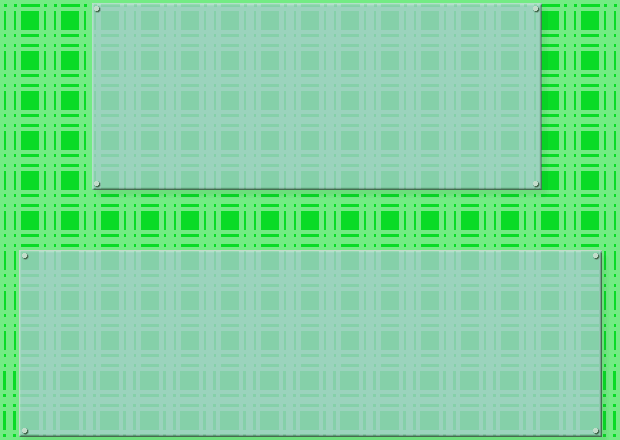


 クイズ1回戦(10問)
クイズ1回戦(10問) 背景:部室
背景:部室

















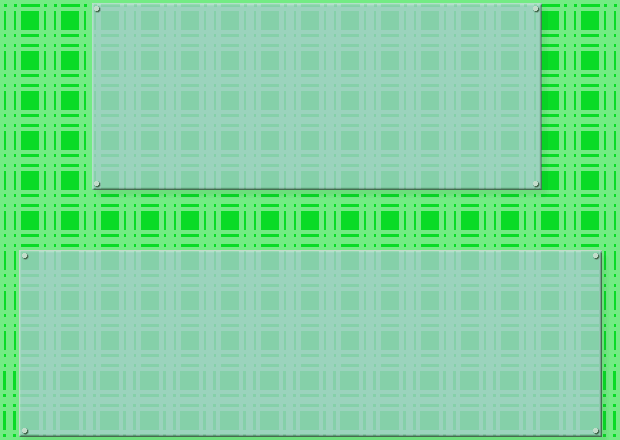


 クイズ2回戦(4問)
クイズ2回戦(4問) 背景:部室
背景:部室
 背景:部室(赤)
背景:部室(赤)
 ここには、いないはずの人間。
ここには、いないはずの人間。 背景:部室(赤)
背景:部室(赤)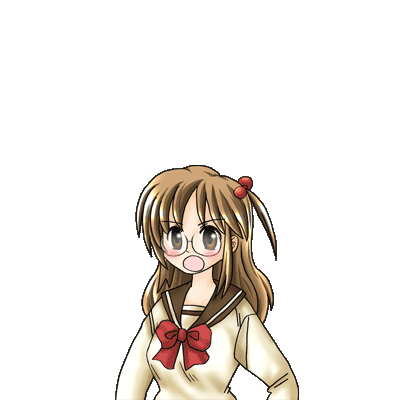
 背景:部室
背景:部室




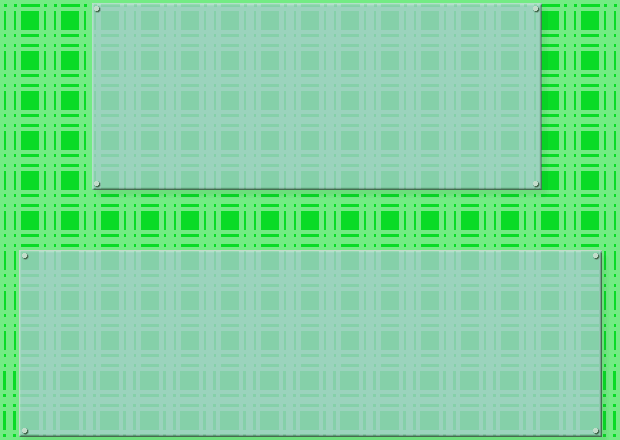


 クイズ3回戦(9問)
クイズ3回戦(9問) 背景:部室(赤)
背景:部室(赤)
 背景:部室(赤)
背景:部室(赤)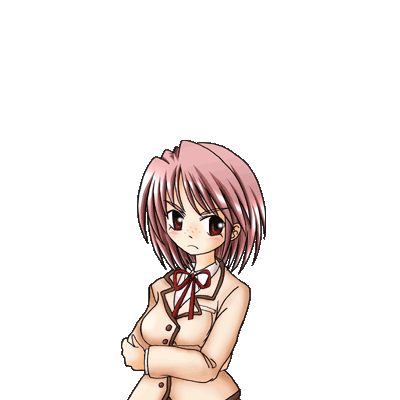

 いい。
いい。 背景:部室(赤)
背景:部室(赤)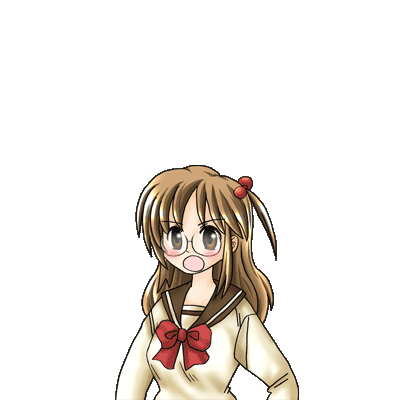




 背景:部室
背景:部室


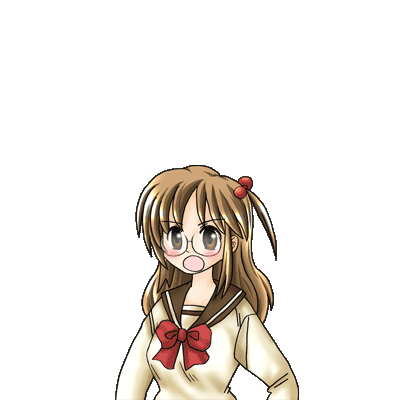

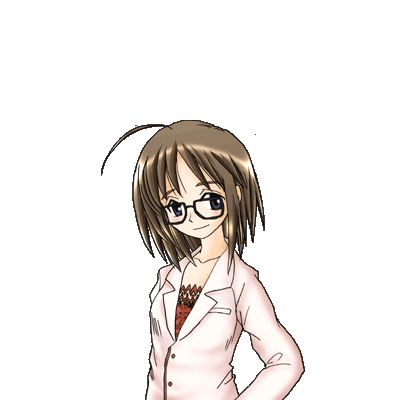
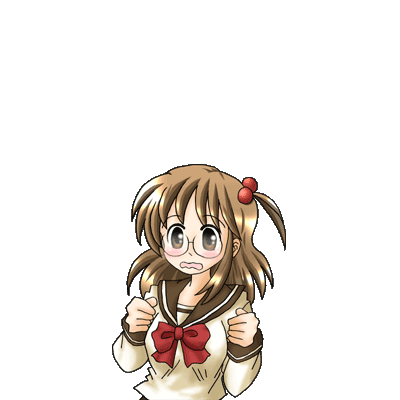
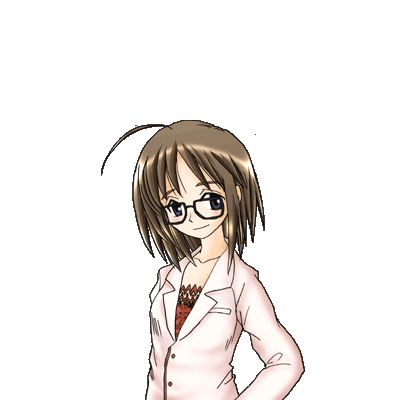
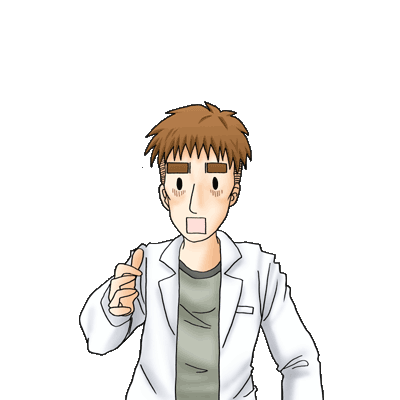
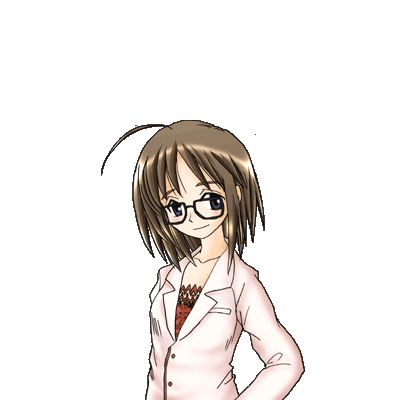
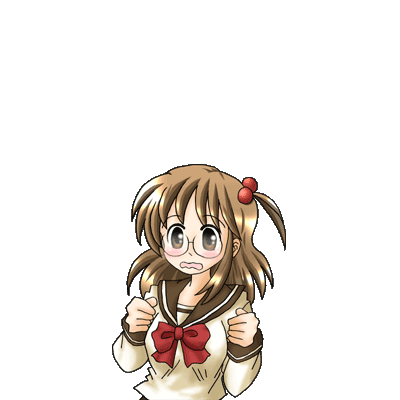
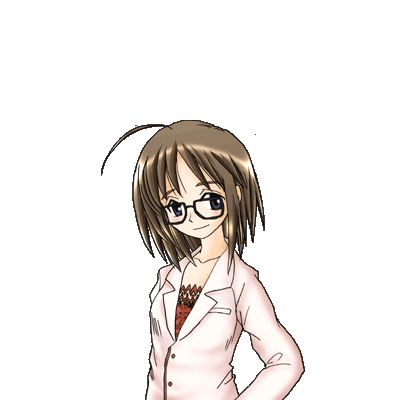




 背景:保健室
背景:保健室

 ぼうっとした意識の中、考えていた。
ぼうっとした意識の中、考えていた。

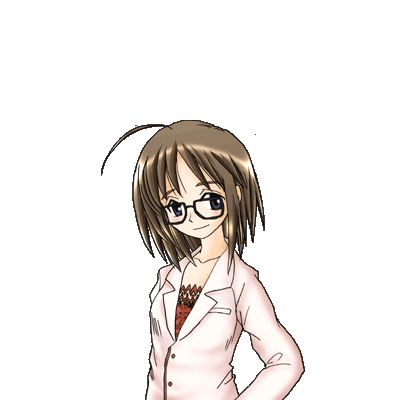

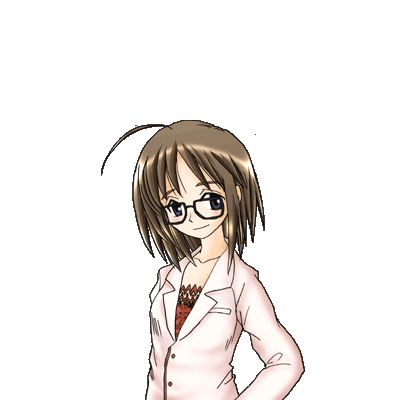

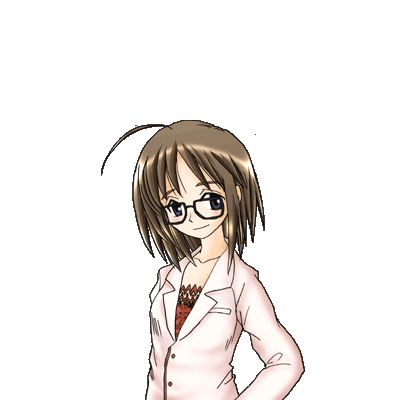

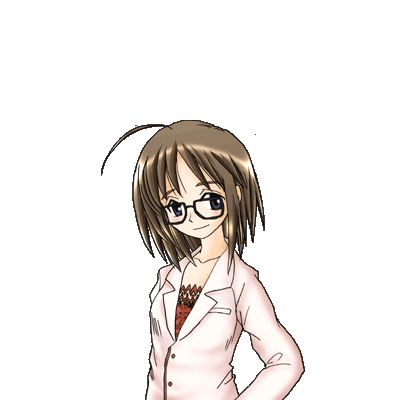

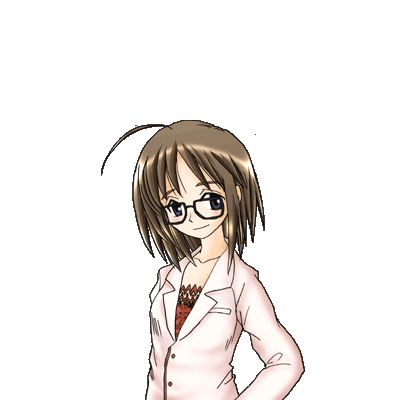
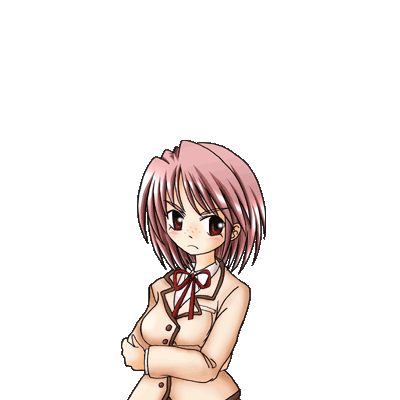


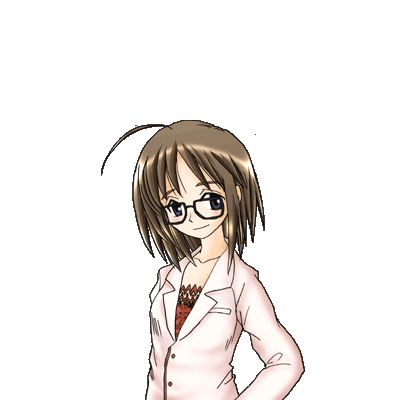

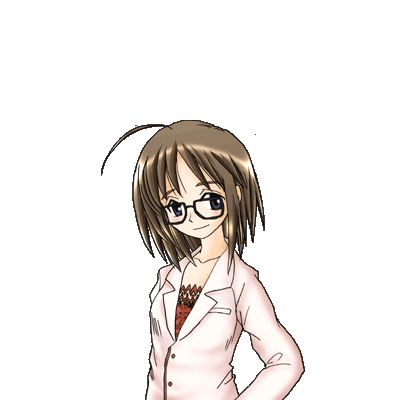

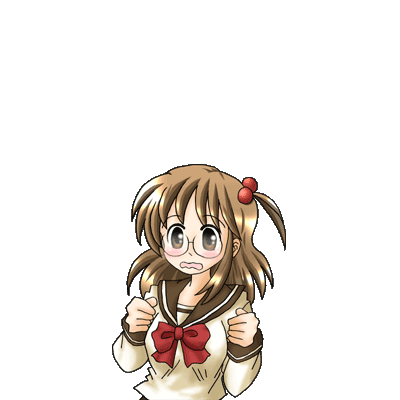





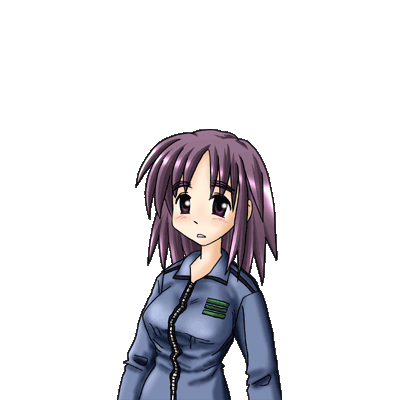



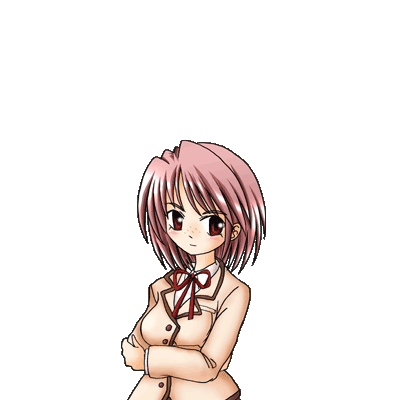

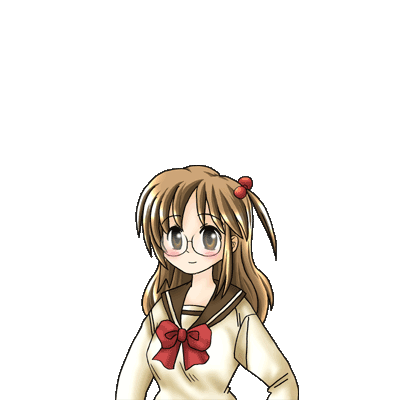

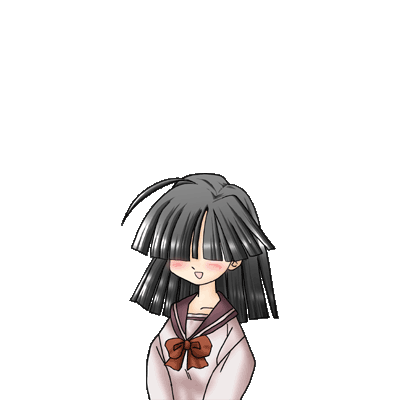
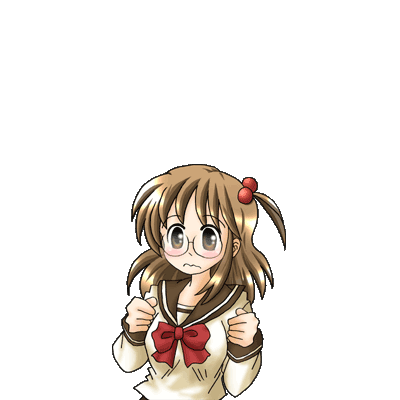

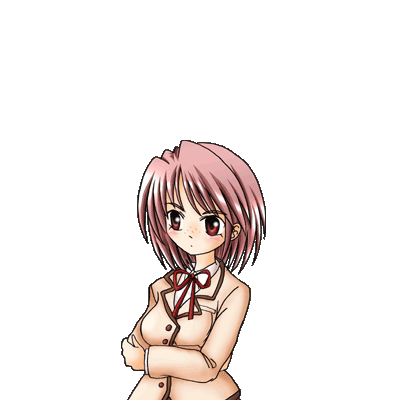



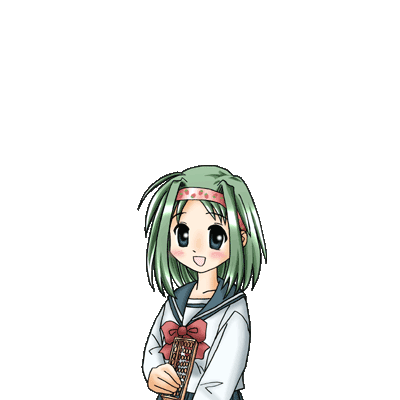

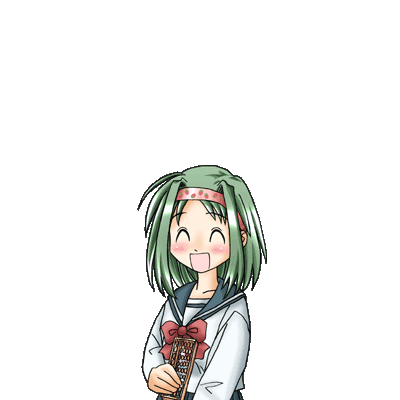




 背景:廊下
背景:廊下

 その頃、保健室の様子を伺うもうひとつの、いや、もうふたつの影があった。
その頃、保健室の様子を伺うもうひとつの、いや、もうふたつの影があった。
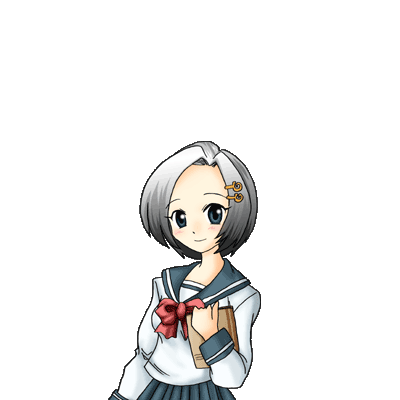

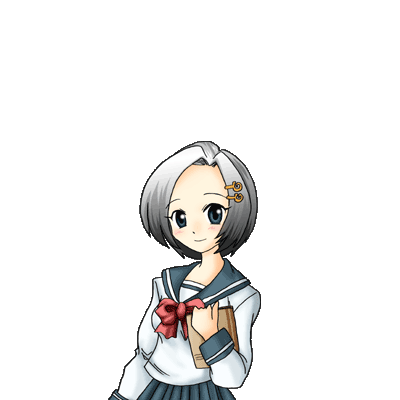

















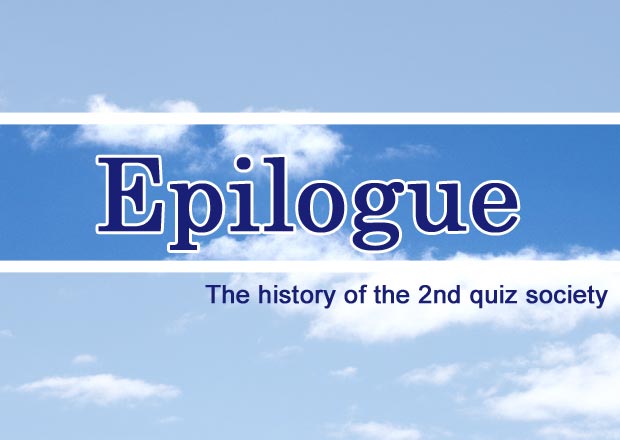
 背景:部室
背景:部室
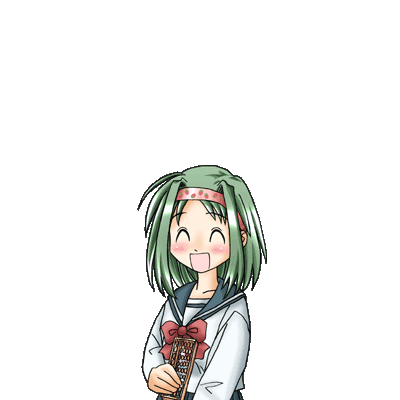
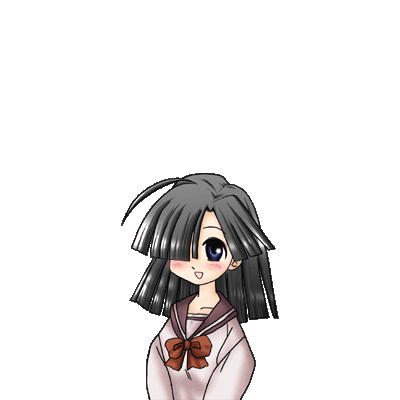
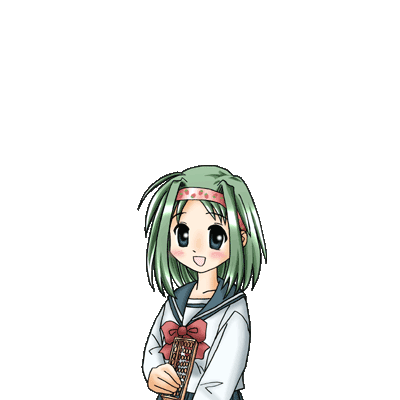
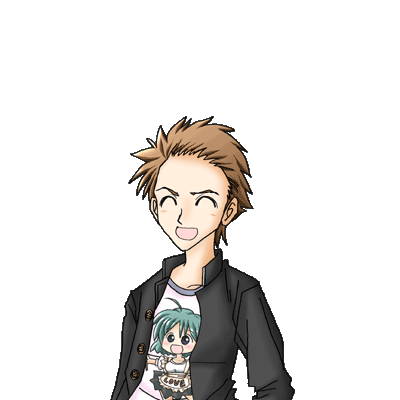
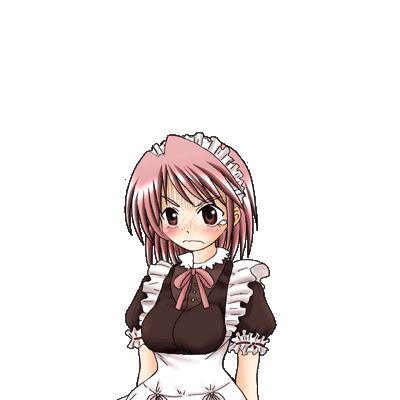

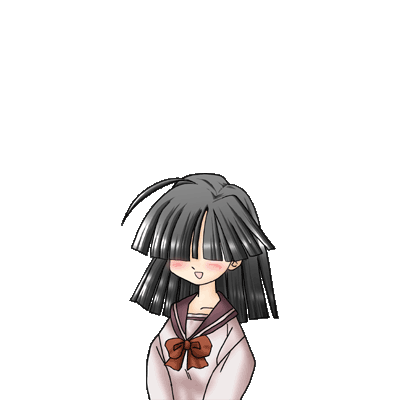
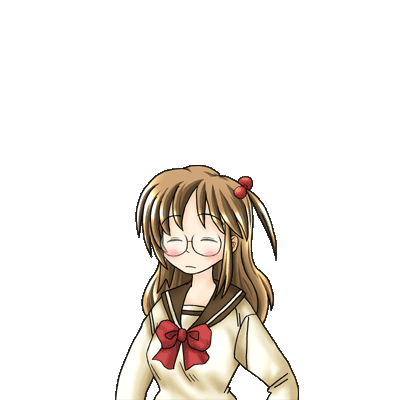



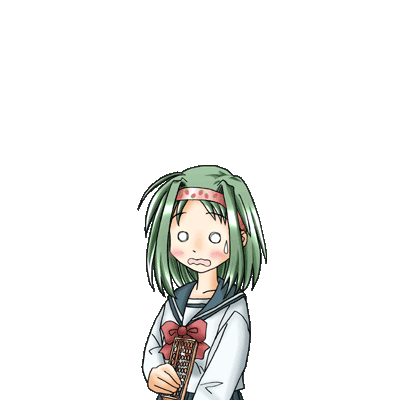
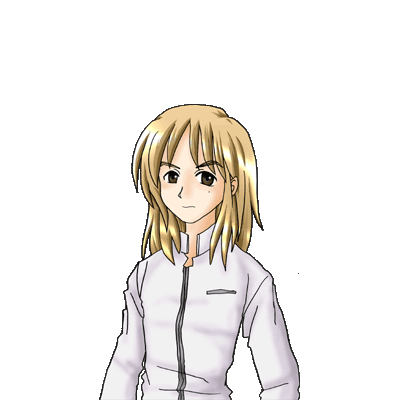
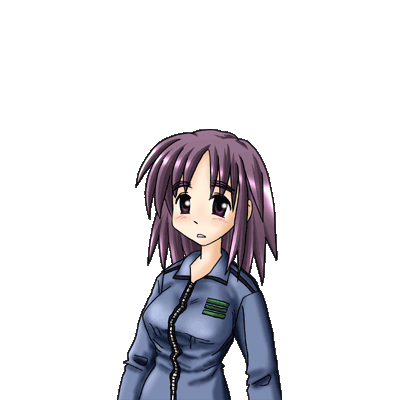
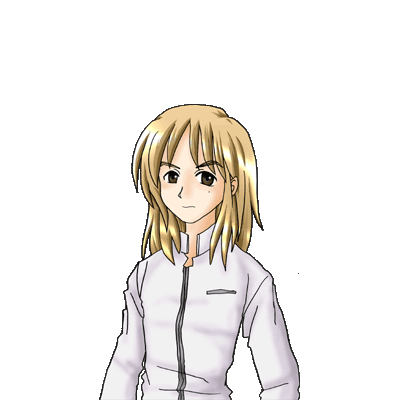

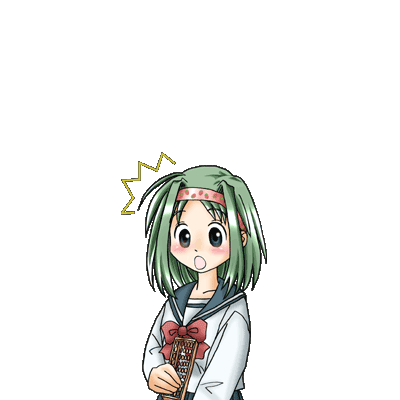

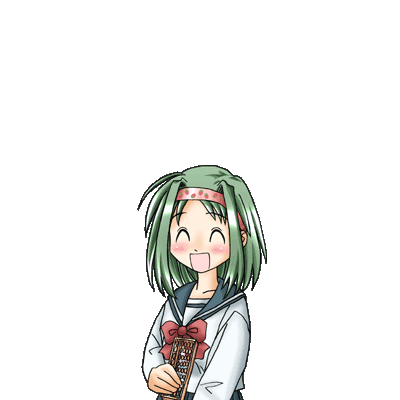
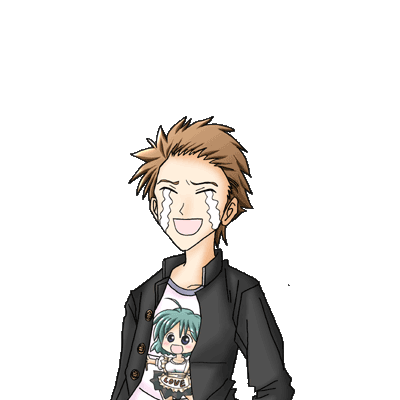
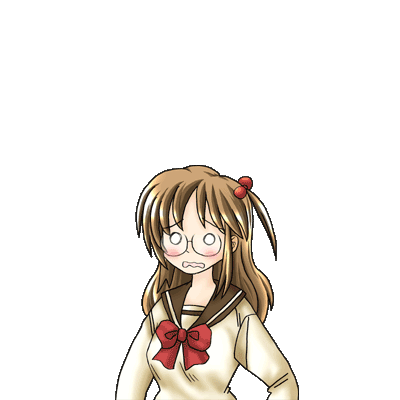
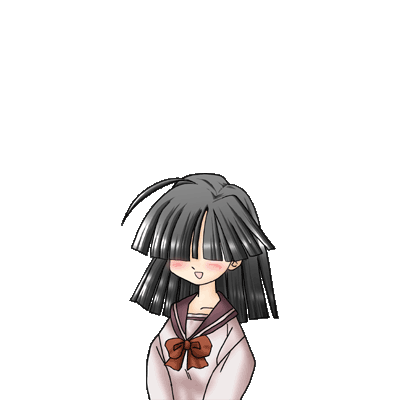





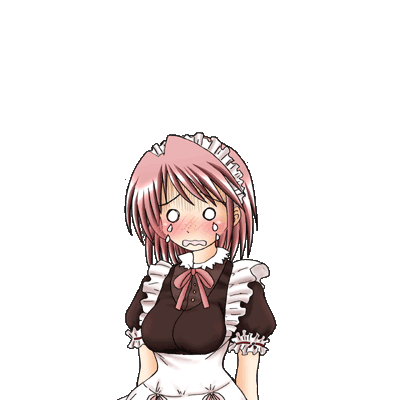





















 背景:部室
背景:部室